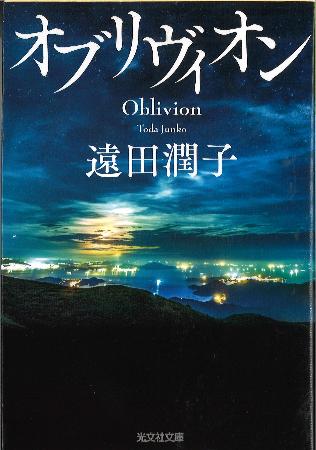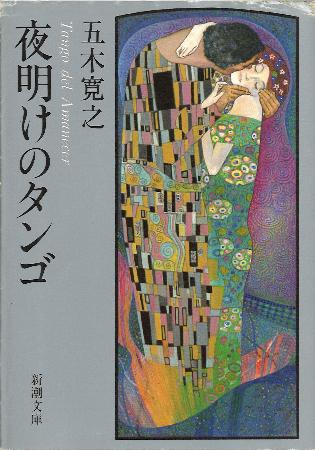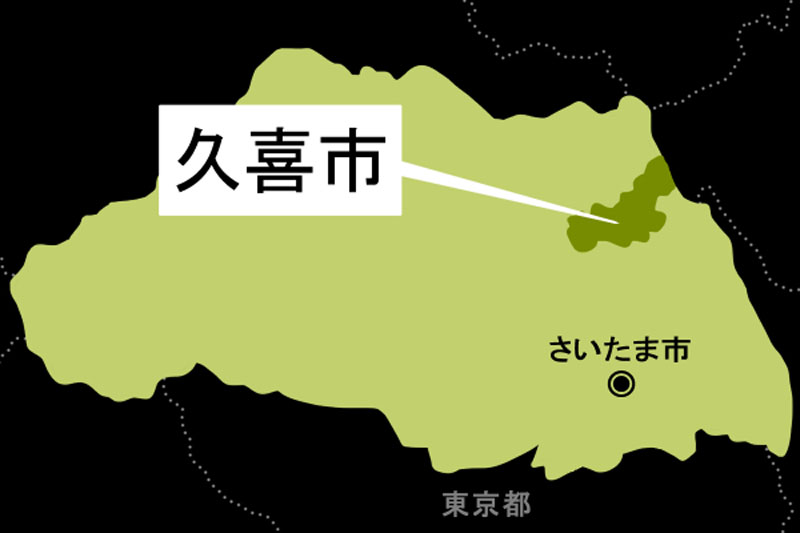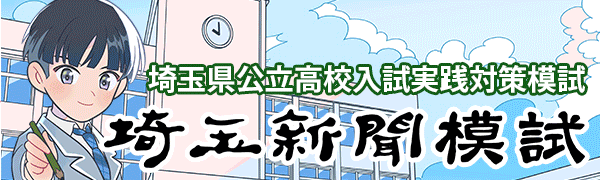【名作文学と音楽(24)】タンゴを忘れるな 遠田潤子『オブリヴィオン』、五木寛之『夜明けのタンゴ』
丸谷才一は元来クラシック党で、それ以外の音楽はピンと来なかったが、タンゴの鬼才、アストル・ピアソラの曲は夢中になって聴いていると、エッセイ『バンドネオン』の中で述べている。クラシック界のスター・ヴァイオリニスト、ギドン・クレーメルがジャンルを越えて取り組んだCD『ピアソラへのオマージュ』をジャケ買いし、引き込まれたのだという(ジャケットのデザインは踊る男女の脚)。そのアルバムにも収録されているピアソラの曲の一つを題名にし、また作中で大きな役割を担わせているのが、遠田潤子(1966~)の『オブリヴィオン』。(2017年)。現在は光文社文庫に入っている。
小説に入る前に、ピアソラのことを少しばかり。人名辞典風に言えば、タンゴの異端児、革命児、破壊者などと様々に呼ばれた1921年生まれのバンドネオン奏者、作曲家である。アルゼンチン生まれだが、少年時代をニューヨークで過ごしている。モダンジャズやクラシックから学んだものをタンゴに持ち込み、独自の刺激的な音楽を作り上げた。1990年代後半からは、前述のクレーメルやチェロ奏者のヨーヨー・マがピアソラ作品のアルバムを録音してクラシック界に<ピアソラ熱>が高まる。ヨーヨー・マの演奏する『リベルタンゴ』は洋酒のテレビCMにも登場した。
遠田の『オブリヴィオン』は、妻を殺害した罪で服役していた吉川森二が仮釈放になり、出所してきたところから始まる。大阪市平野区で文化住宅の一室を借り、木工所で働き始めた森二の身辺に兄でヤクザ稼業の光一、亡き妻の兄でラテン語学者の長嶺圭介が絡んでくる。それがどう展開し、どういう結末を迎えるかは読んでのお楽しみとしておき、本稿は例により、もっぱら本筋の脇で響く音楽に耳を傾ける。
森二がアパートに入居して間もないころ、隣室から奇妙な音が聞こえてきた。長くなるがそのまま引用する。「低く高く、太く細く、うねるように、えぐるように這い回る。あるときは激しく、荒涼とした丘に吹きつける風のように叩きつける。あるときは静かに、曇ったガラス窓の隙間から入ってくる風のように忍び寄る。これは完璧な夜の音だ。陽が沈み闇が落ちてからからはじまる濃密な音楽だ」。
彼の隣人を紹介しておこう。浅黒い肌に彫りの深いラテン系の顔立ちをした18歳の女性・佐藤沙羅。失踪した父が残していったバンドネオンで、彼の好きだった曲『オブリヴィオン』を弾いていた。父はバンドネオン奏者になりたくてアルゼンチンに渡ったがうまくいかず、現地の女性と結婚して日本へ戻った。借金に追われ、妻に去られ、仕事先の金を盗んで逃亡。沙羅はデリヘル嬢になって暮らしを立てている。
森二には10歳になる娘・冬香がいる。実は妻の唯と別の男の間にできた子だ。今は唯の兄である圭介が育てている。唯の相手が誰だったかは森二にも分からない。冬香は本当の父を知りたい一心から、母を殺した憎い<戸籍上の父>を訪ねてきた。森二が不在で会うことができずにいた冬香を、沙羅が自分の部屋に誘い入れた。そこへ森二が帰ってきて一幕あるが、そこは省こう。沙羅が冬香に『オブリヴィオン』を弾いて聞かせているとき、圭介が冬香を連れ戻しに来た。
ここでの騒ぎも割愛する。大事なのはそのあとだ。圭介は去り際、沙羅に向かって「君がさっき弾いていたのは『オブリヴィオン』やな」と言う。「へえ、知ってるん。ピアソラ好きなん?」「タンゴはよく知らない。ただ、クレーメルの演奏で聴いた」。圭介はiPodに入れてあるクレーメルの『オブリヴィオン』を沙羅に聴かせているあいだ、森二に<オブリヴィオン>の意味を知っているかと尋ねる。森二は「知らん」と答える。「忘却や。忘れること、無意識、人事不省、そして、忘れ去られた状態をいう。もしくは……」。森二が「もしくは」と繰り返す。圭介は「恩赦。大赦」と低い声で言ったあと、言葉を続けた。「おまえにはどれも無縁やな。おまえは忘れ去られることもないし、赦されることもない」。森二は打ちのめされた。
<オブリヴィオン>は英語の単語である。意味は圭介が説明した通り。ピアソラがイタリア映画『エンリコ四世』のために書いた曲に、彼のマネージャーが付けた題名なのだという(斎藤充正『アストル・ピアソラ 闘うタンゴ』)。<忘却>を意味するスペイン語<オルビド>やイタリア語<オブリオ>を辞書で調べてみたが、赦しという語義は出ていなかった。アルゼンチンの音楽家によるイタリア映画の主題曲になぜか英語の題名が付けられ、それがこの小説につながったと考えると面白い。
以降の小説の運びには触れずにおく。曲については一つだけ、元々器楽曲だったが、のちに各国語の詞が付けられたことを付け加えておこう。イタリアの女性歌手ミルヴァとピアソラの共演盤『エル・タンゴ』はフランス語による歌唱。アンニュイと抑えた激情の交錯する妖しい雰囲気が立ち昇り、クレーメルの青白く燃える美しい演奏とはまた違った魅力がある。
次に紹介するのは、五木寛之(1932~)の『夜明けのタンゴ』(1980年、のちに新潮文庫)。ごく大ざっぱに要約すると次のようになる。元バンドネオン奏者・水原竜介の経営するタンゴ喫茶<タンゲーロ>が人手に渡りそうになり、かつてのバンド仲間とその周囲の人物が店を救おうと立ち上がる――。筋はそういうことだが、一番の読みどころは文章中に現れ出る、作者のタンゴに関する考え方や思い入れの深さではないだろうか。
彼らの楽団<オルケスタ・ティピカ・コラソン>は、戦後のタンゴ全盛時代に華やかな存在だった。現在はバンマスの木元宏が繊維品雑貨、ピアノの藤野良平が民芸品、専属歌手の洋子がお好み焼きの店をそれぞれ経営し、タンゲーロをたまり場にしている。身売り問題が起きたのは、良平が竜介を引き込んでアルゼンチンから来た<ご老人揃いのオルケスタ>の日本巡演に関わったのが原因。ツアーは不評で、興行会社の社長に祭り上げられた竜介が500万円の負債を抱え込んだ。洋子が昔のステージ衣装を売り払って200万円用意すると言うが、まだ300万円足りない。木元、竜介、洋子がタンゲーロに集まって対応策を協議しようということになった。
木元が店に来たとき、竜介は上の階で書き物をしていた。居合わせた水原家の次女、少々跳ねっ返りの由希がバイトの青年にこんなことを言う。「親父さんのいない時ぐらい、もっと今っぽい音楽かけたら? あたしなんか赤ん坊の時から、子守唄がわりにタンゴきいてきたんだからね。いいかげんききあきちゃったわよ」。「木元のおじさまは、どう?」と振られた元バンマスが「いいタンゴってのは、聴きこめば聴きこむほど味わいが感じられてくるもんでね。私はあきるってことがない」と答えると、由希はここぞとばかりに日頃の思いを吐露する。
「古いタンゴばっかりだからいやなの。それもアルゼンチン・タンゴばっかり。あたしは一九三〇年代のドイツのタンゴが好き。なんかこう、デカダンで、不吉な感じの、人工美の極致みたいな曲があるじゃない。どこか世紀末的な雰囲気のね。ディートリッヒのタンゴも好きよ」
このあたりは五木が語り下ろしたタンゴ論『タンゴは娼婦』の中の、次の発言がベースになっている。「コンチネンタル・タンゴは、ただのダンス音楽ではなく、ヨーロッパのデカダンスと心中するようなかたちで、実に微妙にかかわりあってきた音楽だ。三〇年代にナチのファシズムがヨーロッパをおおっていくなかで、もうこのヨーロッパはだめなんじゃないかという、一種刹那的な絶望感のなかで、すばらしい曲を生み出してきた」。
30年代ドイツのタンゴといえば、有名なところでは『碧空』や『夜のタンゴ』などが思い浮かぶ。豊麗なストリングスの演奏で耳になじんでいるこういった曲さえも、五木の指摘を頭に入れて聴くと、これまでとは違う印象になってくる。また、由希が付け加えた<ディートリッヒのタンゴ>に当てはまりそうなのは、『ジョニー』あたりかと思う。
店を閉め、話し合いが始まろうとしているところへ、歓迎されざる酔っぱらいの常連、高木錠治が現れた。追い返そうとしても、店の前から動かない。そこへ長女の真希が帰ってきた。バレエ一筋に打ち込んできたお人形さんのような美人で、所属バレエ団の翌春公演では『ジゼル』の主役を踊ることになっている。その真希が高木に同情して店に招き入れた。ここから話が新たな展開をみせていく。
高木が突然、店の窮状について詳しく話し始めた。木元が「あんた、どうしてそれを……」と問うと、高木は名刺を差し出し、自分は興信所の調査員で、たまたまこの店が受け持ち区域なので事情を知るに至り、困惑していると打ち明ける。話に加わった高木は最後に、真希の体を触らせてくれと言い出す。あっけにとられた皆に向かって高木はこう述べる。「このお嬢さんは、クラシック・バレエを踊るよりも、むしろ、タンゴを踊るに適した女性だということを申しあげたいのです」。高木は真希に近づき、無造作に彼女の腕をつかんで素早く前に引いた。すると真希はあやうく相手に倒れかかるところを、体をひねって踏みとどまった。そして怒りに燃えた目で高木を見た。
高木は弁じ立てる。「そのバランス。それです。(中略)ぼくの不意の引きに対して、あなたは後ろへ逆らうでもなく、前へ倒れかかるでもなく、相手について行きながら粘りのある自分の動きを保っていた」「タンゴには、あなたのような一瞬の動物的バランスと、そして火のように熱い反抗心を心の中に隠し持った踊り手が必要なんだ。あなたには、それがある」「あなたはタンゴを踊れる人だ。それは間違いない」。
真希の体の反応が的確に表現されているのは、作者の五木が若い頃、実際にタンゴを踊っていた経験があるからだと思う。エッセイ『三月のタンゴ』には、おもに新宿、そのほか都内各所や川崎、横浜などのダンスホールに通ったことが書かれている。「ハマジルと称される横須賀、横浜風のジルバと同様、タンゴもまた私のかなり得意なレパートリイの一つだったのである」。
小説に戻る。高木は10年ほど前、全日本の社交ダンス選手権大会で優勝し、ボストンの全米ダンス選手権でも2位入賞した経歴の持ち主だった。ゆえあってダンス界からは身を引いていたが、ある航空会社が新規直行便PRの一貫でタンゴ・ダンスのコンクールを催すことを知り、真希をパートナーにして出場しようと考えた。賞金の500万円でタンゲーロを救おうというのである。真希はバレエを捨ててその話に乗り、猛練習が始まった。
バレエ育ちの真希がタンゴ…。木元は納得がいかなかった。「私は首をかしげました。タンゴは必ずしも一般のイメージにあるような、華麗かつ社交的な踊りではないと思っているからです。いや、タンゴ・ダンスとは、その出自において卑俗さと、なまなましい生活の匂いをぷんぷん発散させて世に出たものではないか。情熱というより情欲を、華やかさよりも貧しさと怒りを、そして、孤独と絶望の暗いうめき声の中から一筋の光を求めて高まってきた音楽です」。ここにも五木のタンゴ観がにじみ出ている。由希の口を借りて説いたドイツ・タンゴのデカダンス、木元に語らせたアルゼンチン・タンゴの生々しさ、そして高木と真希を媒介にしたタンゴの肉体性が、本作を通して五木の言いたかったことかと思う。
真希は高木の期待に応えた。コンクールの結果は言わずとも分かるだろう。華麗で典雅なサロンのダンスを得意とするライバルに対し、高木・水原組は「思いきり俗っぽく、思いきりエロチックに、そして思いきり野性的で、いやらしいほど露骨な踊り」で立ち向かい、勝利を収めた。決勝に使われた曲は、木元たちが昔よくリクエストをもらったオリジナル『夜明けのタンゴ』だった。なお、この小説はテレビドラマ化され、主演の松坂慶子が同名の主題歌も唄った。歌詞は五木自身が筆を執っている。(松本泰樹・共同通信社記者)
まつもと・やすき 1955年信州生まれ。ピアソラの音楽を知ったのは確か高校生のころだったと記憶する。最近、プロのギター奏者に伴奏してもらうセッションで、『オブリヴィオン』をヴァイオリンで弾いた。