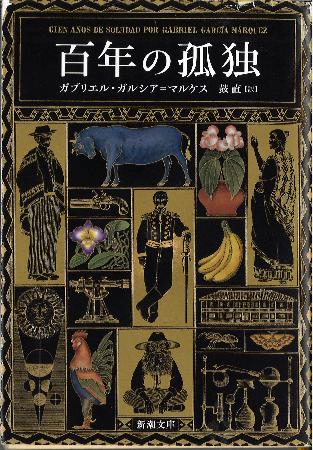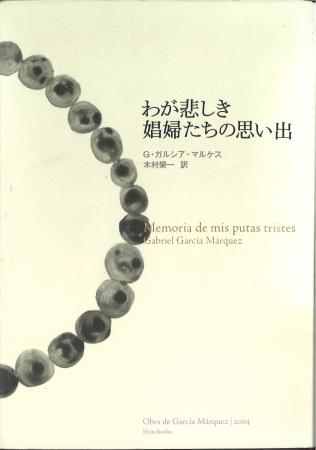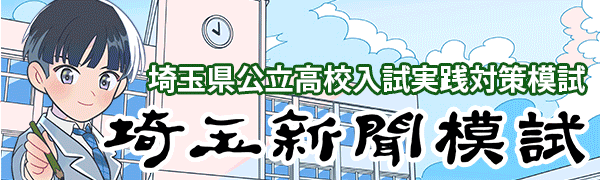【名作文学と音楽(27)】バジェナートは書いた、今度はボレロだ ガブリエル・ガルシア=マルケス『百年の孤独』など3作
1967年に発表されたガブリエル・ガルシア=マルケス(1927~2014)の世界的ベストセラー『百年の孤独』は、邦訳の単行本が1972年に出てから半世紀以上も文庫にならず、「文庫化されたら世界が滅びる」という冗談まで広まっていたという。その『百年の孤独』が作者没後10年にあたる今年の6月末、新潮文庫の1冊としてついに発売された。するとどうだろう、飛ぶように売れてちょっとした社会現象にまでなった。帯の惹句「この世界が滅びる前に――」も効いたか?
ガルシア=マルケスはコロンビア生まれのノーベル賞作家。クラシック音楽(特にロマン派の室内楽)のファンでもあったが、生涯にわたってラテン・アメリカの大衆音楽を愛した。作品には様々な音楽が描き込まれている。まずは『百年の孤独』を読んでみよう。
本作では架空の町マコンドを舞台に、7世代、100年にわたるブエンディア一族の歴史が語られる。鼓直の<訳者あとがき>によると、作者は物語の終わりを1928年に設定しているというので、おおざっぱに19世紀前半から20世紀前半にかけての年代記と見ておく。ただし内容はかなり幻想的である。題名にある<孤独>は、寂しさ、暗さではなく、ブエンディア家の人々に多い<我が道を行く>性格を指すのではないか。私はそう思って読んだ。
開拓当初、マコンドには家が20軒ほどしかなかった。進取の気性に富むホセ・アルカディオ・ブエンディアがリーダー格となり、水汲みの労力や日当たりが平等になるよう家々の配置や通りの方向を定めた。この秩序正しい集落にふさわしい音風景が、全戸に備えられたチャイム付きの時計である。「町は三十分ごとに徐々に進行する同じ和音で活気づき、やがて、一秒の狂いもなくいっせいに鳴りひびくワルツのメロディーとともに正午に達した」
マコンドに新商品や珍奇な品物を売りに来るジプシー(ロマ)の笛や太鼓、シンバルの音は町に非日常をもたらす合図だった。彼らは演奏や踊りで住人を魅了し、ある年には<イタリアふうのロマンスを口ずさむ極彩色の鸚鵡(おうむ)>や<タンバリンの音につられて金の卵を百個も産みおとす雌鶏(めんどり)>などを持って来た。
コロンビアの民衆歌謡バジェナート(サウンドの要はアコーディオン)の象徴的存在である伝説上の音楽家、フランシスコ・エル・オンブレもマコンドに現れた。<ギアナでウォルター・ローリー卿に贈られた古めかしい手風琴>で伴奏をつけ、放浪先のあちこちで起こった事件を歌にして聴かせた。ガルシア=マルケスは、奇怪な挿話を連ねて紡いだ『百年の孤独』を称して450頁のバジェナートのようなものだと言ったことがある。
アコーディオンは作中で、やくざな楽器として描かれる。ホセ・アルカディオ・ブエンディアの妻ウルスラは、アコーディオンを「フランシスコ・エル・オンブレのあとを継いだ浮浪人たちだけが持つ楽器」と軽蔑していた。しかし、一族きっての放蕩者アウレリャノ・セグンドはこの楽器を習得して名人の域に達し、機会を見つけては人前で弾きまくった。
ガルシア=マルケスは子供のころ、アコーディオン弾きの遍歴の歌に惹かれ、幾つかを暗記するほどだった。しかし当時彼の面倒を見ていた祖母は、それをならず者の歌とみなしていたので、<台所の女たち>は隠れて歌ったものだという。アウレリャノ・セグンドの人物造形には、作者自身のそうした記憶も投影されているだろう。
ウルスラは自宅を改築する際、家具や装飾品と一緒に自動ピアノを購入した。機械仕掛けの楽器は分解された部品の形で届いた。輸入商の元から、それを組み立て、流行の曲を仕込んだ紙テープを装着するイタリア人技師、ピエトロ・クレスピが派遣されて来た。金髪で美貌のこの男が、やがてブエンディア一家に波紋を投げかける。
ピエトロ・クレスピはマコンドに居着き、楽器とゼンマイ仕掛けの玩具を扱う店を開いた。ブエンディア家の一員レベーカ(素性は確かならず)と愛し合い、婚約するが、ウルスラの息子に横取りされてしまう。次いで、以前から彼に思いを寄せていたウルスラの娘アマランタと恋仲になるも、求婚を拒絶されて自殺した。発見されたときには、店にあるすべてのオルゴールの蓋が開き、でたらめの合奏が鳴り響いていた。
各戸の時計が一秒の狂いもなく奏でるワルツから、自殺の現場で響いていたオルゴールのでたらめな合奏へ。その間には、ホセ・アルカディオ・ブエンディアが新着の自動ピアノに興味を抱いて分解したものの、組み立て直しに失敗してでたらめな曲がとめどなく流れ出したこともあった。混乱した響きは、のちにマコンドが辿る運命(最後は蜃気楼のように消えて滅びる)の前兆なのだろうか。
先を急ぎすぎた。クラビコードという楽器も出てくるのだった。音楽事典によると、16世紀から19世紀初頭まで用いられた箱形の鍵盤楽器で、小型のものには脚がなかった。放蕩者アウレリャノ・セグンドの不釣り合いな妻、フェルナンダが8年間過ごした修道院で習い覚えた。彼女はラテン語で詩を作ることができ、外国の君主と国事について語り、教皇と神について論じられるだけの知識を身に付けていた。典雅なクラビコードをたしなむフェルナンダ、やくざな楽器アコーディオンを弾いて騒ぐのが好きなアウレリャノ・セグンド。好む楽器においても対照的な夫婦は、それぞれの道(孤独な道?)を歩いている。
音楽への言及はまだ続くがこのぐらいにしよう。ところで、大の音楽好きであるガルシア=マルケスが本作執筆時に持っていたレコードは、たった2枚だったという。ドビュッシーの『前奏曲集』とビートルズの『ア・ハード・デイズ・ナイト』。すり切れるまで聴いたそうである。
次に取り上げるのは、1985年発表の『コレラの時代の愛』(新潮社刊、木村榮一訳)。ガルシア=マルケスは本作に着手する前のインタビューで「バジェナートはもう書いたから、今度はボレロを書きたい」と発言している(作家自身が設立した非営利団体ガボ財団のホームページより)。ボレロはキューバからラテン・アメリカ諸国に広まったロマンティックな音楽(『ベサメ・ムーチョ』『アドロ』など)である。ガルシア=マルケスはその言葉どおり、恋を、それも一通りではない恋をテーマとする小説を書いた。
物語の発端は19世紀後半。見習い郵便局員のフロレンティーノ・アリーサが、13歳の女学生フェルミーナ・ダーサと出会って恋に落ちる。二人は密かに手紙を交わすようになり、やがて結婚の約束までした。フェルミーナは結局、親の介入もあって名門の医師フベナル・ウルビーノ博士(コレラの伝染を食い止めた功績あり)の妻になるが、フロレンティーノは半世紀以上も彼女を想い続け、博士の急死を知るや、好機到来とばかりに失った恋の成就に向かって走り出す――。
恋に付き物の音楽といえばセレナーデである。愛しい人の窓辺を見上げて演奏する甘く美しい調べ。フェルミーナをめぐる二人の男性も、それぞれの方法でセレナーデを彼女の耳に届けた。
ヴァイオリンが弾けたフロレンティーノは、自作のワルツ『王冠をいただいた女神』を彼女の寝室に向けて演奏した。家の前まで行くのは遠慮し、最初は公園から、そのあとは丘の上の墓地などから音楽のラヴ・レターを送った。
ヴァイオリンでセレナーデを演奏する若い男にはモデルがあった。ガルシア=マルケスの父である。作者の自伝『生きて、語り伝える』(新潮社刊、旦敬介訳)には、『踊りが終わって』という<果てしなく甘いワルツ>が、父お得意のレパートリーだったと書いてある。「母が語るところによれば、明け方近くにそのヴァイオリンを聞くと誰しもはらはらと涙を流さずにはいられなかったという」
一方ウルビーノ博士は、自分でもピアノが弾けたが、町に来演した著名ピアニストの力を借りた。終演後、ラバの引く荷車でピアノを運ばせ、彼に<一世を風靡したセレナーデ>を弾いてもらったのである。
博士はフロレンティーノに増して音楽に熱心だった。長年見捨てられていた劇場の復活に尽力したほか、コルトー(ピアノ)、ティボー(ヴァイオリン)、カザルス(チェロ)のトリオを招聘しようと奔走することもあった。新婚旅行でパリを訪れていた時には、オッフェンバック作曲『ホフマン物語』(1881年)の初演を聴いている。晩年、飼っていたオウムにフランスのキャバレー歌手イヴェット・ギルベールとアリスティド・ブリュアンのレコードを毎日聴かせ、覚え込ませることに成功した。そのオウムが逃げ出した時、博士はつかまえようとして登った梯子から落下し、命を落としたのである。
フェルミーナと音楽の関わりはどうだったか。義母に「ピアノも弾けないようなら、品のいい婦人とはいえないと思いますよ」と言われて困った。幼年時代に習ってはいたが<ガレー船のようなピアノ教室で過ごした苦い経験>を忘れられなかったのだ。博士が中に入り、ピアノではなくハープを習うことになったが、これもうまくいかなかった。夫を亡くしてからはラジオでメレンゲやプレーナといったラテン音楽を聴いた。
作中には他にも音楽好きの人物が出てくるが、最後はやはりフロレンティーノに締めてもらおう。彼は博士の死後、フェルミーナとの距離を少しずつ縮め、一緒に川船の旅をするところまで持って行った。船上の楽団からヴァイオリンを借りて弾いたのは、もちろん『王冠をいただく女神』。数時間後に無理やり止められるまで、この曲を奏で続けた。
『わが悲しき娼婦たちの思い出』(新潮社刊、木村榮一訳)は2004年、作者が77歳の年に発表された中篇である。川端康成の『眠れる美女』から想を得たという。語り手の<私>が生まれたのは19世紀の末ごろと思われる。新聞社で長く働き、今は音楽と演劇のコラムや日曜紙面用の記事を書いている。作中に出てくる音楽は主にクラシックとボレロ。
「満九十歳の誕生日に、うら若い処女を狂ったように愛して、自分の誕生祝いにしようと考えた」という刺激の強い書き出しで始まる。語り手の<私>は娼家の女主人ローサ・カバルカスに電話をして望みを伝えた。誕生日の前日、カザルスが弾くバッハの無伴奏組曲を聴きながらまどろんでいるところへ、彼女から電話がかかってきた。<十四になるかならず>の女の子が見つかったというので、<私>は娼家に出かけていく。使用中の部屋のラジオから、メキシコの女性歌手トーニャ・ラ・ネグラの歌声が聞こえた。ローサ・カバルカスは大きく息をついて「ボレロは私の命なのよ」と言った。「私もそう思っているが、文章に書くだけの勇気がなくてね」と語り手。
部屋に入ると、女の子は寝ていた。昼間の仕事で疲れている上に鎮静剤を飲まされていて、一晩中目を覚まさなかった。<私>は彼女の体を軽く触るが途中でやめた。「そこで、耳元で『デルガディーナのベッドのまわりは天使で一杯』をうたってやった」。曲はメキシコの民謡『デルガディーナ』のことだろう。<私>は名前を知らぬこの子を<デルガディーナ>と呼ぶことにした。
その後も<私>はデルガディーナの客になったが、ポルノ的な場面はない。ふんだんにあるのは音楽だ。<私>は幻想の中で、<プッチーニの愛のデュエット><アグスティン・ララのボレロ><ガルデルのタンゴ>をデルガディーナと一緒に歌った(ララは『ソラメンテ・ウナ・ベス』などで知られる作曲家、カルロス・ガルデルはタンゴの大歌手)。
クラシックの方では、サティ、ワグナー、ドビュッシー、ブルックナー、ブラームスなどの名前と曲が出てくる。その中に、こういう場面がある。<私>がジャック・ティボーとアルフレッド・コルトーのリサイタルを聴きに行ったときのことだ。演奏されたのはフランクのヴァイオリン・ソナタだった。楽屋を訪ねた<私>は彼らに「シューマンのソナタはすばらしかったですね」と見当違いのことを言い、大恥をかいてしまう。この出来事は彼が90歳の時となっているが、それならティボーもコルトーもとっくに彼岸の人である。
小説の終わり近くで<私>は死が間近に迫ってきたことを実感している。蒸し暑い演奏会場でこんなことがあった。「最後に、アレグレット・ポコ・モッソが鳴り響いたが、そのときに、死を迎える前に運命が私に最後のコンサートをもたらしてくれたのだと感じて、身体が震えるような感動を覚えた」。曲の名を言わず、ただ「やや速く、少し躍動して」という発想記号で示したのはなぜか? 一番有名な「アレグレット・ポコ・モッソ」は何かと考えてみた。そうだ、フランクのヴァイオリン・ソナタ最終楽章ではないか!(松本泰樹・共同通信記者)
まつもと・やすき 1955年信州生まれ。『百年の孤独』の文庫初版は、高額のプレミアム付きで転売の対象になっているようだ。定価は税込1375円だが、1万円近い売値もネット上で見た。私が古書店で買ったのは2刷で、税込220円だった。