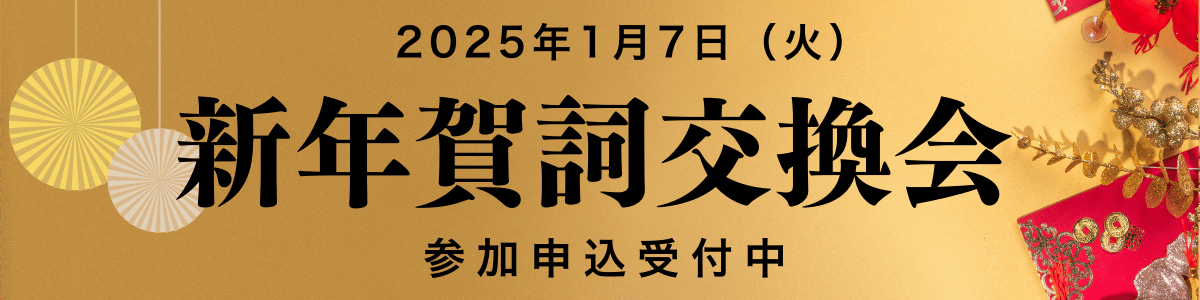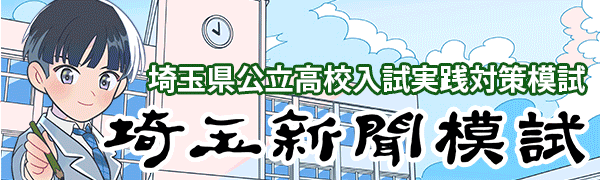【シネマの花道(5)】人間洞察が生んだ演技と文章 高峰秀子生誕100年
天才子役と呼ばれ、少女スターを経て大女優となった。日本映画史でもまれな俳優人生を歩んだ高峰秀子は1924年生まれ、今年は生誕100年に当たる。亡くなって14年たつが、出演作の上映や関連書籍の刊行が相次ぐなど今も人気は衰えない。年配から若者まで幅広い世代に愛されているのはなぜか。
高峰の人生を決定づけたのはまだ幼かったころ、養父に背負われて松竹蒲田撮影所に行った春の日のことだった。当時のスター川田芳子主演映画「母」の子役オーディションが偶然行われており、子どもたちの列の最後尾に並ばされた。野村芳亭監督の目に留まった高峰は、5歳にして有無を言わさず子役となり、あらゆる撮影現場に引っ張りだことなる。
「母」の高峰はおかっぱ頭で母親に甘える少女役がなんとも愛らしいが、自伝エッセー「わたしの渡世日記」によると「ピチャンと墨を落として、ワーンと泣け」という注文に「私は墨くらい上手にすれるのに」「なんでこんなアホらしいことをしなければならないのか」と不満だったという。撮影をスムーズに進めるために機嫌を取ってくる大人たちを子ども心にも滑稽だと感じており、当時から冷静に周りを観察していたことがうかがえる。
多くの子役たちが成長とともに輝きを失っていく中、高峰は思春期の壁を乗り越えていく。山本嘉次郎監督の「綴方教室」「馬」などが大ヒット。時あたかも戦争へと向かう昭和10年代、高峰のブロマイドを後生大事に持ち歩いた兵隊から一日に何十通ものファンレターが軍事郵便で届いたという。「兵士たちは、私の作り笑いを承知の上で、それでも優しく胸のポケットにおさめてくれた、と思うと、私はまた、やりきれなさで身の置きどころがないような気持ちになる」(「わたしの渡世日記」)
高峰の代表作といえば「二十四の瞳」「浮雲」を挙げる人が多いが、どちらの作品にも戦争の影が色濃く差している。木下恵介監督の「二十四の瞳」は小豆島の分教場に赴任した新米小学校教師の大石先生と12人の生徒たちの交流を描いた映画だが、大石先生の初々しさと子どもたちのけなげさ、戦争に翻弄された彼らの人生がオーバーラップし、何度見ても涙を禁じ得ない。
「カルメン故郷に帰る」「銀座カンカン娘」などで見せた明るさも戦後の開放感に満ちた空気にぴったりで、清新さが高峰の一つの魅力だったが、成瀬巳喜男監督の「浮雲」では一転、戦争の暗部を引きずって生きる女を陰影深く演じた。
戦時中、南方へ渡ったゆき子(高峰)は妻のある富岡(森雅之)と深い関係になる。引き揚げ後、富岡のもとを訪ねて冷たくあしらわれたゆき子だが思いを断ちきれず、泥沼のような関係をずるずると続けていく。
「なぜ返事くださらないの」「私のことはどうなってもいいの? そんな簡単なものなの?」「ぼんやり待ってたのがバカだったのよ」―。駄目な男と分かっていながら別れられない女は、時に恨み言を言い、時に真っすぐ愛を求める。終戦直後の寒々しいバラックで、雨が降り続く屋久島の薄暗い民家で、離れようにも離れられない男と女のさがが描かれる。
大石先生とゆき子は正反対の役柄と言ってもいいが、どちらも高峰はごく自然にその人物として映画の中に存在していて違和感がない。その後も「華岡青洲の妻」で嫁との確執を繰り広げるしゅうとめ、「恍惚の人」で認知症の義父を介護する嫁と、その時々の年齢にふさわしい幅広い役を演じているが、どの作品もスクリーンに映っているのは観客の感情を揺さぶる登場人物であって「スター高峰秀子」ではない。
この自然さ、幅の広さはどこから来るのか。高峰の養女で文筆家の斎藤明美は「押し出さないこと」にあるという。「高峰の演技は〝引く魅力〟。主役であっても自分が目立てばいいのではなく、作品の調和を考えていた。映画はスタッフや俳優みんなで背負うものだというセオリーがよく分かっていた。100%で演じるのではなく、80で演じた結果が120に見えるのだと思う」
300本を超す映画に出演した高峰の最後の作品「衝動殺人 息子よ」が公開されたのは1979年。相前後するように力を注ぐようになったのが文筆活動だった。自身、いつのまにかやらされていた俳優という仕事より、文章を書くことの方が好きだったという。近年の若い女性ファンは、エッセーを通じて高峰の生き方に引かれたという人が多い。
人生で出会った信頼すべき人々とのエピソード。気に入ったものだけを身の回りに置く暮らし。そして夫で映画監督・脚本家の松山善三との静かな生活。高峰が書く文章は凝った名文ではなく、平易でありながらユーモアにあふれ、一本しんが通っていた。スッと背筋が伸びた姿が伝わってくる文章だ。
「映画にしろ随筆にしろ生活にしろ、全てに高峰の感性が表れている。それは長年、人間を観察してきたことで培われたのだと思う」と斎藤。幼いころに実母を亡くして養母に引き取られ、物心つかないうちに映画界という大人の世界に放り込まれた。自分を頼ってくる親族の生活を支え、さまざまな人間の本質を見てきた。
ろくに通えなかった学校をやめたときの気持ちを、高峰はこう記している。「学校へゆかなくても人生の勉強は出来る。私の周りには、善いもの、悪いもの、美しいもの、醜いもの、なにからなにまで揃っている。そのすべてが、今日から私の教科書だ」(同)
人間に対する洞察力が高峰秀子という人間を育てた。生きる上で大切なことは何かを学び、確固とした価値観を築き上げた。それが演技や文章に通底しているのだろう。(敬称略/加藤義久・共同通信記者)
生誕100年を記念した映画上映や展覧会、書籍刊行が続く。詳しくは「高峰秀子生誕100年プロジェクト」のホームページまで。
かとう・よしひさ 文化部で映画や文芸を担当しました。「浮雲」はどうしようもない男を演じた相手役の森雅之が絶品です。「こんな男、別れろよ」と思わせる駄目男でありながら、色気がダダ漏れ。