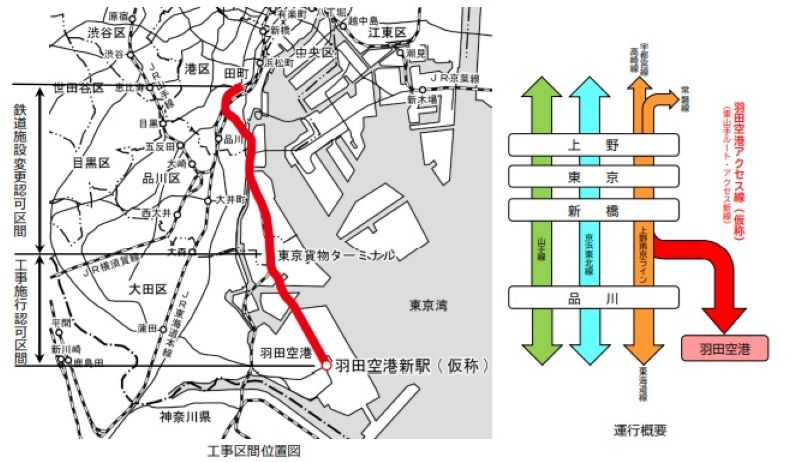油料理と相性抜群 埼玉・秩父の伝統食「つきこんにゃく」 プリプリな食感、歯切れも良く コンニャクイモを杵で7千回、手作業で丹念に製造 製法守り、作り続ける3軒
武甲山の裏に位置する、秩父市浦山地区の集落に今月16日、真っ白な“湯けむり”が立ち上がった。秩父地方の伝統食「つきこんにゃく」の製造が始まった合図だ。午前10時ごろ、浦山毛附耕地の会社員、原嶋広文さん(63)宅を訪れると、蒸したコンニャクイモを大きな臼に入れ、杵(きね)でリズミカルにつく、原嶋さんの姿があった。過疎化が急速に進み、40世帯70人ほどになった現在の浦山地区で、つきこんにゃく作りを継承しているのは、原嶋さん宅含めて3軒のみになった。
浦山地区のつきこんにゃく(別称・石こんにゃく)作りは何百年と続く。コンニャクイモを杵でつくことで、気泡や硬さをあえて残す製法は、こんにゃく本来のプリプリ食感に、シコシコとした歯切れの良さを加える。「味がなじみやすいので、きんぴらなどの油料理と相性抜群」と原嶋さんは語る。
原嶋さん宅では、群馬県産の品種「はるなくろ」と、広島県産の在来種を組み合わせたコンニャクイモを使用している。大釜でイモを2時半ほど蒸し、軟らかくなったら、臼に入れ1時間(約7千回)ほどつく。湯でしっかりともみ込んだ後、凝固剤となる木の灰を使った灰汁(あく)を流して、手作業で丹念に混ぜ込んでいく。
「灰汁は、木の種類によって固まり方が異なるため、木の選定が重要」と原嶋さん。灰汁合わせが終わったこんにゃくは、ビニールを敷いた木製の箱に敷き詰め、1時間ほど放置すると自然に固まり、切り分けができる。
原嶋さんは本業の傍ら、毎年秋から冬にかけて計30臼(1臼約14キロ)ほど、つきこんにゃくを製造・販売している。市場には出さず、毎年10月の浦山地区の「大日堂の縁日」や、12月の「秩父夜祭」の行事関係者、地元住民や都市部に移った元住民らから予約が入るたびに杵を握る。原嶋さんが子どもの頃は、各家庭でつきこんにゃくを作るのは当たり前だった。
「体力と根気がいる作業なので、今ではミキサーを使用する家庭が定番になった。無駄な労力と思われるかも知れないが、製法を守り続ける残りの仲間に刺激を受けながら、毎年心待ちにしてくれている方がいる限り、作り続けていく」と原嶋さんはほほ笑んだ。