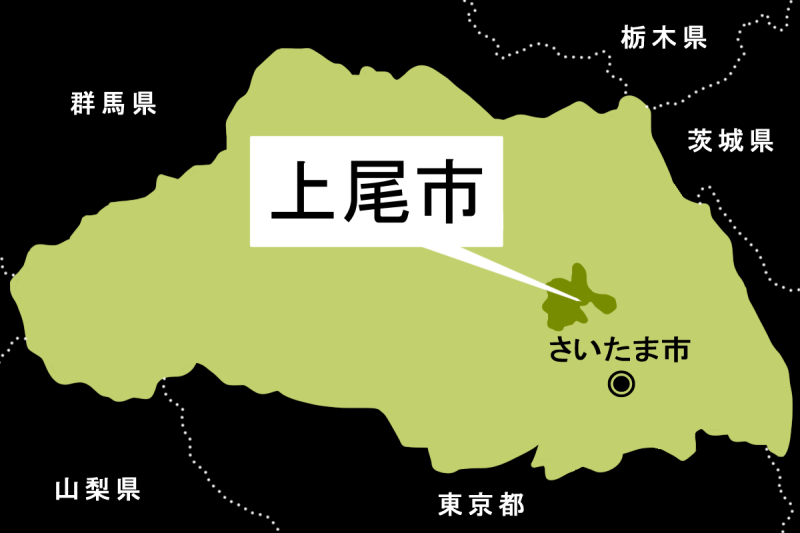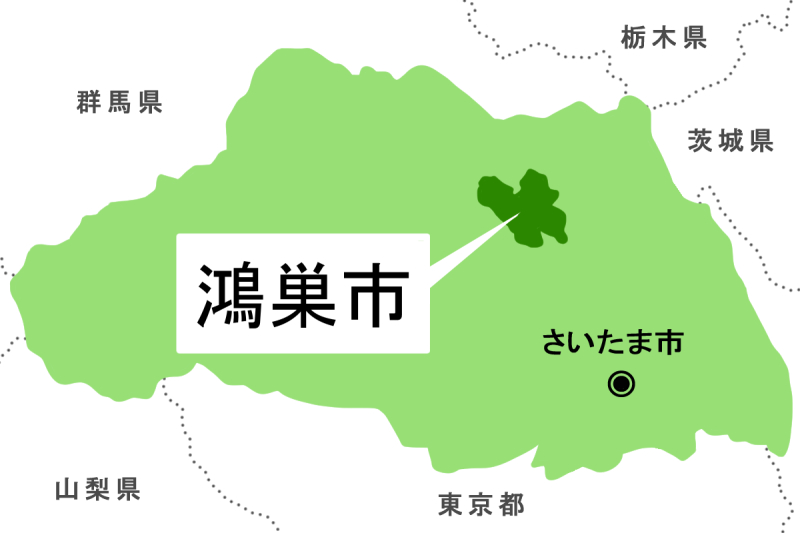八潮の道路陥没…今回の大規模な事故、日本初では 下水道政策、東京大学大学院・特任准教授の話「マンホールの下など腐食しやすい」「目視点検が不可欠」「下水道経営を構造的に見直すべき」
2025/01/30/11:24
東京大学大学院都市工学科(下水道政策)加藤裕之特任准教授の話
下水管の腐食で陥没が生じる現象は昔からあるが、今回のように大規模な事故は日本で初めてではないか。下水で生じた硫化水素は水分に反応して硫酸に変わり、コンクリートの管を腐食させる。特にマンホールの下などは水が滞留し、腐食しやすい。生じた穴から周囲の土が取られて連鎖的に2回目の陥没につながったのではないか。
予防については人工衛星などの新技術もあるが、下に降りて実際に見なければ分からない。コストと人手がかかるが、重要な場所は目視での点検が不可欠だ。国は下水管の老朽化を問題視し、2015年の法改正で点検頻度を5年に一回以上とした。県も優先度を決めて取り組み、事故現場も21年度に点検した結果、修復すべき異常が見つからなかったということだが、緊急輸送道路でもある現場の社会的影響の大きさや、マンホールなどの条件を考慮すると、適切な頻度だったか。
現状では、維持管理には国の補助がなく、点検頻度を増やすには市民の理解を得て使用料を上げるしかない。今回をきっかけに、国は財政的な補助を検討するとともに、小規模な自治体では民間企業の力を活用し広域的に点検を行い、スケールメリットや効率性を高めるなど、下水道経営を構造的に見直すべきだ。