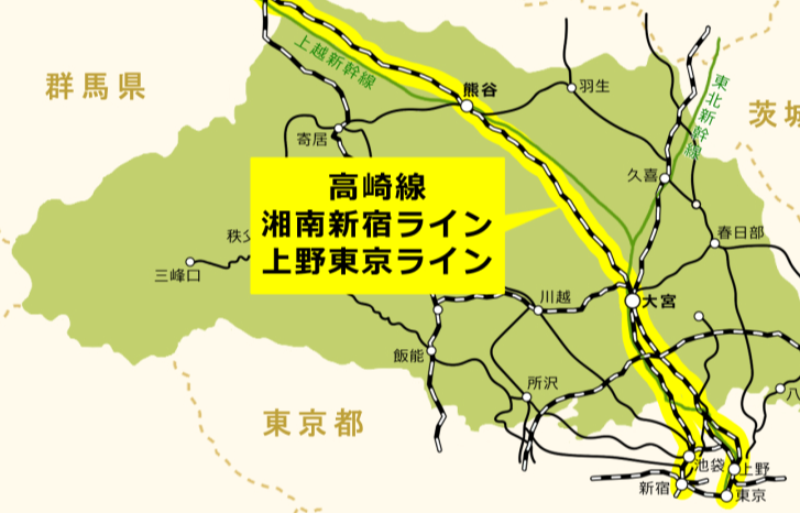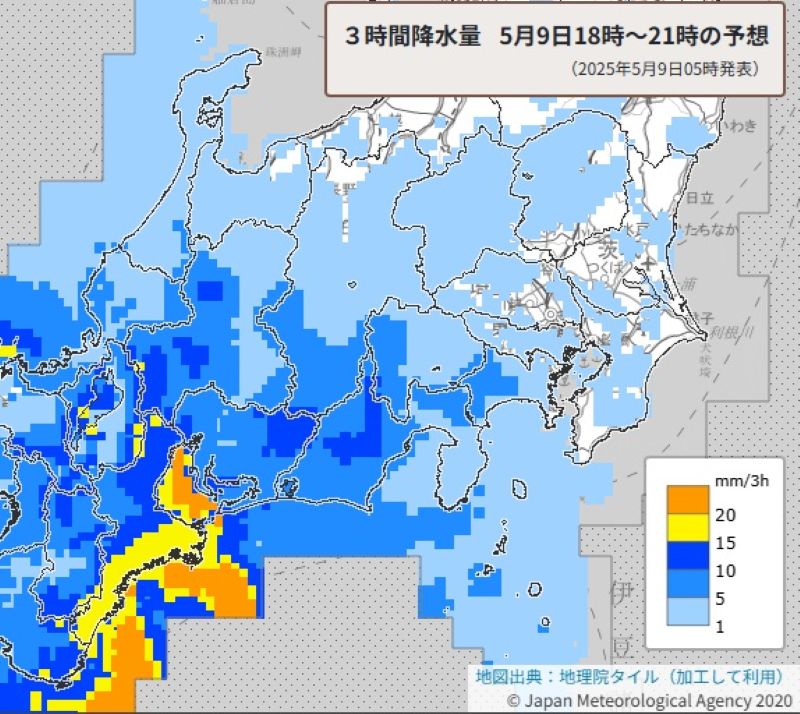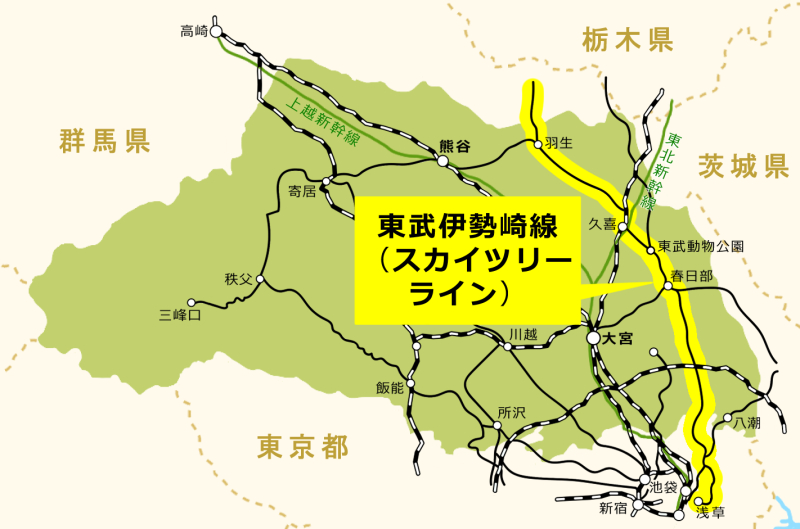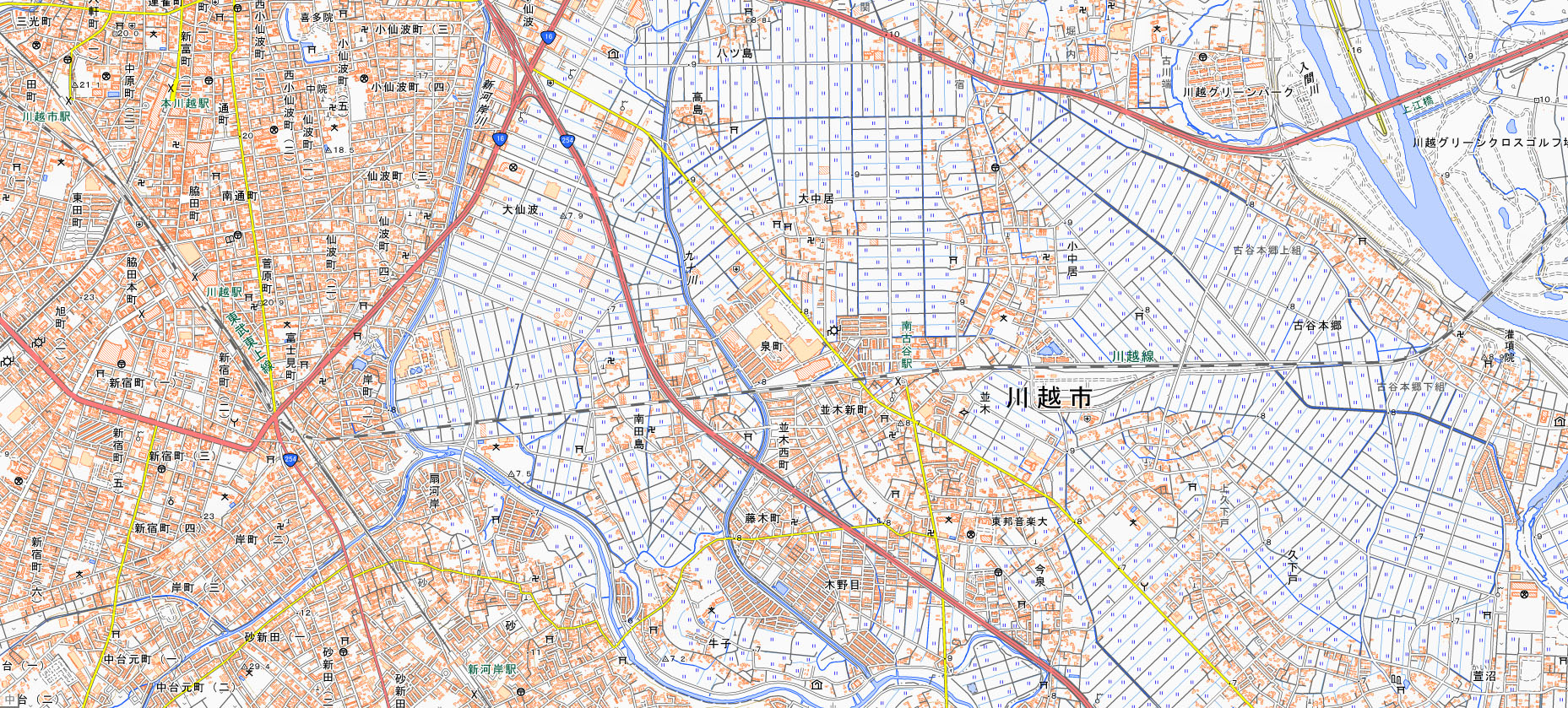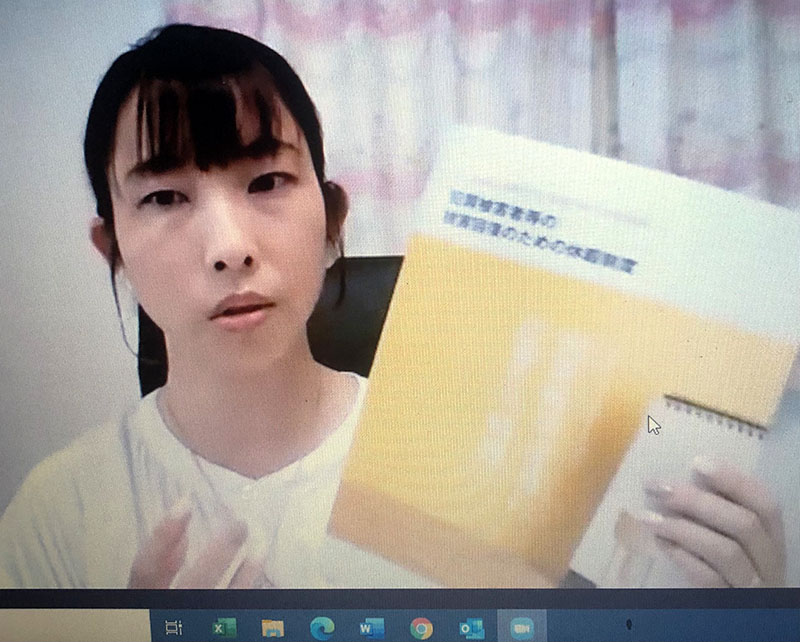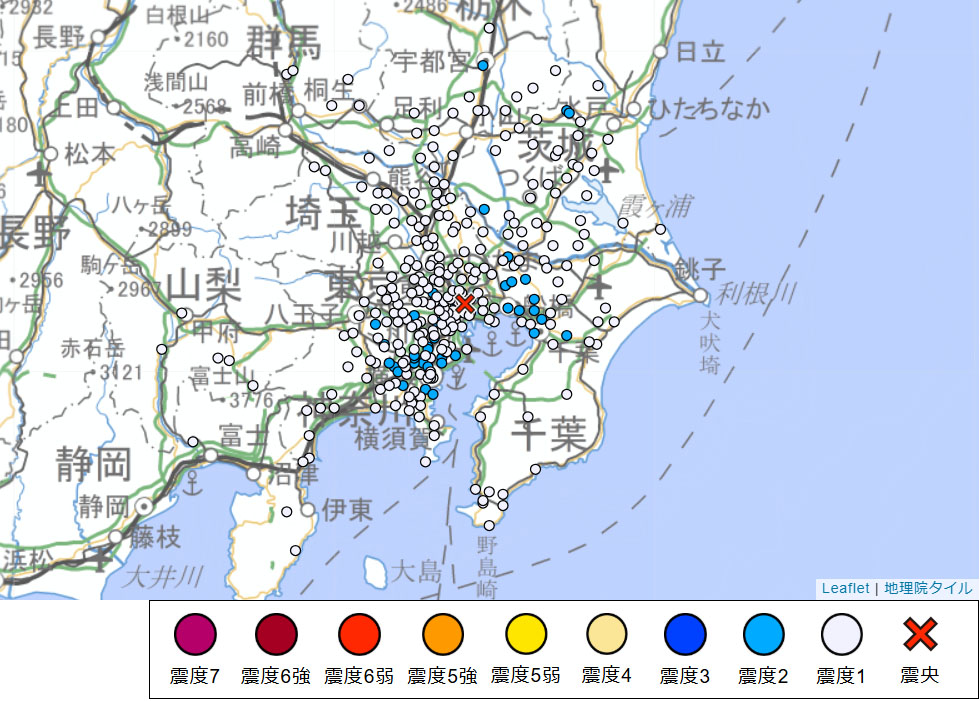埼玉にも魔除け…わざと柱を未完成の状態に 熊谷の諏訪神社、日光東照宮・陽明門の「逆さ柱」と類似の手法で施工 ものつくり大学院生の調査で明らかに 本殿は5月18日に一般公開の予定
熊谷市上新田の諏訪神社本殿(県指定有形文化財)について、日光東照宮陽明門の「逆さ柱」と類似する建築手法で施工されていたことが、ものつくり大学大学院2年生で横山研究室の星辰之介さん(24)の調査で明らかになった。星さんは「あえて未完成の状態にすることで、災いを避ける狙いがあった」と語った。
諏訪神社の本殿は1746(延享3)年に柴田信右衛門豊忠が施主となって創建したもので、大工棟梁(とうりょう)の内田清八郎や彫り物大工棟梁の石原吟八郎らが妻沼聖天山の国宝「歓喜院聖天堂」の工事中断の期間中に手がけた。本殿全体が精巧で緻密な彫刻によって装飾されており、2016年に県指定有形文化財となり、その後は保存修理工事も行われた。
日光東照宮の逆さ柱は「建物は完成と同時に崩壊が始まる」という伝承を逆手にとり、わざと柱を未完成の状態にすることで魔除けの意味がある。日光東照宮の工事に携わった平内大隅政信(へいのうちおおすみまさのぶ)の嫡男、応勝(まさかつ)の次男が林家へ養子に入り、歓喜院聖天堂の大工棟梁の林兵庫正清となる。林兵庫正清の門弟である内田清八郎は歓喜院聖天堂の造営に携わっている。
諏訪神社の本殿は4本の本柱のうち北西柱1本がほかの3本と彫刻の配置が違う。3本は入子菱繋(いりこびしつなぎ)文、紗綾(さや)形文を順に組み合わせているが、北西柱だけは紗綾形文、入子菱繋文の逆の順番だった。逆さ柱を意識したもので、建物の状況からも大工棟梁が意図的に行ったことが判明した。
本殿は十二支の彫刻も備わっていたが、蛇の彫刻だけがなく、主祭神が蛇神であることや、申(さる)が本来配置されるべき場所とは逆側の戌(いぬ)とは対角側にあり、犬猿の中の関係を踏まえて切り離した配置にしていたことも分かった。星さんは「2年間の研究の成果」と話した。
本殿は5月18日に一般公開を予定する。