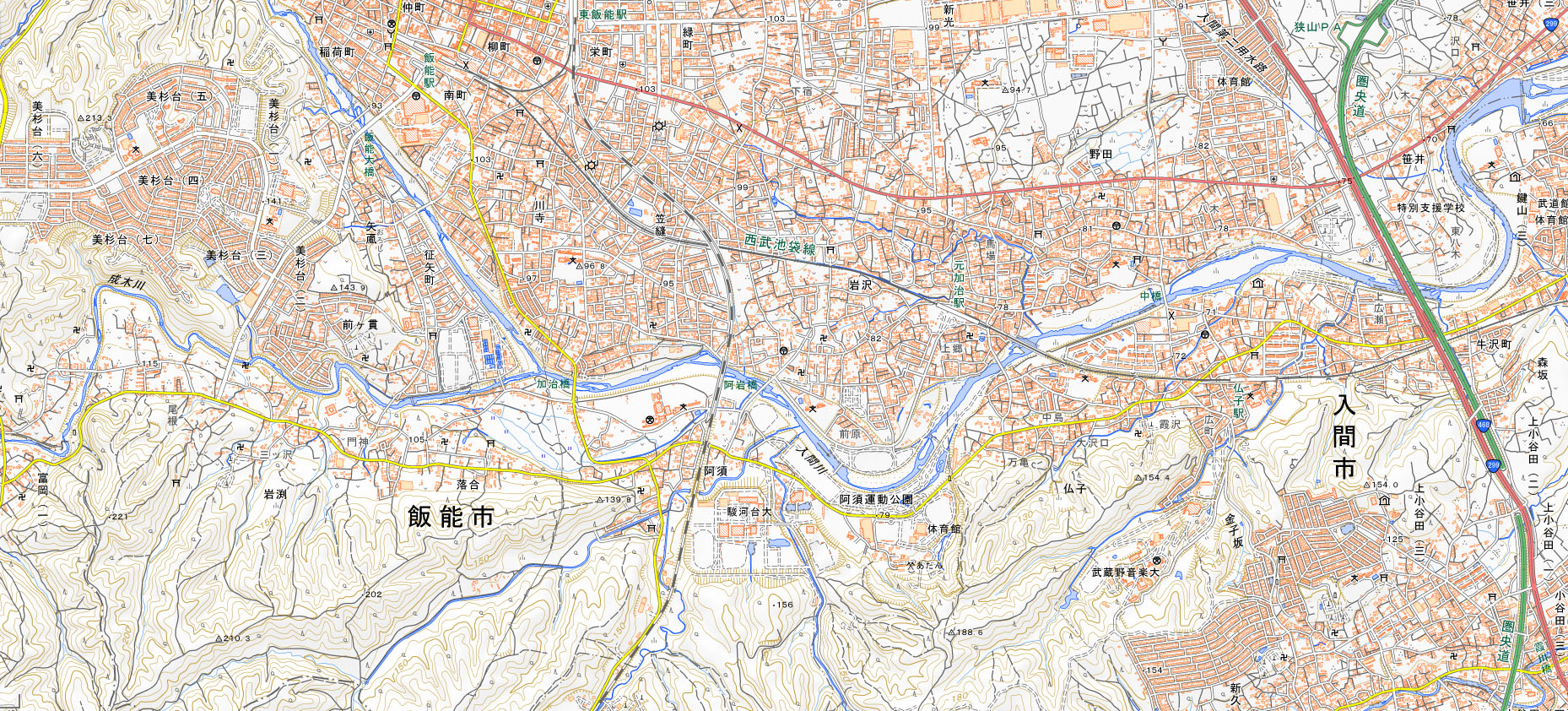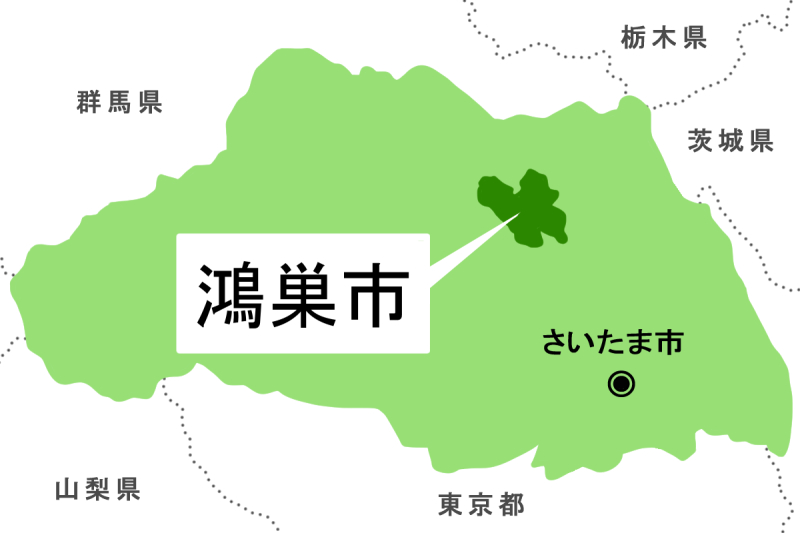熊谷桜が深めた縁 宮城・気仙沼に「花のお嫁入り」 植える会が10周年で記念誌 津波被害受けた被災地に桜を植える活動で交流
2011年3月11日に発生した東日本大震災で、甚大な津波被害に遭った宮城県気仙沼市に桜を植える活動を行ってきた熊谷市の市民団体「『花のお嫁入り』気仙沼に熊谷桜(クマガイザクラ)を植える会」は、昨年春で終了した取り組みをまとめた10周年記念誌「千穐楽(せんしゅうらく)から未来へ」を編集した。冊子には、活動に携わった人々の思いと交流継続への願いが込められている。
記念誌はA4判、カラー24ページで、千部を製作。気仙沼市に300部を届け、700部は熊谷市内の小中学校や図書館と公民館、過去の活動参加者らに配布した。植樹のため現地訪問した時の写真を掲載したほか、両市の関係者約30人が寄稿している。
気仙沼市は平安時代の終わりから鎌倉時代の初めにかけて活躍した熊谷市ゆかりの武将、熊谷直実の孫直宗が約800年前に移り住んで統治した地と伝わっている。同会によると、現在も熊谷姓の市民が5%ほどいるという。
震災前は、両市民の交流はほとんどなかった。震災後、津波で大きな被害を受けた気仙沼市が熊谷氏に縁があるとされる土地だったことから、熊谷市自治会連合会が1600万円の義援金を寄付。翌12年には、熊谷歌舞伎の会と小鹿野歌舞伎保存会が現地で復興支援公演を行った。
支援の取り組みを通じて、津波や塩害によって現地の桜並木が枯れてしまったことを知ると、熊谷桜を育てている熊谷市内の市民団体「桜ファンクラブ」を中心に同会が発足。14年から、「花のお嫁入り」が始まった。
熊谷桜は早咲き八重桜の一種。コロナ下の20年は中止されたものの、同会は参加者を募って気仙沼市をほぼ毎年訪れ、苗木を贈ってきた。24年4月には「嫁入り」が節目の10回目を迎え、計千本に達したことから、区切りをつけることにしたという。活動では延べ428人の市民らが訪問、1024本を届けた。
現地では、熊谷氏ゆかりの神社などに植樹。個人宅には、鉢植えの熊谷桜を届けた。記念誌の編集を担当した同会委員の栗原和江さん(65)は「(贈り手と受け取った側で)個々の交流が生まれ、今では親戚付き合いのようになっている。(熊谷市内の)妻沼で取れたネギをあげたり、向こうからサンマが送られてきたり」とほほ笑む。
同会は記念誌の完成で役目を終えるが、今後は桜ファンクラブが訪問を継続。気仙沼市民の手で熊谷桜を増やしていけるよう、接ぎ木の講習会を行う。同クラブと植える会の両方で会長を務める横田透さん(74)は「気仙沼の方々は被災して大変だったはずなのに、私たちを大歓迎してくれた。逆に元気をいただけたからこそ、10年もの間続いたと思う」と感謝する。
同クラブのメンバーらは、29日から31日までの日程で現地へ足を運び、30日に初の講習会を実施する。オオシマザクラを台木にする熊谷桜の接ぎ木は、難度が高いという。横田さんは「技術移転がきちんとできるまで、3~4年は必要。それまでは、毎年3月ごろに行きたい。記念誌を通して、今までの活動をたくさんの人に知ってもらい、熊谷と気仙沼の関係をさらに広げていければ」と願った。