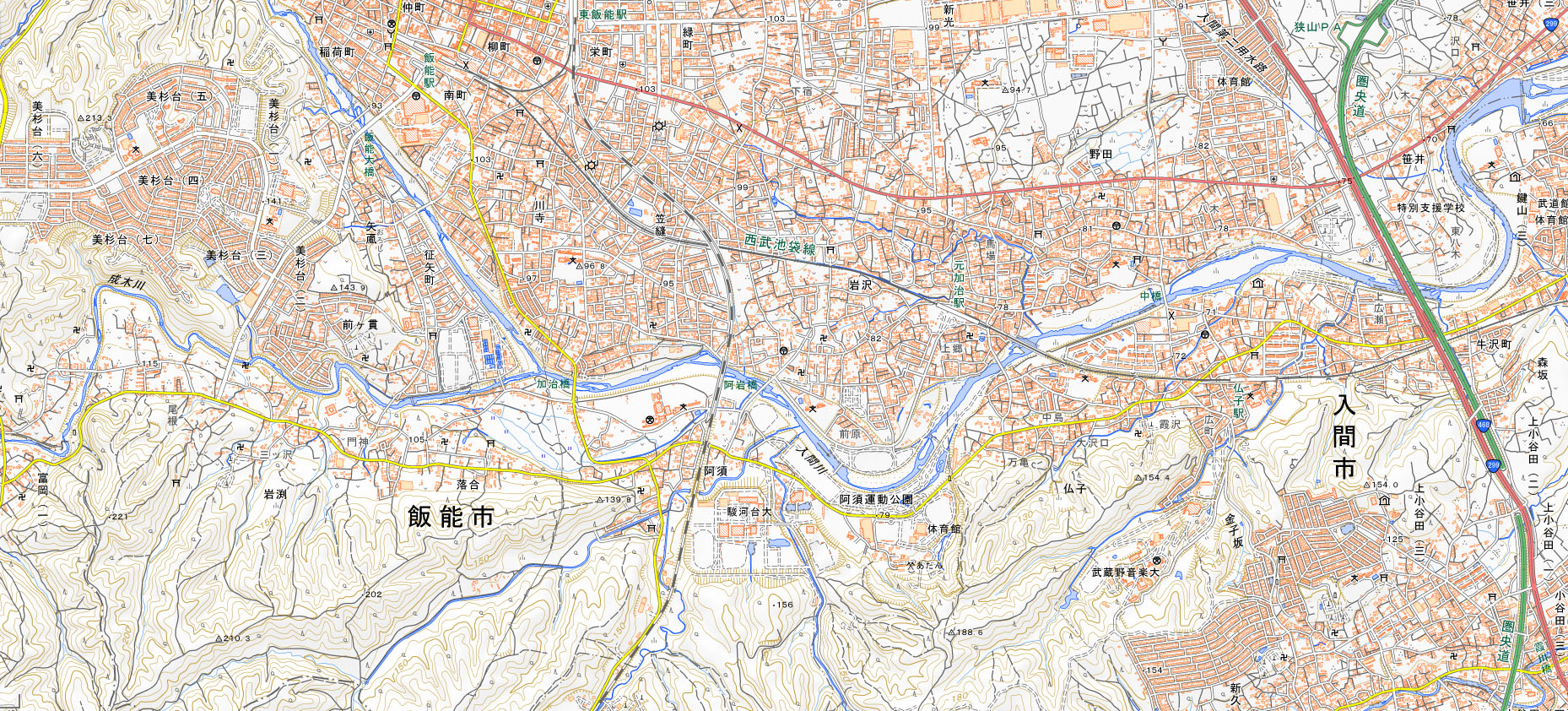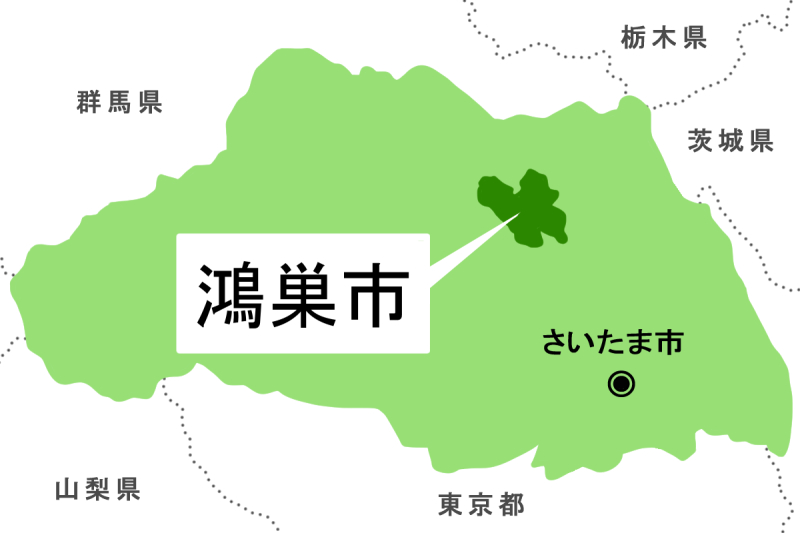独自の技で深み 線状に切った金箔で仏像を装飾する截金師の小塚さん 糊の代わりに漆を使用した技法を考案 ピアスやイヤリングなどの工芸品も制作
2025/03/18/09:09
金箔を4、5枚重ね熱で溶かして厚みをつけ、截金箔(きりかねはく)を作る。竹で創った刃物「竹刃」で、線状に切り、のりと筆を使って仏像に貼り付ける。そんな作業で仏像を装飾する職人を截金師という。ふじみ野市の截金師小塚桃恵さん(38)は仏師の夫と共に工房を営んでいる。
截金は仏教とともに伝来した仏像の装飾手法の一つで、平安から鎌倉時代に多用された。その魅力を「型にはまらない文様を作り、そのものを際立たせる繊細な手法。美術館などで仏像を見ると、金箔が光に反射し、仏像の深みが増すんです」と説く。
小塚さんは同市出身。高校卒業後、京都の専門学校「伝統工芸大学校」に入学。仏像の彩色を学び、卒業後は仏像修復工房で截金を覚えた。この間、夫の智彦さんと結婚。2014年に熊谷市内で工房を立ち上げた。実家に空きスペースができ、20年にふじみ野市に移転した。
子どもの頃から神社や妖怪が好きだったため、「手に職を付けよう」と飛び込んだという。截金は鑑賞用のため、触ると金箔がはがれることから、5年前、糊の代わりに漆を使用した技法「漆截金」を考案。今はこの技法を活用して、ピアスやイヤリングなどの工芸品も制作している。
3年前、狭山市の文化財に指定されている神社の神像の彩色を落札し、昨年、修復した神像を収めている。仏像の彩色の合間に漆截金で制作した工芸品は県展に出品したり、手作りサイトに登録し、販売している。
「仏像は正面から見るものだが、台座や背中などの見えないところも手を抜かずにやっています。次に修復する職人に恥ずかしくない物を残したいから」と仕事と向き合う。職人気質が良い作品を生み出している。