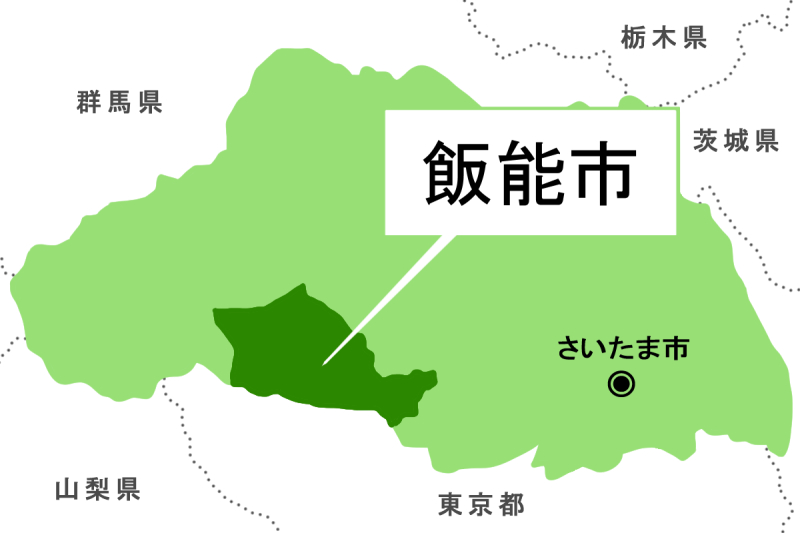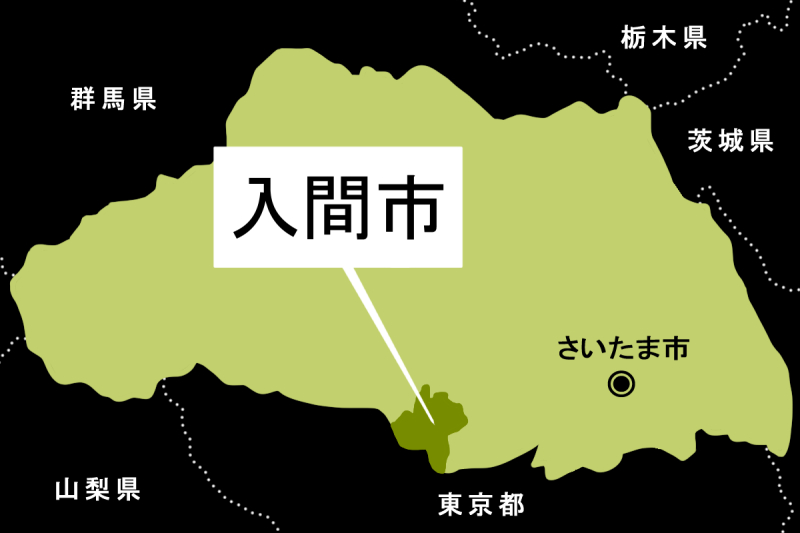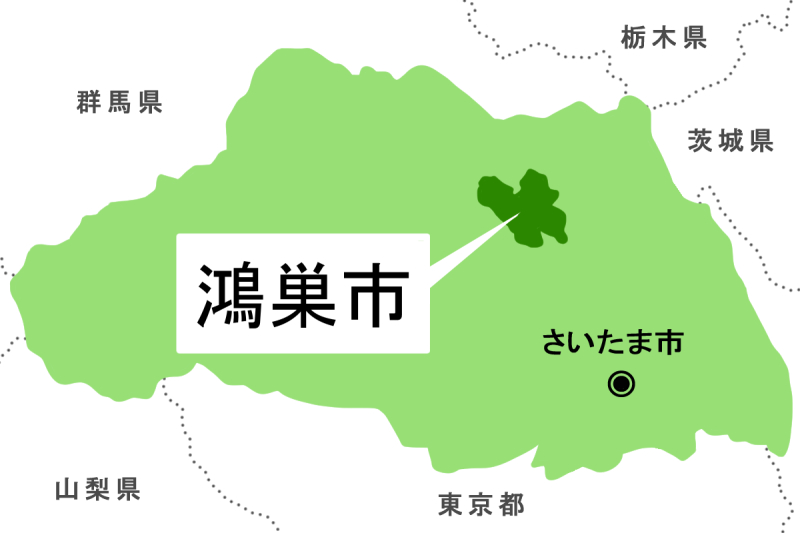【名作文学と音楽(33)】モーツァルトで誘惑を ソレルス『ゆるぎなき心』、ブローフィ『雪の舞踏会』
1763~4年のパリで、ジャン=フィリップ・ラモーとウォルフガング・アマデウス・モーツァルトの軌跡は接近し、しかしすれ違っている。父に連れられたモーツァルトは11月から4月にかけてこの街を訪問し、滞在中の1月27日に8歳の誕生日を迎えた。一方のラモーはモーツァルトがパリを離れた5カ月後の9月12日、ほぼ81年に及ぶ一生を当地で終える。本連載では前回と前々回、ラモーの音楽に縁のある小説『ラモーの甥』(ディドロ)と『やさしい訴え』(小川洋子)を取り上げた。今回はその後を受け、老大家から神童に目を転じてモーツァルトと関わる作品を読んでいくことにする。
まずフランスの現代作家フィリップ・ソレルス(1936~2023)が1987年に発表した長編小説『ゆるぎなき心』(集英社刊・岩崎力訳)に注目したい。内容を大まかに要約するなら、著者自身を思わせる作家Ph.Sを含む男性2人と女性3人が1984年10月8日に秘密結社<ゆるぎなき心>を設立し、メンバーの幸福(快楽と知識)を追求していくというように一応は説明できる。しかしこれでは不十分だ。もう少し具体的に言わなくてはならない。彼らはフリーセックスを楽しみ、文化・芸術の世界に遊ぼうというのである。万華鏡のように変転するストーリーの中から、音楽が現れる場面を抜き出してみよう。
5人はヴェネツィアで出会った。Sがベネデット・マルチェロ音楽院で開かれたコンサートに行くと、すぐ横の席にシグリッド(哲学者)とリヴ(俳優)の女性2人連れが坐っていた。ステージで演奏しているヴァイオリニストのチェチーリアが彼女たちの友人で、共演者のクラリネット吹きマルコはチェチーリアの同棲相手。Sはシグリッドとリヴを誘惑して「三人の完全な結婚」を成り立たせ、音楽家2人も仲間に引き入れた。この日演奏されたモーツァルトのクラリネット五重奏曲は、のちに設立される結社(岩崎訳では<協会>)の賛歌になる。結社を名乗り、7条の規約まで定めたのはほんのお遊びだが、モーツァルトがフリーメイソンの会員だったことも意識されているだろう。
チェチーリアとマルコは、ミサのためヴェネツィアを訪れた教皇ヨハネ=パウロ2世の歓迎会でも、モーツァルトのクラリネット五重奏曲を演奏した。マルコが前口上を受け持ち、曲の書かれた1789年はモーツァルトが幸福の絶頂にあった年だと前置きしたあと、「私たち、何人かの友人と私は、この曲を、いわば彼の全作品の『ゆるぎない核心』をなすものとみなしております」と楽屋落ちの洒落を紛れ込ませると、客席にいたSは「悪くない、マルコ、悪くないよ…」と心の中で喝采を送った。
Sはまた、モーツァルトのクラリネット五重奏曲をBGMにして、リヴとセックスしたり色事師カザノヴァの回想録を読み返したりしている。ソレルスがこの曲に重要な役割を担わせたのはなぜだろうと考えてみる。メンバーの数が5人であることに合わせるつもりがあったかもしれない。それだけなら同じ編成で書かれたブラームスの曲でもよいのだが、結社<ゆるぎなき心>の気分にふさわしいのは明らかにモーツァルトの方だし、ソレルスはカザノヴァやモーツァルトが活躍した18世紀という時代を好んでいる。また、ソレルスは『神秘のモーツァルト』(綜合社刊・堀江敏幸訳)で「五重奏という構成は、孤独な気持ちをさらにつよめるものだ。協奏曲、交響曲、そしてオペラが『外』にあるのに対して、五重奏曲は内にある」とも言っている。<内>は<心>に通じるだろう。
ここで<カザノヴァ>の表記について説明したほうがいかもしれない。彼はヴェネツィア生まれのイタリア人で、本名はジャコモ・カサノヴァだが、『回想録』をフランス語で著した際は、フランス風にジャック・カザノヴァと称していた。同書の岸田国士訳(岩波文庫)と窪田般彌訳(河出文庫)では<カザノヴァ>、大久保昭男訳(教養文庫)では<カサノヴァ>になっている。本書の岩崎訳は<カサノーヴァ>。どれを採ろうか迷ったが、ソレルス自身が<カザノヴァ>と発音しているのをYouTubeで聴いたので、それに合わせた。
元に戻って少し見方を変えてみよう。五重奏にはさまざまな楽器の組み合わせがある中で、なぜクラリネットだったのか。作中に「ギリシアでは、人々を熱狂させる楽器はディオニュソス的なアウロスだ。それはフルートではなくクラリネットである」という言葉があるのも一つの手がかりになるだろう。また、ソレルスはジョイス研究家デイヴィッド・ヘイマンとの対談『ニューヨークの啓示』(岩崎力訳・みすず書房刊)で「ぼくはクラリネット奏者か歌手になりたかった」と述べ、前出の『神秘のモーツァルト』では、クラリネットのことを「自然を歌う魔法の楽器」「苦悩やメランコリーや吐き気に対する偉大な治療薬」と表現している。その口ぶりから、彼がいかにクラリネットを重く見ていたかがうかがわれる。これらの事柄が複合的に作用した結果、モーツァルトのクラリネット五重奏曲が5人を結びつける曲に選ばれたのではないかと私は推測している。
『ゆるぎなき心』からは、モーツァルト以外の音楽も聞こえてくる。Sが発作で苦しんでいる時、ラジオ放送で流れていたのはバッハの『ヨハネ受難曲』。バッハの曲ではそのほか、チェチーリアが無伴奏のパルティータを練習したり、海辺でチェンバロ奏者ラルフと一緒にト長調のソナタ(BWV1019)を演奏したりする。後者に少し付け加えよう。2人の音楽家はチェンバロを小型トラックに積み込んで夏の間、城から城へと回っている。その途中でヴェネツィアに立ち寄った。「旅芸人の暮らしよ」とチェチーリア。
「かすかな風、満ち潮、青い水面、日が沈む… 白い三角形の船が沖からもどってくる… 遠くでは赤や青のウィンドサーフィンの帆がまだ回っている」。気持ちのいい風景には違いない。しかし、そんな場所でチェンバロを弾いていいのか? 「十五分ぐらいなら大丈夫。それ以上だと湿気でやられる危険がある。さあ運ぼう」。発言者の名前は書かれていないが、そう言ったのはラルフだろう。しかし本当に大丈夫だったのか。チェチーリアのヴァイオリンも含めて。
Sはジャズに耳を傾けることもある。リヴと一緒の時だった。「カウント・ベイシーの古いレコード《オン・ザ・サニー・サイド・オヴ・ザ・ストリート》を聞く。コントラバスはレイ・ブラウン…」。おそらく彼らが共演したアルバム『フォー・ザ・セカンド・タイム』(1975年)のことと思われる。名前を挙げられた巨匠2人は、ドラムスのルイ・ベルソンを加えた豪華なトリオでこの曲を演奏している。
小説は寄り道を繰り返しながら進んでいく。Sはさらに多くの女性を誘惑し、カザノヴァについて考え続ける。そして突然、全く劇的でない、拍子抜けとも言える結末に至る。雨に降り込められた初秋のパリへ帰ったSが、妻のローラに「なんという年だろう!」と言うと、ローラが「ほかの年と似たようなものじゃない? ちがう?」と陽気に答えるのだ。どう受け取ったものだろう。ソレルスは読者を宙ぶらりんにさせて楽しんでいるとしか考えられないのだが。
次に紹介するのは、英国人女性作家ブリジッド・ブローフィ(1929~1984)の中篇小説『雪の舞踏会』。1964年の作品で、丸谷才一による翻訳がかつて、河出書房、大和書房の単行本や中公文庫で出ていた。モーツァルトのオペラ『ドン・ジョヴァンニ』を踏まえる洒落たお話だ。以下、引用は大和書房版より。
いつの年か分からないが、雪の降る大晦日に開かれた仮装舞踏会(テーマは18世紀)が作品の舞台。広い邸宅にヴォルテールやマリー・アントワネット、ハミルトン夫人(ネルソン提督の愛人)などに化けた客が集まっている。長いスカートを着け、スペイン風の櫛を髪に挿したアンナもその中にいた。夜中の12時にさしかかると楽団が『蛍の光』を演奏し、人々はキスをし始めた。そのとき、見知らぬ男がアンナに近づいてきて彼女の唇を奪った。男は黒い衣裳をまとい、仮面をしていた。「あなたは?」とアンナが聞く。「ぼくはドン・ジョヴァンニ。あなたは?」アンナが黙っていると、男はまた問いを繰り返した。アンナは「それを申し上げないうちは、あたくし、安全なわけですの」と答える。「安全?」と男。「あたくし、ドンナ・アンナ」
ここでオペラ『ドン・ジョヴァンニ』の冒頭をおさらいしておこう。名うての好色漢であるドン・ジョヴァンニは騎士長の娘ドンナ・アンナに目を付け、彼女の屋敷に忍び込んだ。さてドンナ・アンナの運命やいかに、というところだが、操が破られたかどうかははっきりしない。確かなのは、その場でドン・ジョヴァンニが騎士長と決闘になり、心ならずも殺してしまったことである。
ブローフィは『雪の舞踏会』の巻頭に、自著『劇作家モーツァルト』から引用した次の文を載せている。「オペラがはじまつたとき、ドン・ジョヴァンニはドンナ・アンナをちようど誘惑したばかりだつたのか、それとも誘惑するのに失敗したところだつたのかといふ、あの、この上なく魅惑的なゴシップは、今後の二世紀もきつと論じられるだらう」。ついでに言えば、もうひとつの巻頭言はローマの喜劇作家プラウトゥスの戯曲から引かれた句「苦役と労働のさなか、死はひそやかに我らを襲ふ」。オペラは騎士長の死で始まり、ドン・ジョヴァンニの最期(騎士長の石像に悔悛を迫られるが拒否し、燃え上がる炎の中に姿を消す)で終わるのである。
小説に戻れば、<ドンナ・アンナ>ことアンナは仮面の男の手から逃れ、この家の女主人アン(当夜の姿はアン女王)の寝室に入り込んだ。似た名前の2人は仲の良い友人同士で、アンナの元夫はアンの最初の結婚相手でもあった(アンは4回結婚している)。
これだけで頭が混乱しそうだが、アンナの本名もアンで、彼女たちの双方を知る人々の間でのみ、便宜上、アン、アンナ、と呼び分けられているというおまけがつく。頭に入っただろうか?
2人の会話は気が利いていて面白いので、ひとつ紹介しておきたい。「今夜この邸にマリー・アントアネットが、すくなくとも五人ゐますわ」(アン)。「女は誰でも首を切られてみたいの」「今までお気づきになりませんでした?」(アンナ)。ここにも<死>が顔を出しているのを忘れずにおこう。
ドンナ・アンナ(オペラのである)の貞操問題についての会話もあった。アンは<事は既に起こっていた>という見解を支持する。「もちろん彼女は口説かれただけと言つてゐます。でも、さう言はなければならなかつたのぢやないかしら。つまり十八世紀のことだし、女の名誉つてことがあるし、彼女のあのつまらない婚約者のことも考へなくちやならないでせう。それに、あの娘はかはいさうにスペイン人だつた……」。アンナは興味津々にそれを聞き、こう言う。「序曲の音楽をうんと注意深く聴けば、幕があくすぐ前にどういふ事が起こつてゐるか、わかるでせうね」。モーツァルトが初演の直前、大急ぎで書き上げたという序曲は劇的な和音で始まる。それが何を意味するかはともかくとして。
アンとアンナが食堂へ行くと、この家の主人と親しい音楽学者ドクター・プロムピウスがいた。早速アンが懸案の問題を持ち出し、「あたくしたちが知りたいのは、ドン・ジョヴァンニが本当にドンナ・アンナを誘惑したのかといふことですの」と説明を求める。ドクターは「それはこの上なく魅惑的な問題ですな」「この問題は歴史的に検討しなければいけませんな」「当時の文化状況の光のもとに、二者択一的な状況を検討してみませう」などと言うものの、結論はうやむやにしてごまかした。
そうこうするうち、アンはほかの来客の相手をしに行く。そこへ仮面の男がやってきて、アンナに向かってこう宣言した。「ぼくは、ドンナ・アンナに、当然の権利を要求するために参りました」
彼はアンナに逃げても無駄なのだと言い、その証拠がここにあるとばかりに、1枚の紙切れを渡す。そこにはこう書いてあった。
「彼女がドン・ジョヴァンニの犠牲者の一人であること、ドン・ジョヴァンニがドン・オッターヴィオ(引用者注:ドンナ・アンナの婚約者)に仮装して夜の闇にまぎれ望みを達したこと、ドンナ・アンナが自分の錯覚の怖るべき確実さに気付いた瞬間に幕があがることは、たしかな事実である。(中略)アインシュタイン『モーツァルト』四三九ページ」
アインシュタイン(あの物理学者の従兄弟)は高名なモーツァルト研究者。<たしかな事実>の裏付けは示されていないが、<事は起こった>派に勇気を与える一文である。アンナは「相談なすつた権威者のなかで、あなたを支持してくれる人はたつた一人しか見つからなかつたわけね」と言って紙切れを返した。
2人の会話は続く。「いま、どんなことをお考へになつていらつしゃいます?」(アンナ)。「モーツァルトとセックス」「あなたは?」(仮面の男)。「モーツァルト、セックス、そして死」(アンナ)。
さらにこんなやりとりも。「カザノヴァは『ドン・ジョヴァンニ』の初演を聴いたんですよ。(中略)御存じでしたか?」(仮面の男)「初演は一七八七年十月二十九日でしたね」(アンナ)。アンナはこのオペラに詳しい。それもそのはず、娘時代の名前で本を出したこともあった。
カザノヴァが初演を聴いたというのは、はっきりした事実とまでは言えなくとも、あってもおかしくない逸話として伝わっている。彼は『ドン・ジョヴァンニ』の台本作者ダ・ポンテと旧知の間柄であり、プラハで初演が行われた時、この街に来ていたから、演奏会場に足を運んだ可能性は大いにある。
音楽学者のヨーゼフ・ハインツ・アイブルは『モーツァルト年譜』(音楽之友社・武川寛海訳)で「この上演にはおそらくジャーコモ・カザノヴァも居合わせた」と推定しており、アインシュタインは「初演の際の聴衆のなかには老カザノヴァもいた」(白水社刊『モーツァルト』浅井昌男訳)と断定。ソレルスは前出の『神秘のモーツァルト』でさらに想像を膨らませた。「幕があがる。客席に、亡命中だったボヘミアのデュックスからふらりとやってきた、注意深い観客がひとりいる。彼がモーツァルトに出会い、『カタログのアリア』にインスピレーションを与えたのはまちがいなさそうで、その直後に、彼は自身の生涯の物語を書こうと決意することになる。ハンサムで、背が高くて、しっかり陽に焼けた男。名前はカザノヴァ」
再び小説に戻ろう。終末が近い。アンナはさまざまな問答の末、誘惑に応じることにし、仮面の男のアパートへ行ってベッドを共にする。そのあとで2人はまたパーティーに戻ってきた。男はもう仮面をしていない。しばらく屋敷にいたあと、アンナは男を置き去りにしてタクシーに乗り、一人で家に帰った。そして鍵を開ける。「彼女はなかにはいつた――死を思ひながら」。こちらの幕切れはきれいに整えられている。(共同通信記者・松本泰樹)
まつもと・やすき 1955年信州生まれ。旅行でプラハを訪れたとき、人形劇の『ドン・ジョヴァンニ』を見た。プラハはこのオペラが初演された街であり、人形劇が盛んなことでも知られる。ドン・ジョヴァンニなどの主要な役に加え、指揮者の人形も大活躍する愉快な舞台で、存分に楽しませてくれた。