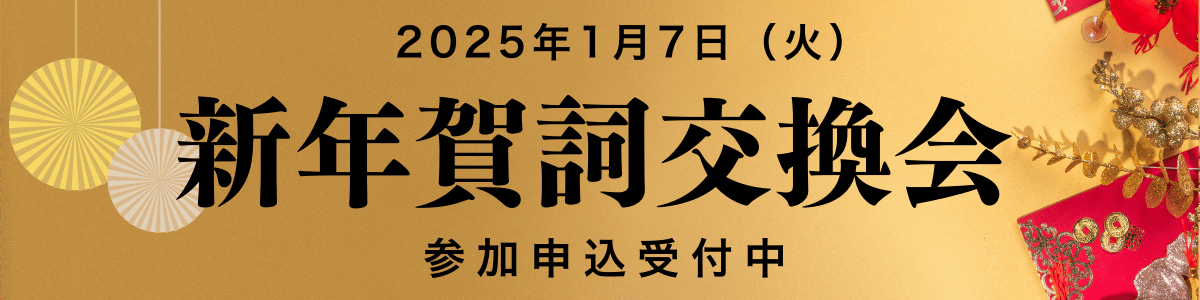埼玉新聞タウン記者制度15周年「記事が人つなげる」 交流会に30人、意見交換
市民の立場で取材活動を行う埼玉新聞タウン記者の交流会が17日、埼玉県さいたま市北区吉野町の埼玉新聞社本社で開かれ、オンラインも含め、関係者ら約30人が参加した。タウン記者制度が誕生して15年。意見交換では「記事が掲載されたことで人と人がつながった」「伝えたいという思いが強い記事が多い。読み応えがある」などの声が聞かれた。
■連載800回を慰労
当日はまず、「道ばただより~春日部の自然」を17年6カ月間にわたりほぼ毎週、800回連載した三好あき子さん(春日部市)に関根正昌社長が感謝状を贈呈した。三好さんは「1、2年のつもりで引き受けたが、まさかこんなに長く書くとは思わなかった。生き物は生き方が多様で不思議。新聞の記事にはうそを書いてはいけない。調べながら自分の勉強になった」と振り返った。
本年度の功績をたたえる年間MVPは、「さいたま国際芸術祭2023」の特集紙面を中学生らとともに担当した8人に贈られた。代表してあいさつに立った斉藤昌代さん(川越市)は「中学生と一緒にアートの講座を受け、取材できたのは貴重な体験だった。作家さんからじかに話を聞き、中学生が書いた記事を手直しすることで自分自身もためになった」と話した。
■新聞に載る喜び
タウン記者のメンバーは、各地域でさまざまな活動をしている人が多い。交流会では、それぞれの自己紹介と近況を報告し合った。
100歳まで働けるもの作り工房「BABAlab(ばばらぼ)」(さいたま市南区)のスタッフでもある横地真子さん(同)は、自身も執筆している「ばあちゃん新聞」の取り組みを紹介。「75歳以上の人が働く福岡の会社が出している。新聞に載りたいと思う人はまだたくさんいると感じている」と話した。
報告では、埼玉新聞の紙面について「ここがいい、ここが課題」をテーマに率直に語ってもらった。阿部健二郎さん(さいたま市南区)は「食事の後に飲みながら端から端まで読んでいても飽きない。休刊日には前の日の新聞を読み直すが、いつも新しい発見がある。一般家庭で取っている人が少ないのが残念」。原口和子さん(上尾市)は「記事が出た時、取材した人がすごく喜んでくれる。それぞれの人生に影響があったと思えてうれしい」と、声を弾ませた。
■楽しい地元ニュース
「大きなニュースはテレビやネットで見られる。地元の小さなニュースを読むのが楽しい」(斉藤さん)といった意見のほか、松崎ちあきさん(同市見沼区)は「断捨離をしていて昔の記事に見入ってしまった。ネットがつながらなくなっても紙は残る。ネットだけになるのは危険」。橋本大樹さん(川越市)は「自己満足的にやっていた感があったが、記事を通して人と人がつながり、自分自身の意識が変わった」。オンラインで参加した一瀬要さん(同)は「新聞を開かせる目的となるような記事があるといいと思う。他県にもタウン記者がいるのであれば、つながれたら」と、指摘した。
一方、デスク側からは「生活者の視点で、われわれが気付かされることも多い。皆さんの伝えたいという思いが心を揺さぶる」などのメッセージがそれぞれ寄せられた。
この日は、早稲田大学人間科学学術院教授の武田尚子さんも出席。「地域でフィールドワークを行う学生たちの学びの応用として、記事を書かせたい。学生タウン記者として参加できれば」と、新年度からゼミのカリキュラムに記者講座を組み込むことにしている。
【タウン記者】読者により近い立場から市民目線で取材し、記事を書く埼玉新聞独自の記者。1980~90年代にあった「ミニコミ広場」の通信員制度のノウハウを生かし、2009年に制度化。NPO法人埼玉情報センターと協力して開催している市民記者養成講座の修了者やライター経験者などから募り、掲載した記事行数、写真枚数に応じて報酬を支払う。現在、55人が登録。