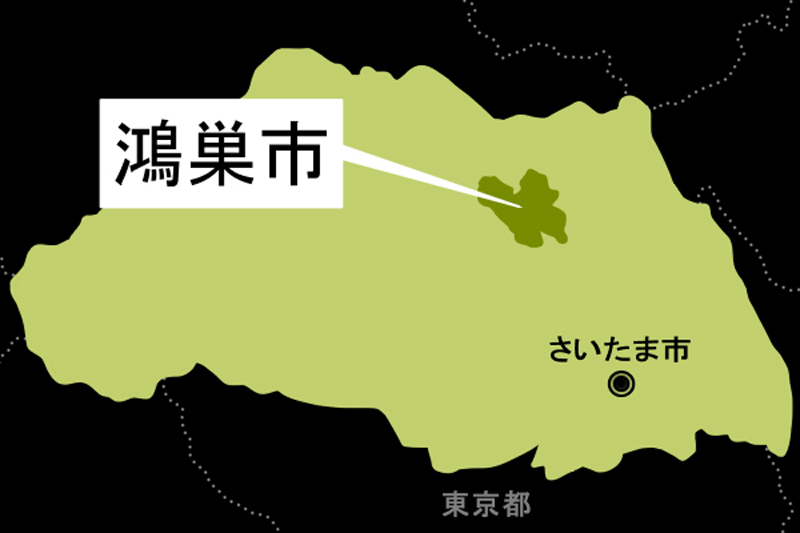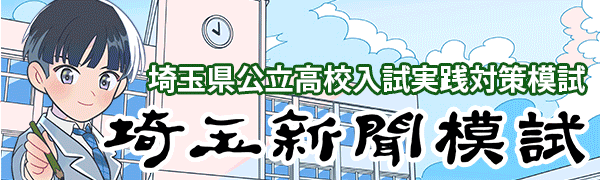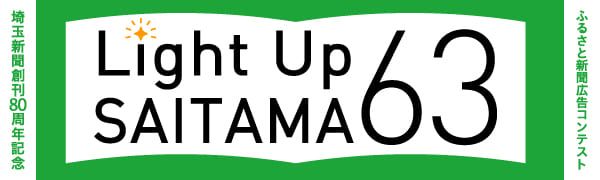人力車の事務所や竿職人らが新たに入居 埼玉・川越の弁天長屋、息を吹き返す 9日から市内彫刻家の石彫展
老朽化に伴い改修工事が行われていた、埼玉県川越市喜多町の四軒長屋に新たな入居者が決まった。職人や創作家が顔をそろえ、ものづくりの交流拠点としての活動が本格化する。長屋の目指す構想を感じてもらおうと、9日から市内の彫刻家・田中毅さんの作品を集めた石彫展が開催される。
弁天横丁と親しまれ、かつては置屋が立ち、芸者横丁とも呼ばれた細い路地にある。「喜多町弁天長屋」と命名され、NPO法人川越蔵の会が再生事業に取り組んでいた。木造2階建ての9区画で入居者を募集し、このほど5区画で入居が決まった。
江戸和竿(ざお)職人の小春友樹さん、ガラスや壁面にロゴなどを描く作家福島英人さん、川越人力車いつき屋(事務所)、ギャラリーなんとうり分室のほか、1階で「トモリ食堂」を開く田代友里さんが入居する。長屋の一角で既に入居していた革の靴・かばん修理を手掛ける「坂庭」の篠田俊樹さんも継続して活動する。
6~10畳の各区画は主に作業場として使われ、作品の展示にも活用される。川越蔵の会副会長の白土真二さんは「理想的な職人たちが入居してくれた。ものづくり、アートの拠点となるよう喜多町弁天長屋を盛り立ててほしい」と期待している。
江戸和竿「小春」を構えた小春さんは川越市出身。女性向けのアパレルメーカーで営業の仕事をしていたが、市内の釣り場で知り合った江戸和竿師との出会いが転機となった。「ものづくりに興味があった。職人は自分に適した仕事」と和竿の道に進んだ。
江戸和竿は江戸時代から続く伝統工芸で、竹を使い、漆を塗り、強度と美しさを兼ね備えた継ぎ竿。小春さんは「長屋に入居するほかの職人から刺激を受けている。弁天横丁が、どんなアーティスティックな路地になっていくのか楽しみ」と話している。
田中さんの石彫展は9~19日正午から午後6時まで長屋1階で開催。「トモリ食堂」は月、火曜日定休だが、1階展示スペースは8日まで閉鎖となる。長屋の残り4区画は引き続き入居者を募集中。問い合わせは、川越蔵の会ホームページから。