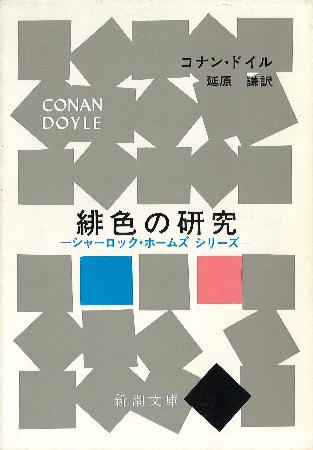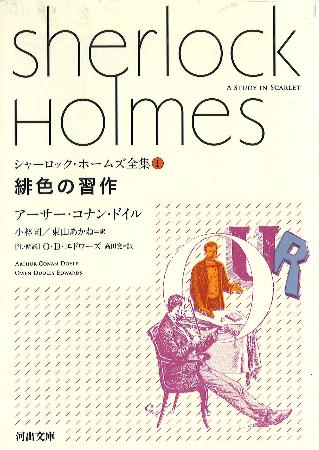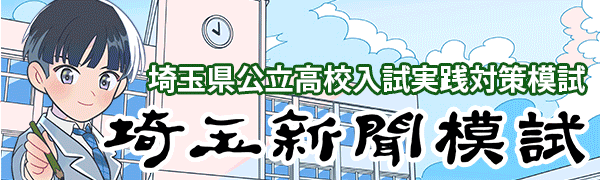【名作文学と音楽(26)】『蝶々』の謎と名探偵の迷言 向田邦子『あ・うん』、コナン・ドイル『緋色の研究』
今月のコラムは、向田邦子(1929~1981)の長篇小説『あ・うん』(1981年、文藝春秋刊)から書き始めることにする。改めて言うまでもないが、向田はテレビドラマの脚本家として名を挙げたのち、エッセイ、小説に進出した。前回取り上げた『一九三四年冬――乱歩』の作者・久世光彦もテレビ界出身で、一緒に仕事をした間柄である。
<あ・うん>は阿吽。1対の仁王像や狛犬で口を開けた方が<阿>、閉じた方が<吽>の相を表す。阿吽の呼吸と言えば、互いの息がよく合っていることの喩えだ。
<狛犬>と題する第1章で、陸軍時代から20年余りの付き合いになる門倉修造と水田仙吉が紹介される。どちらが<阿>でどちらが<吽>だろう。門倉に「あ」の音があり、仙吉には「ん」が含まれるから、何となく想像はつくのだが。
門倉はアルマイトの流行に乗った金属会社の社長で「羽左衛門をもっとバタ臭くしたような美男」。一方、水田(作中での呼び名に従い、以降は仙吉と書く)は中堅製薬会社のサラリーマンで風采が上がらない。何くれと世話を焼くのは門倉の方である。小説の冒頭では、地方から本社へ戻ってくる仙吉のために借家を見つけ、植木や垣根を整え、家財道具をそろええて絹布の布団まで用意した。仙吉一家が到着した時には、風呂が沸き、米櫃も一杯になっている。まさに至れり尽くせりだ。出迎えた門倉と仙吉の会話に<海軍予備会議>という言葉が出てくるので、1934年のことと考えられる。偶然にも、久世の小説で江戸川乱歩が張ホテルに隠れたのと同じ年である。
第2章<蝶々>は「仙吉がヴァイオリンを習いはじめて三カ月になる」と書き出される。例によって門倉のお膳立てである。楽器も先生も手配済みだ。「おれ、習うことにしたから、水田、お前もつきあえよ」。「稽古日は毎週土曜の午後、場所は、ここを貸してくれ、本式でいきたいから先生も白系露人の女史を頼んできた」。厭と言えるはずがない。随分強引なやり方だが、それには理由があった。門倉は、少し前に流産していた仙吉の妻・たみを笑わせたかったのだ。門倉とたみの間には、プラトニック・ラヴ的な感情が流れている。
門倉の狙いは見事当たり、たみだけでなく、娘のさと子も土曜日を楽しみに待つようになった。「二人の男がヴァイオリンを持って女史の前に立ち、音を出しはじめると、母と娘は台所で折り重なるようにして笑いをこらえた」
初心者の弾くヴァイオリンは、昔から<ノコギリの目立て>と悪口を言われ、端で聞く者にとってこれほど耳障りなものはない。それを大の大人が二人がかりでやった日にはどんな音がしたことか。しかし一方で、それはおかしくてたまらない光景ともなる。向田のコメディー・センスが光る場面である。
門倉と仙吉はやがて『蝶々』が弾けるようになった。ヴァイオリンの入門者はこの曲を練習することが多い。技術的に易しく、聞き慣れたメロディーだからだろう。スズキ・メソードの<鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集>も、兎束龍夫・篠崎弘嗣・鷲見三郎編の<新しいヴァイオリン教本>も、第1巻の初めの方にこの曲を載せている。戦前にロシア出身の先生が選ぶ曲だったかどうかは分からないが、習い始めの2人が弾くのにふさわしいことは確かだ。
『蝶々』は明治期の小学唱歌である。原曲は長い間、スペイン民謡とされてきた。岩波文庫の『日本唱歌集』(堀内敬三・井上武士編)、講談社文庫の『日本の唱歌』(金田一春彦・安西愛子編)、岩波新書の『日本の子どもの歌』(園部三郎・山住正己著)もそのように書いている。しかし近年この説に疑念が生じ、ドイツ民謡の『幼いハンス』(ほかの題・詞もあるようだ)が元祖とみなされるようになった。『幼いハンス』はアメリカへ渡ってボート漕ぎの歌Lightly Rowになり、さらにそれが日本に持ち込まれた際、また別の詞が当てはめられた。よく似た詞の<わらべうた>が元からあったという。
『日本の唱歌』に書かれていることだが、作曲家の團伊玖磨がこの曲の一節「菜の葉に飽いたら、桜にとまれ」を取り上げて、「菜の花にばかりにとまる紋白蝶をからかって、たまの浮気を勧めた歌だったか」と茶化したとか。実はこの冗談、『あ・うん』の物語に当てはまる。
門倉は妻のほかに、カフェ<バタビア>の禮子という愛人がいた。彼女が妊娠したことでいろいろ騒動が起き、今度は仙吉がその後始末に追われる。禮子の住むアパートを探してやったり、禮子以外の女性たちへ手切れ金を渡して回ったり。門倉は子供が生まれて落ち着くかと思いきや、さっさと三号さんをつくる。その女性はなんと、仙吉が柄にもなく入れあげた神楽坂の売れっ子芸者、まり奴だった。道楽者の門倉ばかりか仙吉までも、蝶々のごとく花から花へ「遊べよとまれ」なのである。そう考えると、向田が2人に『蝶々』を弾かせたのには、難易度や親しみやすさばかりではない、深い意味があったように思われる。
話は変わるが、世界一有名な素人ヴァイオリニストは誰だろう。架空の人物を含めていいのなら、私はまずシャーロック・ホームズに指を折る。コナン・ドイル(1859~1930)のホームズ物語第1作『緋色の研究』(1887年)の最初の方に、ワトスン医師がホームズのヴァイオリン演奏について述べるところがある。新潮文庫の延原謙訳で引用してみよう。「彼がさまざまの曲を、ことに難曲をも奏しうるのは、かつて私の求めに応じて、メンデルスゾーンの歌曲そのほか愛好の曲を奏してくれたのでもわかる。けれども彼ひとりのときは、めったに楽譜をひろげたり、またはこれという曲らしいものを奏することはないのである」「晩になると、よく肘掛椅子にもたれこんで、眼をつぶって膝の上に横たおしにしたままのヴァイオリンを、そぞろに掻きならすことがあった」。
ワトスンの言葉はまだ続くが、ここでじっくり考えてみたいのは、ホームズがどういう体勢でヴァイオリンを弾いたかである。延原訳に従えば、ヴァイオリンは膝の上で横に倒されていたことになる(thrown across his knee)。上体は後ろにもたれている。この状態で弓を使ってまともに弾くのは不可能と思われる。では、ウクレレのように指で弦をはじいたとは考えられないか。<掻きならす>を原書で見たらscrape (こする)だっただから、どうやら爪弾きではなさそうである。
他の訳者も首をひねりながら筆を進めたのではないか。光文社文庫の日暮雅通訳、角川文庫の駒月雅子訳、創元推理文庫の阿部知二訳、河出文庫の小林司/東山あかね訳(訳題は『緋色の習作』)はいずれも、ヴァイオリンが<膝>あるいは<膝の上>に置かれていたとの表現にとどめている。この書き方だとヴァイオリンを立てていたとも、寝かせていたとも取れるので、ホームズがヴァイオリンをチェロのように抱えて弾いたと想像することもできないではない。しかし、椅子の背に寄りかかっていたのなら、それも難しかろう。
くだくだしい書き方になった。要は、ワトスンが言うような不自然な姿勢でヴァイオリンを自在に弾くのは、いかに型破り好きのホームズでも無理ということである。以下はシャーロキアンでも何でもない私のたわごとだと思って聞いてもらえばよいのだが、そもそもワトスンは、ここで正確な描写をするつもりはなく、皮肉を込めたユーモアでホームズをからかっているのではないか。
さらに言えば、難曲の例にメンデルスゾーンの歌曲を持ってきたのも、ジョークのような気がする。具体的な曲名は書かれていないけれど、メロディーをなぞるだけなら、さして難しくはないだろう。メンデルスゾーンの歌曲では『歌の翼に』がよく知られ、名人ヴァイオリン奏者ハイフェッツによる技巧的な編曲もあるが、『緋色の研究』が書かれたころ、ハイフェッツはまだ生まれていなかった。
ホームズは時々、ワトスンを相手に音楽談義をして聞かせる。その中には、読者を惑わせるような部分が交じっているのもしばしばだ。「今日ヌルマン・ネルーダ夫人を聴きにハレの演奏会へゆきたいと思っているから~」「じゃはやく中食をすませて、ヌルマン・ネルーダを聞きにゆこうよ。夫人はアタックといい、バウイングといい、すばらしいものだ。得意のショパンの小曲など、まったくなんともいわれないじゃないか! ツラララ、リラリラレー」(延原訳)。
ここで話題になっているのは、当時有名だった女性ヴァイオリニスト、ウィルマ・ノーマン=ネルーダである。ハレは彼女の未来の夫でピアニスト、指揮者のチャールズ・ハレ(2人が結婚したのは『緋色の研究』発表の翌年)。<ハレの音楽会>はおそらく彼の指揮する管弦楽演奏会のことで、ネルーダが協奏曲のソリストとして登場するのだろうと思う。
アタックは弓を力強く弦に当てること。<バウイング>はボウイング(運弓法)。ショパンのピアノ曲にはヴァイオリン用の編曲があるから、ネルーダが独奏会のアンコールで弾いたとしてもおかしくない。しかし、ヴァイオリニストの本領をショパンの曲で語るのはどこか変ではないか。ホームズは最後に「ツラララ、リラリラレー」と口ずさんでワトスンを煙に巻いているようだが、見方を変えれば、ワトスンがホームズを戯画化して伝えているとも感じられる。
短篇『赤髪組合』には、サラサーテについて触れた箇所があり、そこでもホームズ独特の屈折した好みが描かれている。サラサーテは『チゴイネルワイゼン』をはじめ、派手でスペイン情緒にあふれた自作曲を得意にした演奏家だが、ホームズはサラサーテが今回、ドイツ音楽を多く弾くから聴きに行くというのだ。ホームズはワトスンに、自分はイタリアやフランスの音楽よりも、内省的なドイツ音楽が好きだと話している。サラサーテの弾くベートーヴェンやブラームスは私も聴いてみたいが、あまり内省的ではないような気がする。
ホームズの愛器はストラディヴァリウスだと短篇『ボール箱』に書かれている。彼がワトソンに語ったところによると、500ギニーは下らない楽器だが、ユダヤ人の店から55シリングで買ったという。1ギニーは21シリングだから、ざっと200分の1の値段だったことになる。まあ、ほら話だろう。そのあとホームズは、パガニーニの逸話を次から次へと1時間にわたって話し続けた。イタリア生まれの鬼才パガニーニも、サラサーテ同様、超絶技巧を売り物にした作曲家・演奏家である。悪魔に魂を売ったという噂も立てられた。内省的なドイツ音楽を好むというホームズも、伝説的ヴィルトゥオーゾの噂話は嫌いでなかった。(松本泰樹・共同通信記者)
まつもと・やすき 1955年信州生まれ。『蝶々』のメロディーは、ドイツの『小さなハンス』やアメリカのLightly Rowと最後が少し違う。ハ長調で示すと、『蝶々』は<ドミソソ・ミミミー>で、あとの二つは<ドミソソ・ドー>。主音の<ド>ではなく3度の<ミ>で終わると柔らかな感じがするし、かすかな浮遊感もあって、軽やかな蝶のイメージに合うように思う。