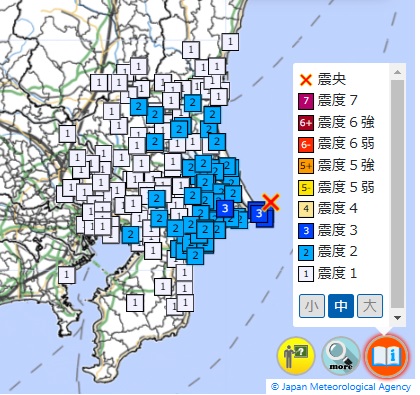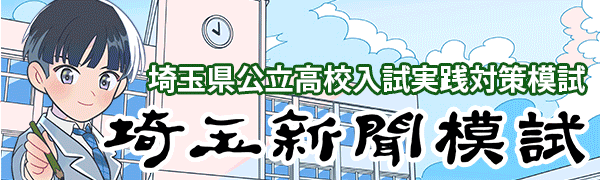【3分間の聴・読・観!(27)】ボカロを聴いて感じる「声と個性」とは? 「自分だけ」なんて幻想かもしれない
ドラえもんの声優大山のぶ代さんが亡くなった。訃報を読んで思い出すのは、「ブーフーウー」のブーや「ハリスの旋風」の主人公石田国松、「のらくろ」を演じた時の声だ。私はむしろドラえもん以前の「大山のぶ代」の声に親しみを感じていた。
声にはその人の個性が表れる。声優が役を演じ分けているとしても、声と個性は1対1のものであり、歌手も同じだと思うのだが…。
「ユリイカ」10月号の特集「いよわ」を読みながら、ボーカロイドはどうだろうと考えた。活躍するボカロP「いよわ」のインタビューや対談、曲の解説などを収めた特集は、多角的にいよわを浮かび上がらせる。
「1000年生きてる」「きゅうくらりん」「黄金数」「一千光年」など、いよわの楽曲では高音、高速でボカロや合成音声が歌っている。人間にはとても無理と思える音域と速さによる歌詞の連射が特徴の一つだ。「ベテラン」と言っていい初音ミクをはじめ、ボカロたち一人一人の声にアーティストとしてのいよわの個性が投影されている。ボカロPが声を自在に操る世界では、声と個性は1対1の関係とは言えないようだ。
特集の評論でも「ボカロや合成音声は、これまで歌いたくても歌えなかった誰もが『歌う』ことを可能にした。これは『声の民主化』という革命なのだ」(ヲノサトル「合成音声と『声の民主化』」)。「『初音ミク』の登場は、人間にとってあまりにも自明だった『声―主体―肉体』の関係性に、(中略)とつぜん亀裂を走らせた」(佐近田展康「声という迷宮」)など、声と音楽の地殻変動が起きていることを物語る。
ミュージックビデオも自作するいよわがインタビューで語った言葉は、制作の奥を垣間見るようで興味深い。「かなり合成音声ごとの個性を意識して、一番適したものは何だろうと考えるところから始めていくことが多いです」「合成音声がいなくなってしまうと自分という存在は大きく揺らいでしまう」
ボカロも合成音声も現代の手段だ。どこか懐かしさを感じさせるピアノや、ずしっとくるバスドラムの音なども効果的に使ういよわの曲は、はるか昔から人が音楽とともにある理由に触れている気がする。
人間と声の関係を更新するボカロシーンを通して人間そのものの理解も進むのか。それを世の中が見定めるのはまだ先になるだろう。注視したい。
「声とは何か」と考えさせられたのは、今夏の芥川賞受賞作の朝比奈秋「サンショウウオの四十九日」でも同じだった。作品の語り手は、29歳の結合双生児の姉と妹だ。体が半分ずつ結合して1人の姿で生きる瞬と杏の2人は、身体の感覚や内臓を共有している。だが別々の思考と感情を持っていて、しかもお互いにその内容が分かる。それぞれが違う声を出して話し、作中の語りでは瞬が「わたし」、杏が「私」と書き分けられる。
心の中の声も共有する瞬と杏は、いわば一つの体で主体と声が2対2の設定だが、2人の生い立ちや家族との会話、伯父の四十九日などが淡々と書き進められ、次第に頭になじんでいく。
交差する瞬と杏の内面を、自己とは、死とは、意識とはという問いが覆っていく。「自分だけの体、自分だけの思考、自分だけの記憶、自分だけの感情、なんてものは実のところ誰にも存在しない。いろんなものを共有しあっていて、独占できるものなどひとつもない。他の人たちと違うのは、私と瞬はあまりに直接的、という点だけだった」。杏の叫びに揺さぶられた。
声と個性、声と主体の1対1の関係はそもそも幻想なのか。心の中で誰にも言わない、言えない思いを抱えているこの私とは何か。「大山のぶ代」から「いよわ」、そして「瞬と杏」。思考がぐるりと回る。(杉本新・共同通信記者)
すぎもと・あらた 文化部を経て編集委員室所属。
【今回の作品リスト】
▽「ユリイカ10月号 特集いよわ」、いよわの楽曲
▽朝比奈秋「サンショウウオの四十九日」