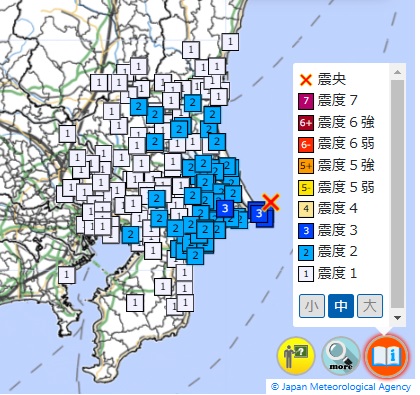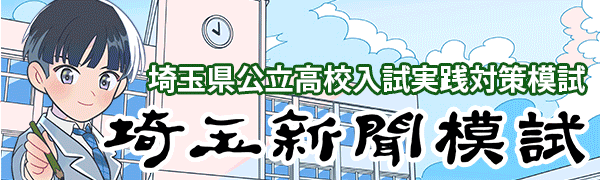室井滋インタビュー「おばさんがズバッとパンチを効かせた」 エッセー「ゆうべのヒミツ」刊行 ※動画連動記事
俳優でエッセイストとしても活躍する室井滋が、5年ぶりのエッセー集「ゆうべのヒミツ」(小学館刊)を出版した。新刊は「若い人が言えないことは、おばさんがズバッと言いましょう」とパンチを効かせたという。執筆に込めた思いと、自身にとって「一生もの」の言葉や共演者との出会いを語ってもらった。
【目次】
(1)小気味よいおばさんとして
(2)喫茶店で執筆中に「チュー」?
(3)二足のわらじで落ち着く場所へ
(4)祖母「あんた、年取られんな」
【むろい・しげる】富山県出身。1981年に映画「風の歌を聴け」でデビュー。俳優、エッセイスト、声優として活躍し、2023年には「高志の国文学館」(富山市)の館長に就任。新刊「ゆうべのヒミツ」には、週刊「女性セブン」での同名タイトル連載(2021年開始)と「夕刊フジ」での連載「瓢箪なまず日記」から自身が選んで再構成した103編を収めた。
(1)小気味よいおばさんとして
記者 完成した本を見てどう思いますか。
室井 絵本作家の長谷川義史さんにカバーをお願いしました。「温かみのある感じにしてください」とリクエストしました。とてもいいと思います!銭湯に通っている私、そして大好きな猫がそばにいて街を歩いているというような「私の日常」ですね。ここにないのは自転車かな。
記者 前作エッセー本「ヤットコスットコ女旅」からの5年間をどうまとめましたか。
室井 世の中の流れが早く、エッセーは生もの、「今」をすごく感じてもらわなきゃいけない部分があるので、あえて新型コロナウイルス禍の話題は割合を減らしたところはあるかなと思いますね。もちろんコロナ禍を経て、今は2024年、そして2025年に向かうわけです。「そういうことがあったからこそ、今こうだね」という話は入れています。
おばさんとしてだいぶ年季が入ってきたので、少しパンチを効かせ、小気味よいおばさんとして「若い人が言えないことは、おばさんがズバッと言いましょう」というものは随分入れています。
※新刊第3章に「オバサンを舐めんなよスイッチ」を収録。室井が東京駅発の新幹線に間に合うよう、急いで乗車したタクシーが裏道を通り抜けようとしたところ、荷下ろし中のトラックに止められてしまう。室井が車から降り、放った一言が痛快なまでに状況を解決する。
それと、ご縁と言いますか、今まで生きてきて「こんな不思議なことありますよね」という視点に立ったものも選んで入れています。あとはハートフルなもの、プラスして、これからの時代へのクエスチョンというか、私なりの投げかけを中心に入れている感じですね。
私は時代遅れながらも頑張って生きているつもりです。(芸能界にいて)情報量は相当あるのですけれども、その中であえて「今、自分の好きな生活を私はチョイスして生きています」ということを、少しばかりアピールしているところもあるのかなと思います。
(2)喫茶店で執筆中に「チュー」?
記者 執筆のペースは? どんなシチュエーションで書いていますか。
室井 毎週必ず書かなきゃいけないものが2本、それ以外に単発でお引き受けしているものや、絵本を書くこともあり、高志の国文学館館長もしていますので何かを書かなければいけないということもあります。だいたい3日に1回は書いています。
よく喫茶店で書いている時、ちょっとした事件が起きることもあるんですよ。例えば、コロナ禍の夏、隣の席との間にアクリル板があった時に、隣の男性が私の足に、足でツンツンってやっている感じがしたんですよ。でも知らん顔なさっていて、またツンツンときたから、「えっ? 次(ツンツンと)来たら絶対注意しよう」と思っていたら、今度別の方向からからツンツンと来たんです。右に来ていたのが左からも来る、左は誰もいない、壁ですから。なんでそんなに長い足なのかと不思議に思っていたら「チュー」と声が聞こえて、見たら足元にネズミがいて「キャー!」。
コロナ禍で風通しを良くしなきゃいけないので、表の扉が開きっぱなし、だから外からネズミも入ってきて。お店の人と一緒に、ネズミを上手に外に誘うことにトライしました。
そういうお話はなかなかないことなので、すぐに書きます。
記者 ご自身もエッセーに「珍事体質」と書いています。珍事を引き寄せてしまうのでしょうか?
室井 書こうと思って、日々いろんなものを観察して歩いているわけでもないんですけど、例えば、ぼんやり窓の外を見ていると、突然、自転車に乗って食べ物を運んでいらっしゃるアルバイトの方が、残念ながら転んでしまわれて、びっくりして見ていたら、その方が、これからお届けしようとする商品を取り出して大丈夫かどうかを確認して、ちょっと中身が崩れていたんだと思います。ちゃんとなるように手で振っていらっしゃる姿を、窓越しで見ちゃうじゃないですか。
転んじゃった彼もすごくお気の毒だし、これを届けられたお宅の方もお気の毒じゃないですか。一つの事柄から、私も思ったり考えたりしますので書いています。
他に、外国人のタクシードライバーさんが昔はいらっしゃらなかったのに、突然というか、じわじわというか、いらっしゃって。自分がタクシーに乗って、話が全然通じないなと思ったらインドの方だったと。皆さんも経験なさっている方が多いと思うんです。今、世の中でこういうことは結構あるよねということを割といち早く、エッセーに書いています。
(3)二足のわらじで落ち着く場所へ
記者 読者層を意識して盛り込む部分もありますか。
室井 女性の中高年の方が多いのかなと思います。タイトルが「ゆうべのヒミツ」で一つのポイントは「不眠」でした。「夜、皆さん眠れてらっしゃるのかしら?」みたいなことを結構、話題にしています。私も随分前からしっかりとは眠れなくなって、朝早く放送している時代劇を見るようになっちゃって。
真夜中にぽっこりと目が覚めた時、つけっぱなしだったテレビで思いがけないものを見て、すごく良かったということも、何編かに書いています。例えば、欧州の街並みを電車やバスがずっと行く。軽やかな音楽だけを乗せ、空から写したお城の風景が続く。若い頃はおそらくつまんないと思ったと思うんですけども、今は結構じっと見ていられます。
夜中に目があまりに覚めることが続くのは、体にもちろん負担になりますけれども、「それはそれで面白い」という風に思った方がいいのかなと思います。
記者 エッセーを書く上での師匠、もしくはこうありたいと思うような存在は?
室井 本当に全くなくてですね。元々が俳優で、書き手として書き続けるぞと思ってやってはきていなかったので。あまり向上心がなかったとも言えるなと、思うんです。
「女優道」と「書くこと」の二足のわらじをずっとやってきています。「書く」という仕事は、私にとって気持ちの上ですごく落ち着く場所。編集者の皆さんとお付き合いができ、小説家の方々からお話を伺う。
(俳優としての)私たちは、映画の台本、テレビのシナリオなど文学に出てくることを体で表現する。遠いようで全然遠くなくて、自分が文学と近いところにいられるというのは、女優としてもとてもありがたいことです。
「集団」で演じることが私たちの日々なのですが、書くことは本当に「個人」として、自分の好きな時間に自分だけの世界で書けるので、そこはまた大きく違う。二つのことが自分にとってとても良かったから続けています。
記者 新刊エッセーで、中学時代の修学旅行を振り返り、富山県人の真面目さを表すエピソードとして、バスの乗り降り練習をつづりました。ご自身のルーツをどう感じていますか。
室井 私たち富山で育った人は「立山連峰の向こうに何があるのかな」と思い、「あの山を越えて、絶対どこか違うところに行きたい」と、若者はそう思い、雪国を一回は出たいなと思う人、あるいは出られなくてもそういう思いを抱かれた人がほとんどだろうと思うんです。どこの県でも、若者は似ていてそういうものかと思うんです。
私も本当に早くそこから飛び出し、違う風になりたいなと思いました。でも10年ぐらい過ぎると、田舎の食べ物がすごくおいしかったり、結構無愛想に思えた町の人がものすごく優しかったりすることに気付いたんです。「一番居心地のいい場所だ」とだんだん気が付き、田舎でも仕事ができないかなと思い、ラジオ出演をするようになりました。
高志の国文学館の仕事をお引き受けして、今、2拠点の生活をしています。都会のことだけを知っているよりも、地方のことを深く理解することが、自分にとって大切なことになっています。「都会に生まれ育ち、田舎のことを全然知らない」と言う友人がいて、私が話すと、「一回富山へ行きたい」と言ってくれて、遊びに来ると「やっぱり田舎があるのはいいね」となります。
記者 富山から見た東京、東京から見た富山という両方の視点が、俳優道、エッセイストの活動に生きているのですね。
室井 そう思います!
(4)祖母「あんた、年取られんな」
記者 新刊第1章の「一生モノ、持ってますか?」にちなみ「一生もの」をいくつか質問します。まず、大事にしている物は何ですか。
室井 物ではないですけども、やはり「友達」ですかね。私は割と、気持ちがしっくり合うと、付き合いが長くなるんですね。長い付き合いの人がそばにいるのは、すごく幸せなことだし、そういう人たちから「ちょっとおかしいんじゃない」「なんか変わったよね」「全然変わらないよね」「ちょっと時代から外れている」などと言われることが、「分かってもらえているんだ」という安心感になります。
記者 一生ものの言葉は?
室井 私はすごくおばあちゃん子だったんです。おばあちゃんはたくさん子供を産みましたが、私の父が一番年を取ってからの子供でした。高齢になって祖母が認知症にかかりました。すごく賢い、いろんなことを教えてくれる存在だったのに。子供ながらに、祖母が衰えていく姿を見るのが歯がゆく嫌だなぁと思い、祖母のすることに文句を付けるようになりました。すると祖母が悲しそうに「あんた、年取られんな」と言いました。
「あなたは年を取りなさんなね」という意味合いなんですが、その言葉を最近すごくよく思い出すんです。祖母の気持ちが今になって分かり始めたっていうんですかね。祖母は目に入れても痛くないぐらいかわいがっている孫から、年を取っていることを悪く言われてしまった。悲しかったと思う。私を叱るのではなくて、そういう風に言った祖母の言葉をね、本当によく思い出しますね。
記者 一生忘れられない共演者は?
室井 石橋蓮司さん。私は大学時代に自主映画をみんなと撮っていて、大きな映画が撮れることになった時、黒木和雄監督の「竜馬暗殺」などたくさんの映画で活躍されていた石橋さんがみんなの憧れのスターだったんです。本当にすてきだった。「出てもらうなら石橋蓮司さんだよね」とみんなで言っていて、「自分たちの映画に出てもらえませんか」と頼みに行ったら快く引き受けてくださって、怒鳴るようなコーチ役で出演してくださった。学生それぞれが小遣いを集めて、お金を包み「すみません、これでお願いします」と言ったら、「こんなのいらないから、何か食べて帰りなさい」とおっしゃったんです。
その後、大人になって、石橋さんに何度も撮影現場でお目にかかり、共演させていただくようになって、石橋さんも私が学生の時に共演させていただいていたことを覚えていてくださった。
(NHK連続テレビ小説)「花子とアン」では、石橋さんがお爺やんの役で、私が(主人公・花子役の)吉高由里子さんのお母さん役で、「明治から大正にかけての家族風景」を演じました。
私たちは農民の役で、顔が日焼けで真っ黒なので、歯がかえって白く映ってしまう。石橋さんが「しまった。これは気をつけないと、おかしいから」と歯を黄色くするために少し汚しをかけてもらっていました。その姿に「さすがだなぁ」と改めて思いました。
記者 最後に新刊のアピールを。
室井 大変なことがたくさん起きている世の中ではありますが、自分のささやかな生活を私は大事にしたいなと思う。自分自身が何を望み、何に幸せを感じるのか、興味が動くのか、ということにきちんと向き合い、「もっともっと楽しくならないかな」「もっともっと面白いところに行けないかな」と、幾つになっても考えていたいなと思っています。そういう「好奇心」を本を通じて感じ取っていただき、「私もそう思うよ」「私だったら、もっとこうなのに」と、パラパラとめくっていただけたら、ありがたいなと思います。
(取材・文=共同通信 藤原朋子 撮影=佐藤まりえ)
※YouTubeチャンネル「うるおうリコメンド」で室井さんのインタビュー動画をご覧になれます。
https://youtu.be/lanNsgwwsYg