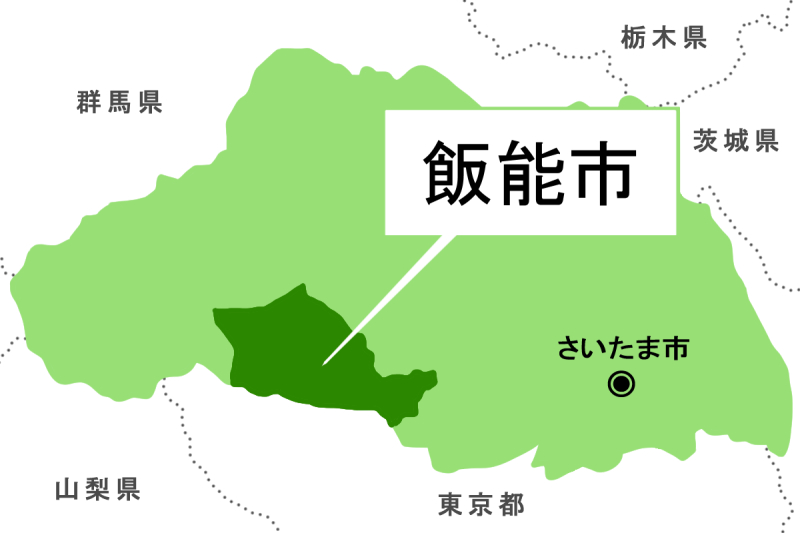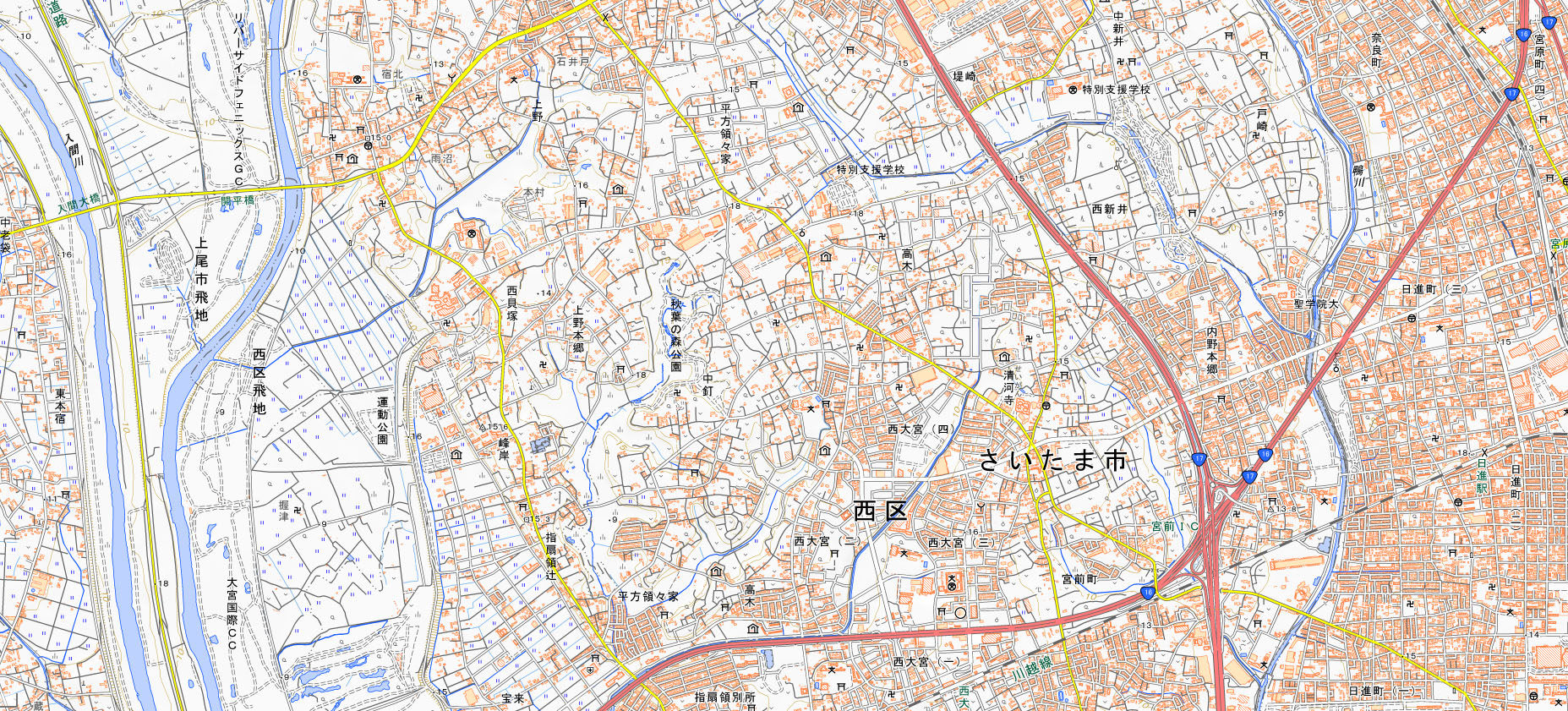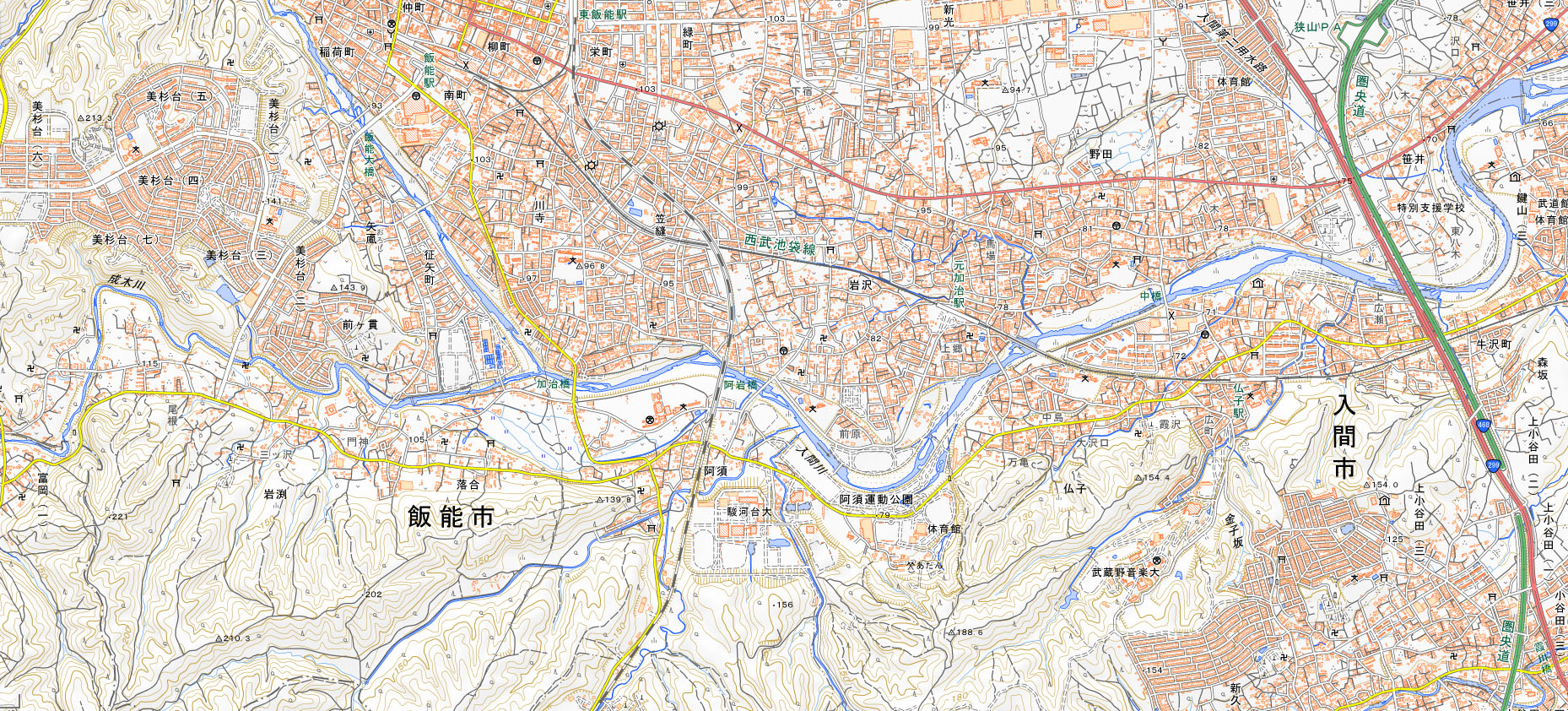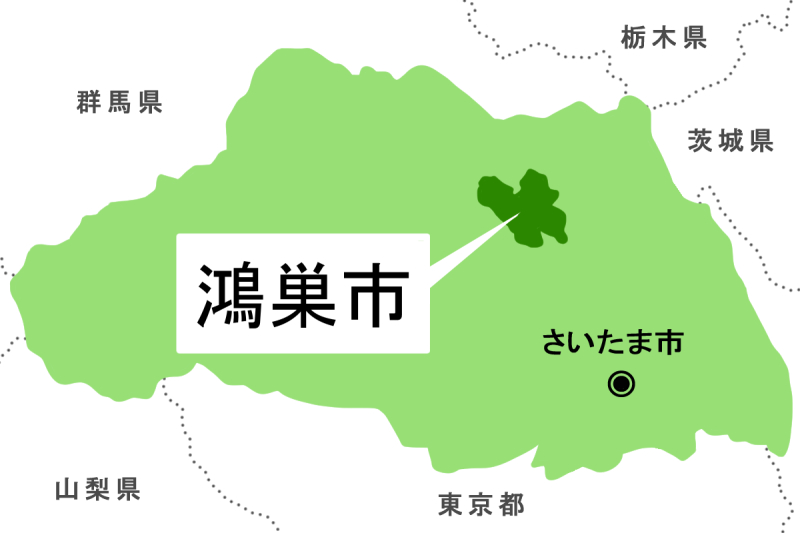【3分間の聴・読・観!(30)】坂本龍一と100年、宮沢賢治の100年 問い直し、かみしめて広がる風景
2023年3月に亡くなった坂本龍一の大型インスタレーションを集め、日本では初の大規模な個展となる「坂本龍一-音を視る 時を聴く」(東京都現代美術館、3月30日まで)は、音と映像を立体的に構成することによって時間の概念を問い直している。
中でも坂本とアーティスト高谷史郎のコラボレーションの新作《TIME TIME》に強い磁力を感じた。2021年の作品『TIME』を基にしており、三つの大画面に夏目漱石「夢十夜」、能「邯鄲」、荘子「胡蝶の夢」をモチーフにした映像と音楽が繰り返し現れては、眠りの中の夢と時の流れを溶け合わせるように展開する。
「もう死にます」。そして「百年、私の墓の傍に坐って待っていて下さい。屹度(きっと)逢いに来ますから」と女が言う「夢十夜」の有名な第一夜。ここで重要な意味を持つのは「百年」である。現実の世界では限られた人しか体験することがない長い時間だが、この短い夢の語り手は最後に「百年はもう来ていたんだな」と気づく。誰にでも同じだけ進む時間が歪んでいる。
重量感のある朗読を聞かせる田中泯は、ある場面では何かを畏怖し、おののくような表情を見せる。「邯鄲」では50年の歳月が一瞬の眠りと等しく、「胡蝶の夢」では夢とうつつが判然としない。
終始低く流れる坂本の音楽や笙の音と、大画面の前に張られた水の反射に包まれると、時間が本来持っているはずの厳格さや一方向に進む圧力が消える。今、立っている展示空間の時間がするするとほどけ、100年の歳月が循環しているのではないかと幻惑された。
坂本と高谷とのコラボから、もう2作品取り上げたい。東日本大震災で被災した高校のピアノを作品としてよみがえらせた《IS YOUR TIME》では、世界各地の地震データを基に、鍵盤がさまざまな間隔で押し下げられて鳴る。分かりやすく時間の流れをたどれるメロディーやハーモニーから自由になった1音、また1音が、胸に浸み込み、響く。原初の感動とはこういうものではないかと思った。
《async‐immersion tokyo》では横に長い18メートルのLEDウォールに、坂本のニューヨークのスタジオで撮影されたピアノ、打楽器や、自然の風景が映る。それらはスキャナーにかけられたように端から徐々に姿を変え、ついに1本の長い横線が織り重ねられた何物かに解体されていく。不可分なはずの存在と時間を揺さぶるのだ。
詩人で比較文学研究者の管啓次郎と、音楽家で作家・翻訳家の小島敬太の共著「サーミランドの宮沢賢治」は、2024年の冬にフィンランド北部のサーミランドへ賢治の作品を携えていった2人の紀行文。100年前に生きた賢治の時間を、はるか遠い北欧から捉え直して新たな魅力を引き出している。
賢治が「銀河鉄道の夜」の執筆に着手したのが1924年であることは、知人らの証言から分かっている。さらに言えば「永訣の朝」などに刻んだ妹トシの死は1922年。その翌年に賢治は列車で北に向かい、死者を追憶する詩を書いている。闇と死の場所としての北に憧れていたのではないか―。100年の時間を超え、賢治をさらに北辺の地に連れて行こうと2人は旅立った。
トナカイの肉をベリーソースで味わうディナーなどサーミの暮らしに触れ、心身にじわりと風土がしみ込む。賢治と出会い直す数日間の2人の旅が、それぞれの目を通した2編でつづられている。
管、小島と作家古川日出男、翻訳家柴田元幸は「銀河鉄道の夜」の朗読劇を続けてきた。サーミランドの凍った湖でも、管は「春と修羅 第二集」から詩を朗読する。その1編「三二九〔野馬がかってにこさへたみちと〕」に寄せた管の思考に引きつけられた。
人が進むべき道を巡って書かれたこの詩から両義性を導き出し、新しい読み方に至った戦慄と陶然。厳寒の北辺まで賢治を伴って来た意味はここにあるのだろう。私にも広々とした風景が浮かんできた。
小島もサーミランドの空の下で賢治作の「星めぐりの歌」を歌う。東京で聴く小島の歌声には澄みきった美しさがあり、美しさゆえに少しだけかなしみも感じさせるのだが、この場面を読んでいる時も冷気とさびしさに粛然とした。静かな北極圏の星々に誘われたような気がして、今まで何度聴いたか知れない「星めぐりの歌」の魅力を改めてかみしめている。(杉本新・共同通信文化部記者)
【今回の作品リスト】
▽「坂本龍一-音を視る 時を聴く」(東京都現代美術館、3月30日まで)
▽管啓次郎・小島敬太著「サーミランドの宮沢賢治」
すぎもと・あらた 1924年、宮沢賢治は詩集「春と修羅」、童話集「注文の多い料理店」を出版しました。生前に世に出した著作はこの2冊だけでしたが、同じ年に「銀河鉄道の夜」の最初の形を書き始めたように、充実した年だったようです。そう思うと、2025年は「賢治第2世紀」の始まりと言えるかもしれません。未踏のイーハトーブが私たちの前にあります。