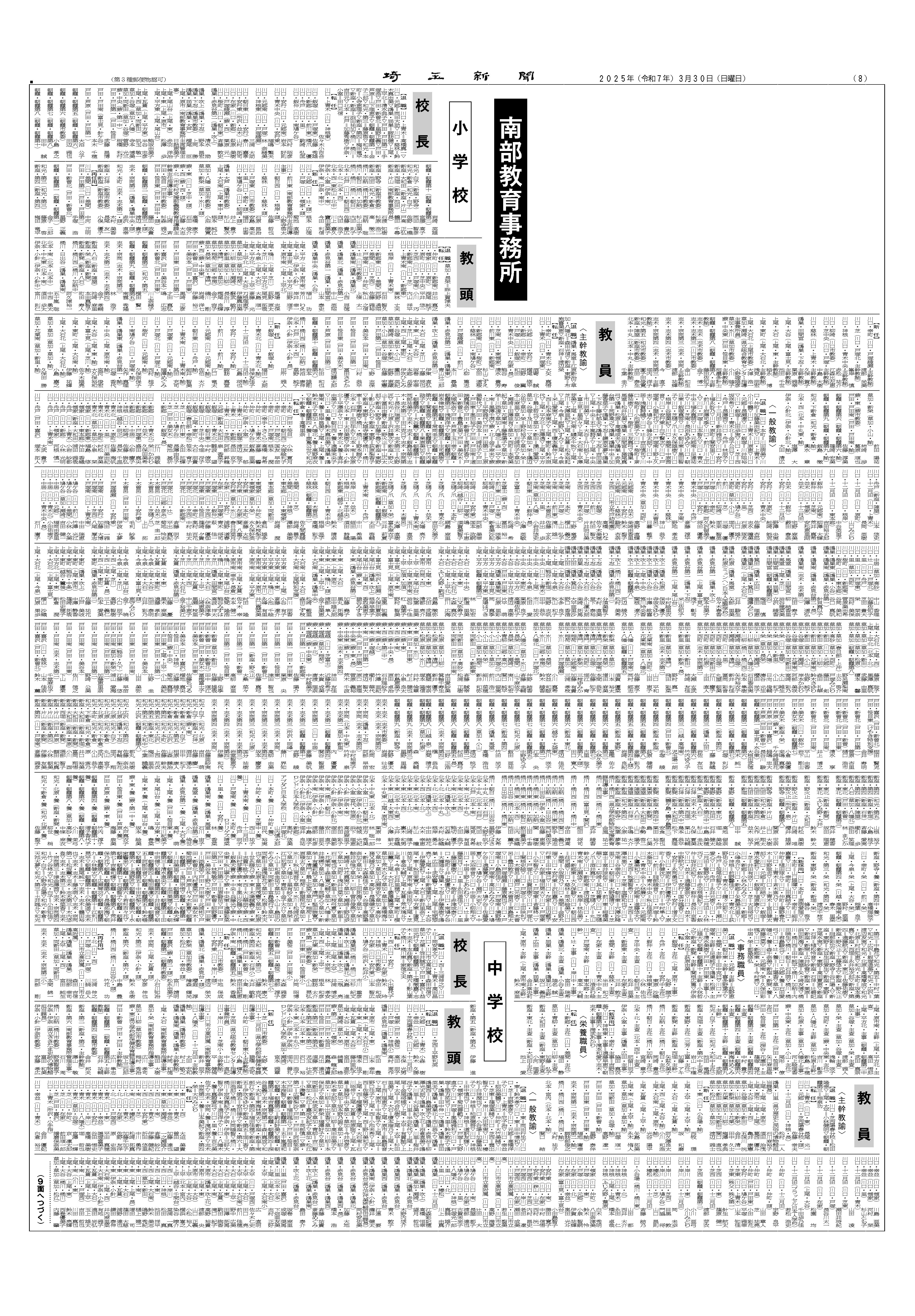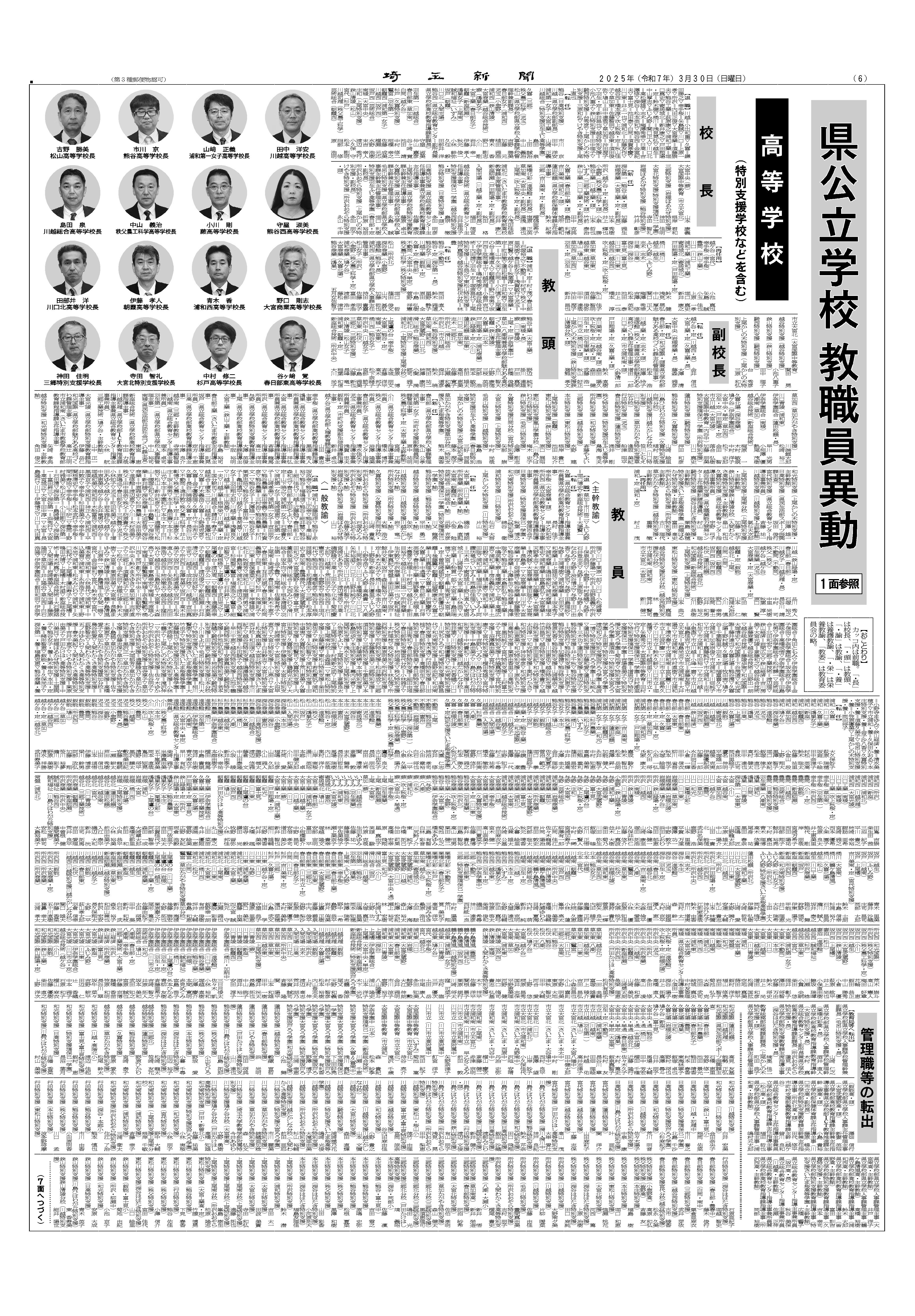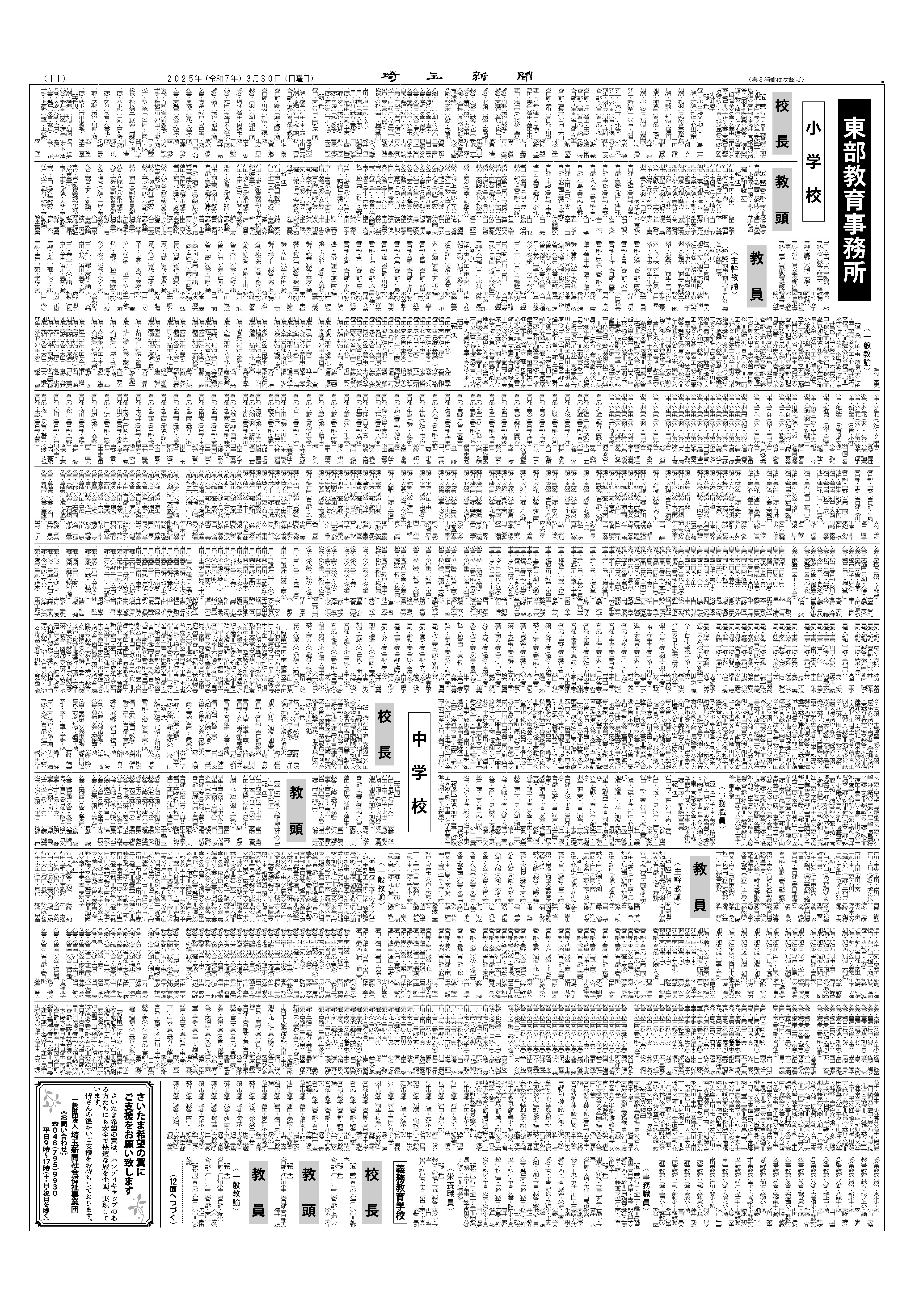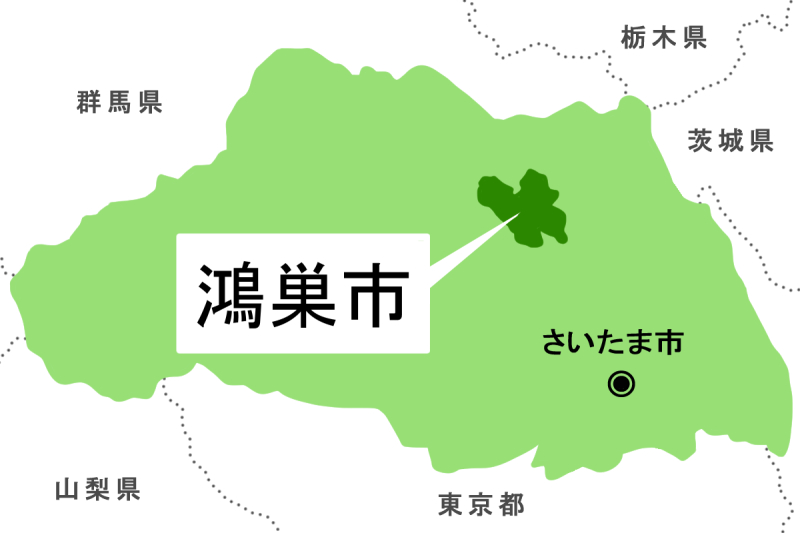今までに経験ない…八潮の道路陥没 穴が刻々と拡大、救助が困難に 要因は下水管の存在と垂直の壁面 点検や補修など対策急務…危機管理防災アドバイザーが警鐘「全国各地で発生する可能性」
2025/02/02/10:02
埼玉県八潮市二丁目の交差点で県道が陥没し、トラックが転落した事故は1日、発生から5日目を迎えた。
元深谷市消防長で危機管理防災アドバイザーの田中章さん(65)は今回の道路陥没について、「今までに経験のないもので、救助活動の難しさを肌で感じる」と語った。
田中さんは1月29日に現地入りして周辺の状況を確認した。これまでにも道路陥没の現場での活動は何度も経験してきたが、陥没してできた穴が刻々と拡大した現場は初めてだという。田中さんによると、活動を困難にしている要因は陥没現場の下を通る下水管の存在と、ほぼ垂直に陥没した現場の状況だ。
上水はバルブを閉めれば管の水流を止めることができるが、下水は排水を抑えることでしか水流を抑える方法がない。下水管が破損してしまうと土砂の流入を止めるのは簡単ではないとし、「水分で軟らかくなった土砂は崩れやすく、結果的に崖のような垂直の壁面ができてしまった」と推測する。
田中さんが経験した道路陥没事故の多くは、救急隊員が地上から命綱を使って穴の中に進入するケースだった。しかし今回は深さ最大15メートルの穴であることや、陥没が拡大する可能性があることから「異例のスロープ造成という判断に至ったのだろう。スロープは重機進入のためだけでなく、隊員の退避経路の意味合いもある」とした。
2日には陥没現場付近で降雪の予報も出ており、現場の土砂にも影響を与える可能性があることから、活動の進行が鈍くなる懸念もある。「現場の救急隊員は一刻も早く救助したい気持ちをこらえて、二次被害が起きないように注意を払っている」とした上で、「下水管の耐久年数を考慮すると、陥没事故は今後全国各地で発生する可能性がある。大規模な点検や補修などの対策が急務」と警鐘を鳴らした。