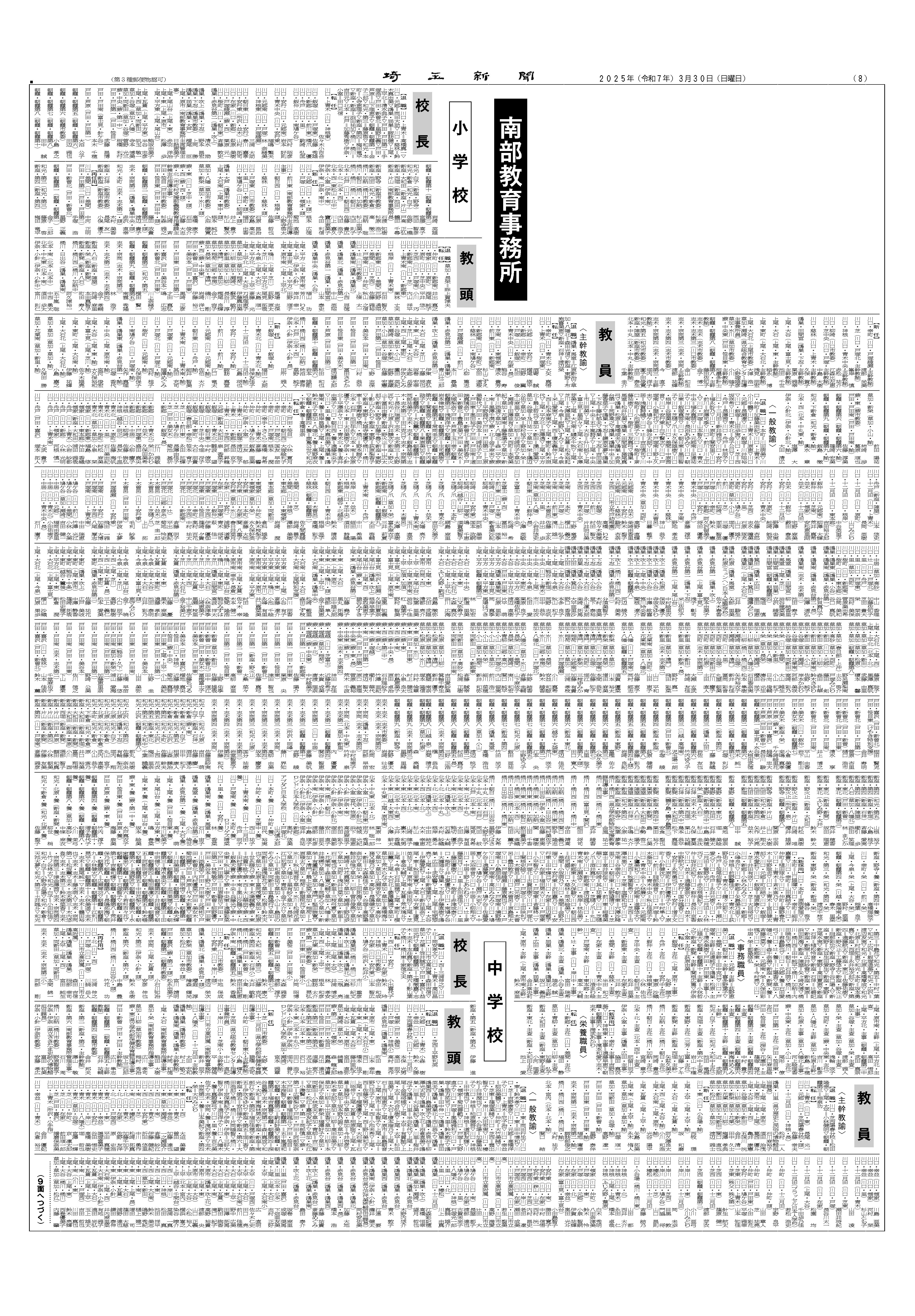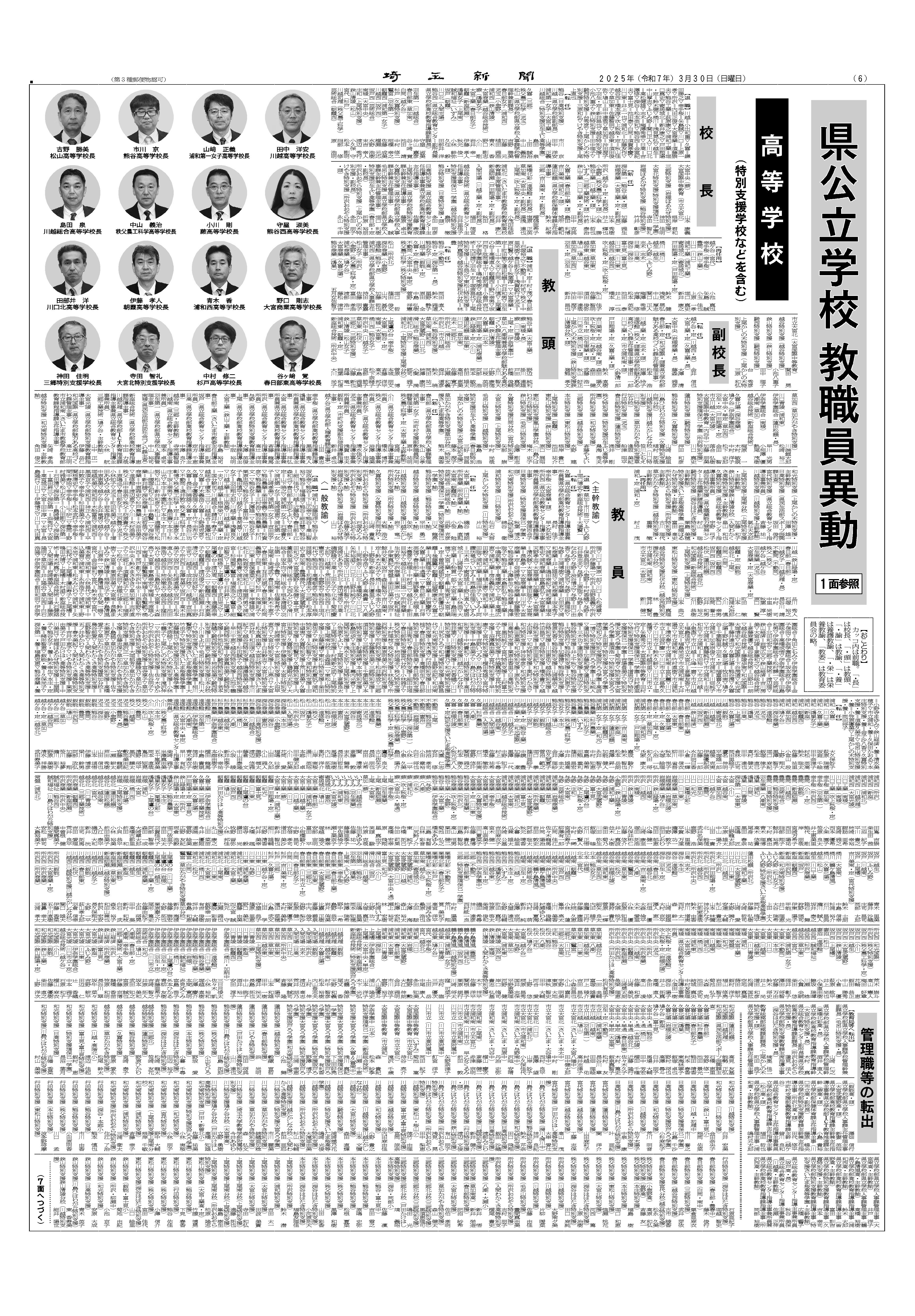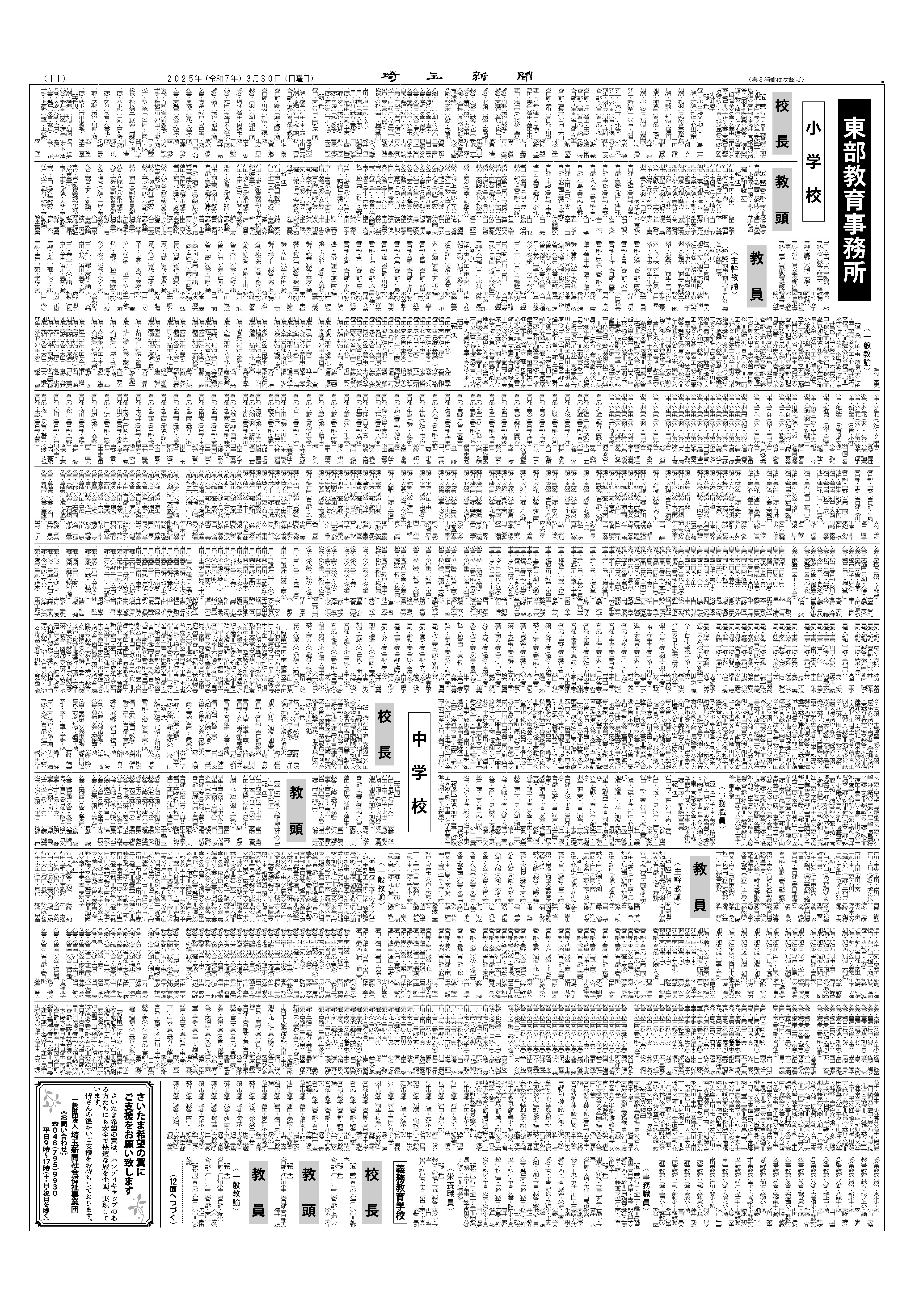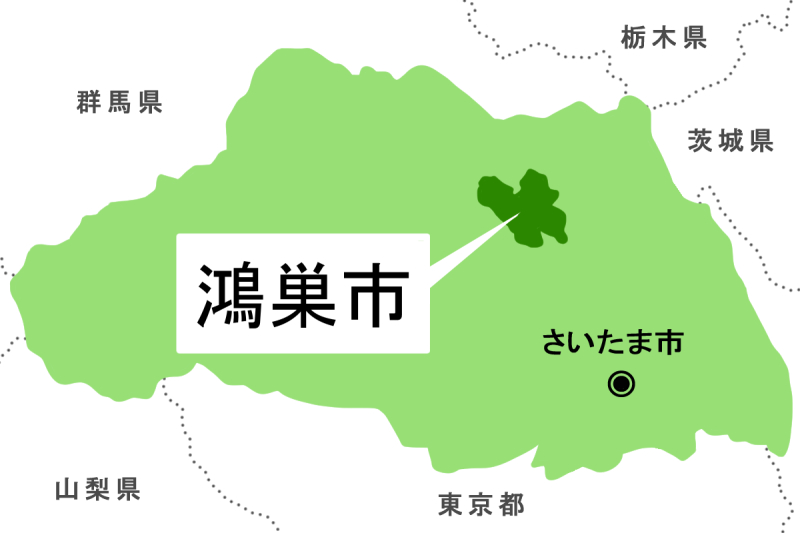【動画】道路陥没…製造が止まった工場も 職員用の風呂を使用禁止に「工業用水もいつ止まるか」 クリーニング店も洗う時の水量減らす…春の衣替えに向け利用増、長期化へ不安 給食センターも節水、落ちる効率「できる限り対応」
八潮市で発生した県道の陥没事故は4日で発生から1週間となった。トラックの男性運転手の救出活動は難航。県内12市町の約120万人を対象とした下水道の利用自粛が続いている。事業者は先を見通せないまま、不安を訴えながら、工夫して節水に取り組んでいる。
東関東生コン協同組合よると、工業用水などの上水管が止まったため、生コンの製造が止まっている工場が県内にあるという。災害などへの対策として、各工場で製造を分担していたことから組合内の別工場で代替し、現場に滞りなく供給できているという。同組合の担当者は「工業用水に関しては情報がほとんど入ってこない。この先どうなるか読めない」と長期化への不安感をあらわにした。
八潮市商工会には事故現場周辺の事務所から補償などに関しての相談が数件あったという。申請書類の書き方などをサポートしており、宍倉身事務局長は「今後の見通しが立っていない。行政に動きがあれば動きに沿って活動していきたい」と話した。
草加市の日本製紙草加工場では、職員用の風呂を使用禁止にした。工業用水は止まっていないものの、浄水場による水質調査は頻度が多くなっているという。担当者は「工業用水もいつ止まるか分からないので不安」と語った。
八潮市内でクリーニング店を営む70代男性は下水道の使用自粛で、排水を減らす工夫をしているという。「一回に洗う時の水量を減らしている。(節水が長期化した場合は)お客さんに納期を待ってもらったり、難しい場合には組合を通じて別のお店にお願いすることがあるかもしれない」と対応策を検討している。
草加市瀬崎でクリーニング店を営む県クリーニング生活衛生同業組合の柳裕一理事長によると、組合に加盟する県東部のクリーニング店で大きな影響は出ていないという。業界にとっては真冬のこの時期は閑散期で、春の衣替えに向け利用が増えるという。災害時は組合員同士で仕事を融通するなど連携することも想定するが、現状各店舗で通常通り業務を行っている。
柳理事長は「節水は行政の指導に従って対応している。行政とも連絡を取っていて、仕事に差し支えない範囲で、水をなるべく出さないよう工夫している」と話している。
八潮市内小中学校の給食約7千食を提供する四季亭・東部給食センター(八潮市新町)は節水のため、各小中学校から戻ってきた食器を時間帯を分けて洗うなど工夫している。「効率は落ちるが、できる限りの対応をしている。(長期化した場合は)教育委員会と検討することになるが、今の段階で決まっていることはない」としている。
埼玉りそな銀行八潮支店は、避難所と八潮消防署に使い切りカイロや栄養ドリンクなどを寄贈した。市職員に必要な物資を確認し、今週中に再度贈るという。吉川久支店長は「一刻も早く救助されることを心より願っている。避難所で生活を送られている方や昼夜問わず懸命な救助活動をしている隊員の方に何かできないかと思った」と話した。