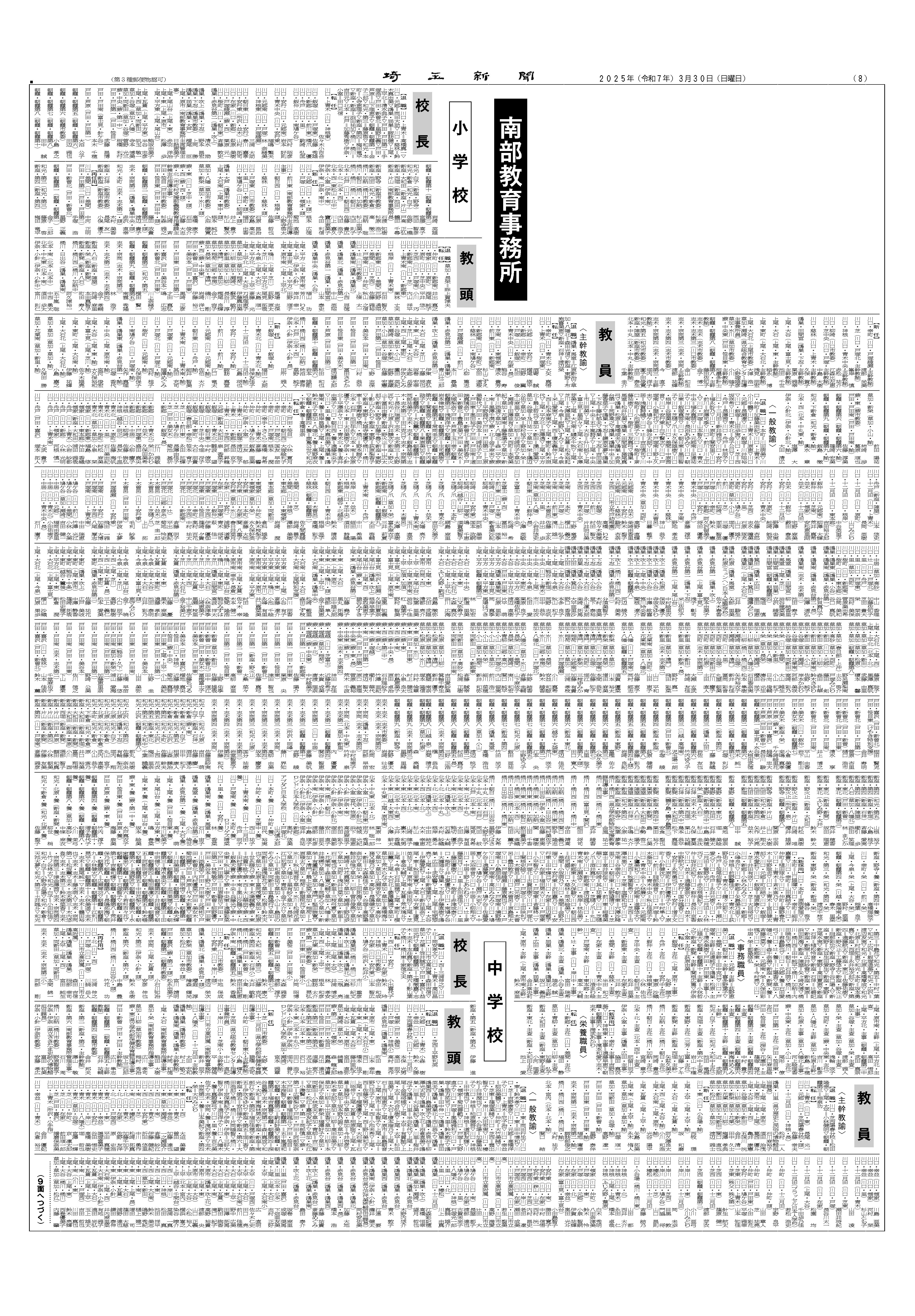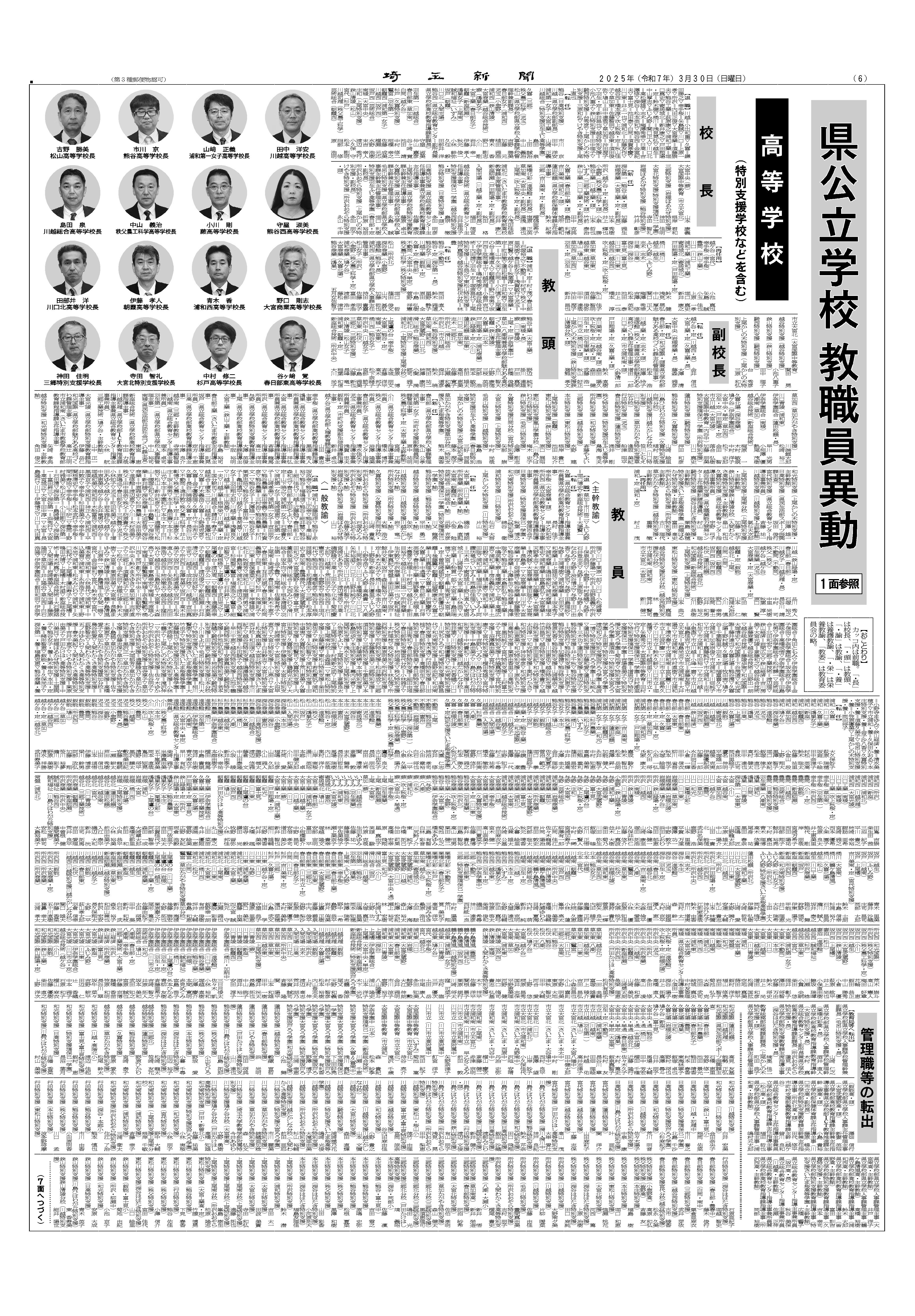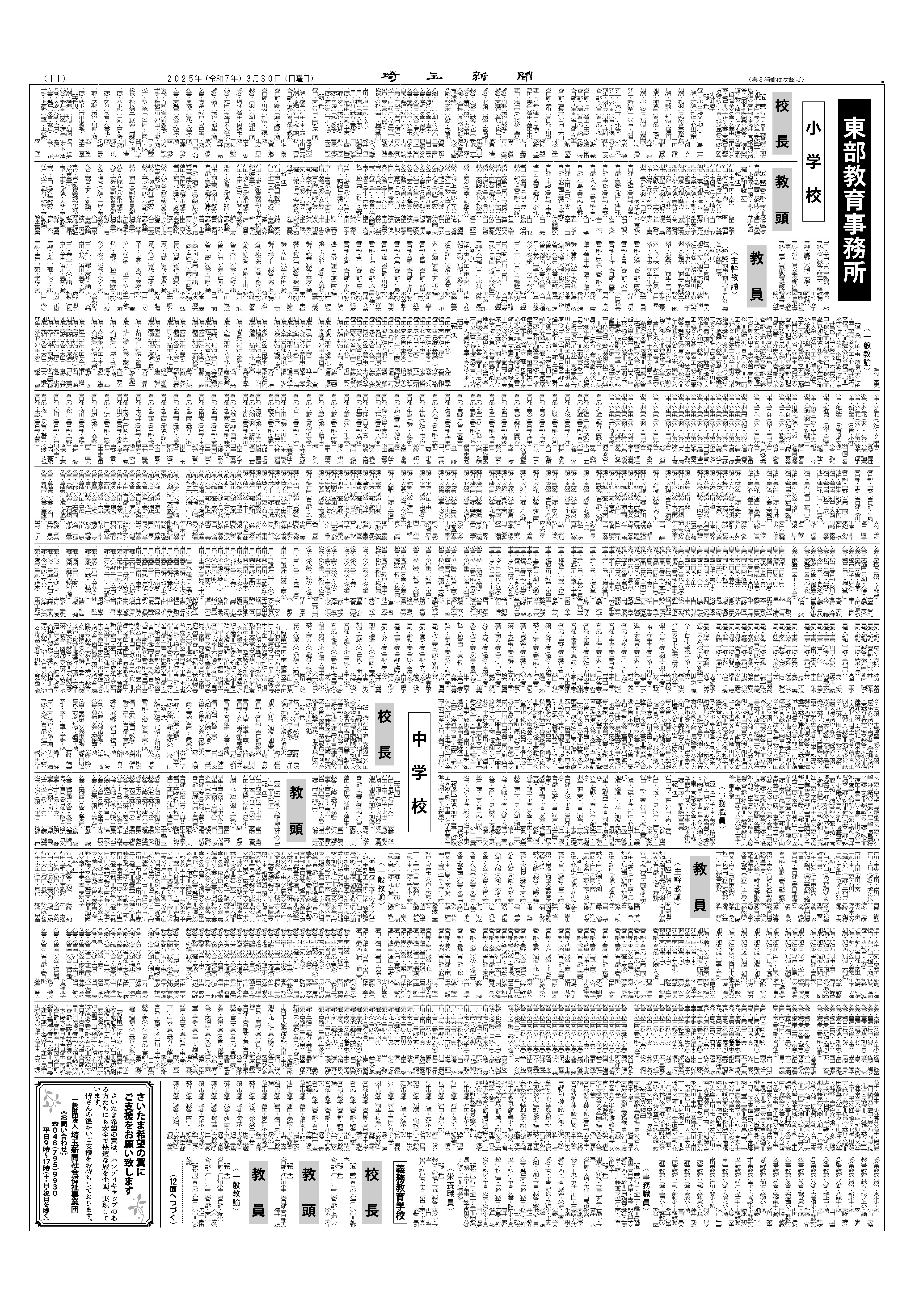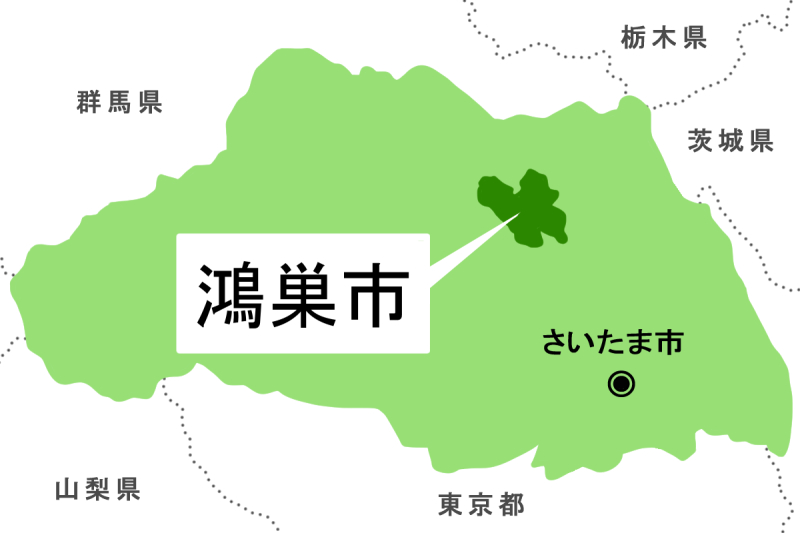道路陥没…下水道の利用自粛が解除で安堵も 男性運転手はいまだ救助されず心配の声 「完全に復旧するまで安心できない」「すぐに(水の使用を)元に戻していいのか分からない」
八潮市で県道が陥没しトラックが転落した事故で県は12日、県内12市町の約120万人に呼びかけていた下水道の利用自粛を解除した。事故から約2週間にわたって節水に努めてきた現場周辺の住民は安堵(あんど)する一方で、男性運転手がいまだ救出されていないことを心配する声もあった。
事故が起きてからは三郷市で風呂を済ませたりしていたという主婦(71)は自粛解除に「やっと終わった。今日はゆっくり湯船に漬かりたいと思う」と胸をなで下ろした。
約2週間の下水の利用自粛で、八潮市中央1丁目の「コインランドリーかもめ」では、利用客が半分ほどになったという。自粛が呼びかけられていない東京都へ洗濯をしに行った人が多く、管理する男性は「ここから少しずつ利用客も戻ると思う」と期待した。
1月28日に発生した事故は陥没箇所の拡大や水流などにより、穴の中に取り残された男性運転手(74)の救助は難航。ドローンによる調査で下水管内でトラックの運転席部分が見つかり、男性が取り残されている可能性が高いと分かった。下水を迂回(うかい)させ、運転席に向けて掘削する方法が検討中だが、工期は約3カ月を要する見込み。
事故現場近くに住む夫妻は湯船には漬からずにシャワーで済ませたり、食器にラップをして洗い物を減らしたりと工夫した。自粛は解除されたものの、妻(76)は「まだ運転手の男性が見つかっていないので、すぐに(水の使用を)元に戻していいのか分からない」と不安そうに話した。
市内の保育園に子どもを通わせている30代の女性も食器洗いや洗濯を短時間で済ますなど節水を心がけたが、「解除といわれてもまだあまり実感がない。運転手さんが心配」と話した。
杉戸町の男性会社員(48)は「下水道の使用制限が解除されたのはありがたいが、これで排水が増えて、捜索活動に支障を来さないか心配。壊れた下水道管の復旧には時間がかかるようだし、完全に復旧するまでは安心できない」と話した。1人暮らしで、外食や外で調理されたものを持ち帰ることが多く、節水には風呂や洗濯の回数を少し減らした程度であまり不便は感じなかったが、「長期化すると、『水を使うな』という無言の圧力が生まれそうで嫌だなと思っていた」と漏らしていた。
洗濯の回数を減らしたり、風呂の残り湯を沸かし直したりするなど節水に協力してきた幸手市の女性(85)は「このまま下水道が使えない状態がずっと続いたら、大変だと思っていた。解除されて良かった」と喜びつつも、「事故の影響で避難している人たちの生活が心配。運転手も早く救出してほしい」と話した。
■事業再開いつに 不安の地元経済
周辺12市町の約120万人に求めていた下水道の利用自粛の解除を受けて、地元経済団体や金融機関では企業活動の影響について本格的な情報収集に乗り出した。
八潮市商工会の宍倉身事務局長は「いつまでこの状態が続くのかという不安の声が日々集まってくる。事業停止で実際に売り上げが減った企業もあるので金融機関とも連携を深めたい」と話した。一方、事故現場の目の前で商売する会員もおり、「事業再開のめどが全く見通せない中、今は捜索活動の進捗(しんちょく)を見守るしかない」ともどかしさも吐露。安否不明の男性運転手の一刻も早い救出を願った。
日本政策金融公庫越谷支店(越谷市)の中村靖支店長は行政など関係機関との情報共有に努める日々。クリーニング店や理美容店などの生活衛生関係だけでなく、12市町の幅広い業界の影響を調査し、「政策金融の担い手として地域経済の停滞を招かないよう有効な支援策を探りたい」と話した。
■さいたま市、区域内住民への浴場開放を終了
さいたま市は、八潮市の県道陥没事故による住民支援として実施していた市内の公共施設の浴場開放を12日で終了すると発表した。
市は4日から下水道使用制限区域の住民を対象に、健康福祉センターなど5カ所の浴場を無料で開放していた。