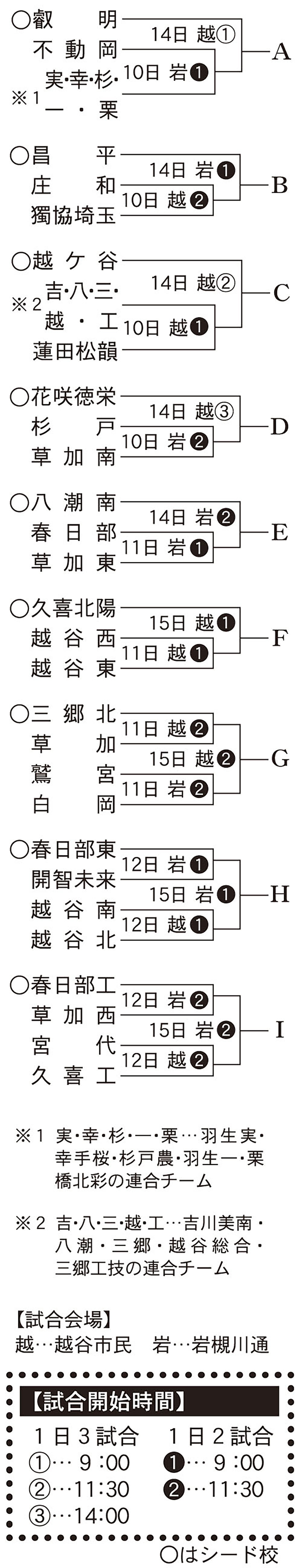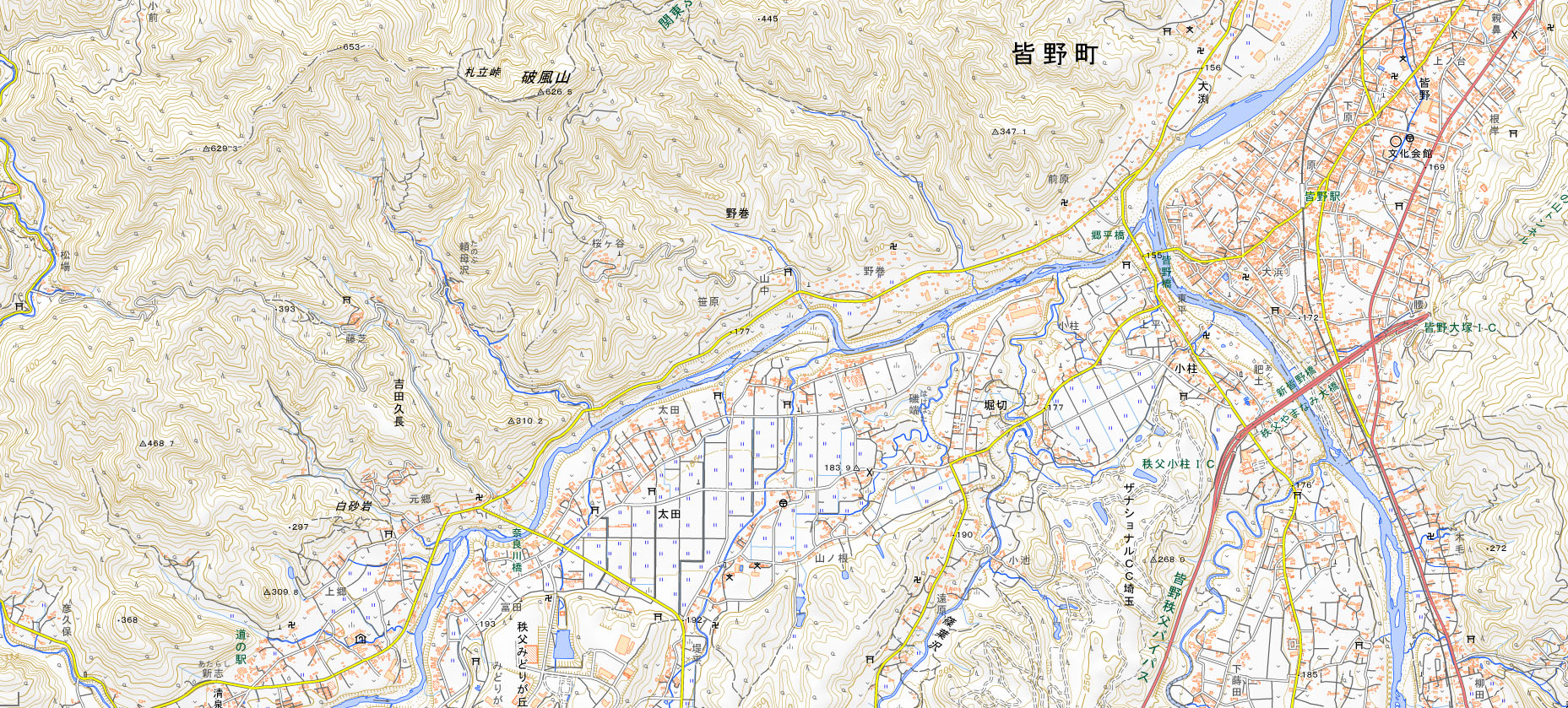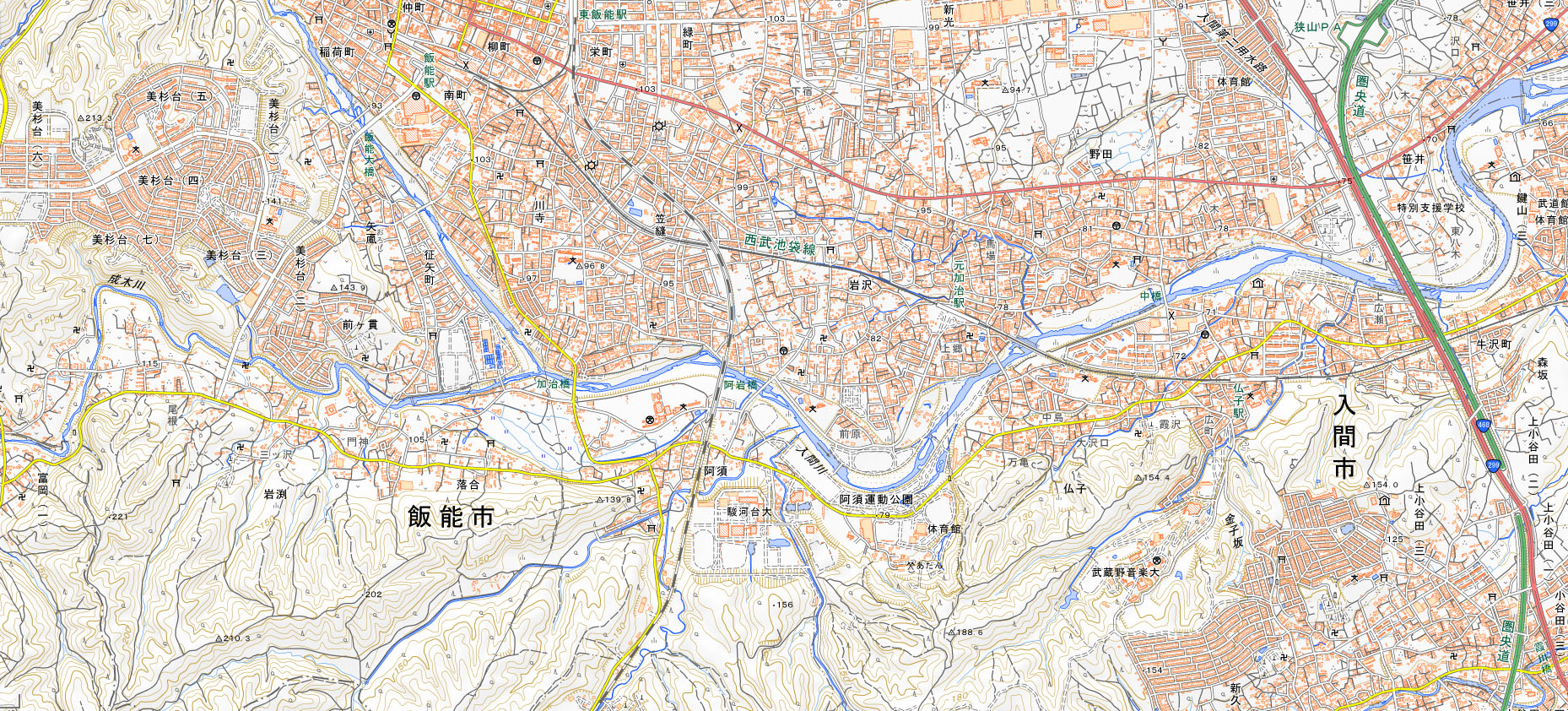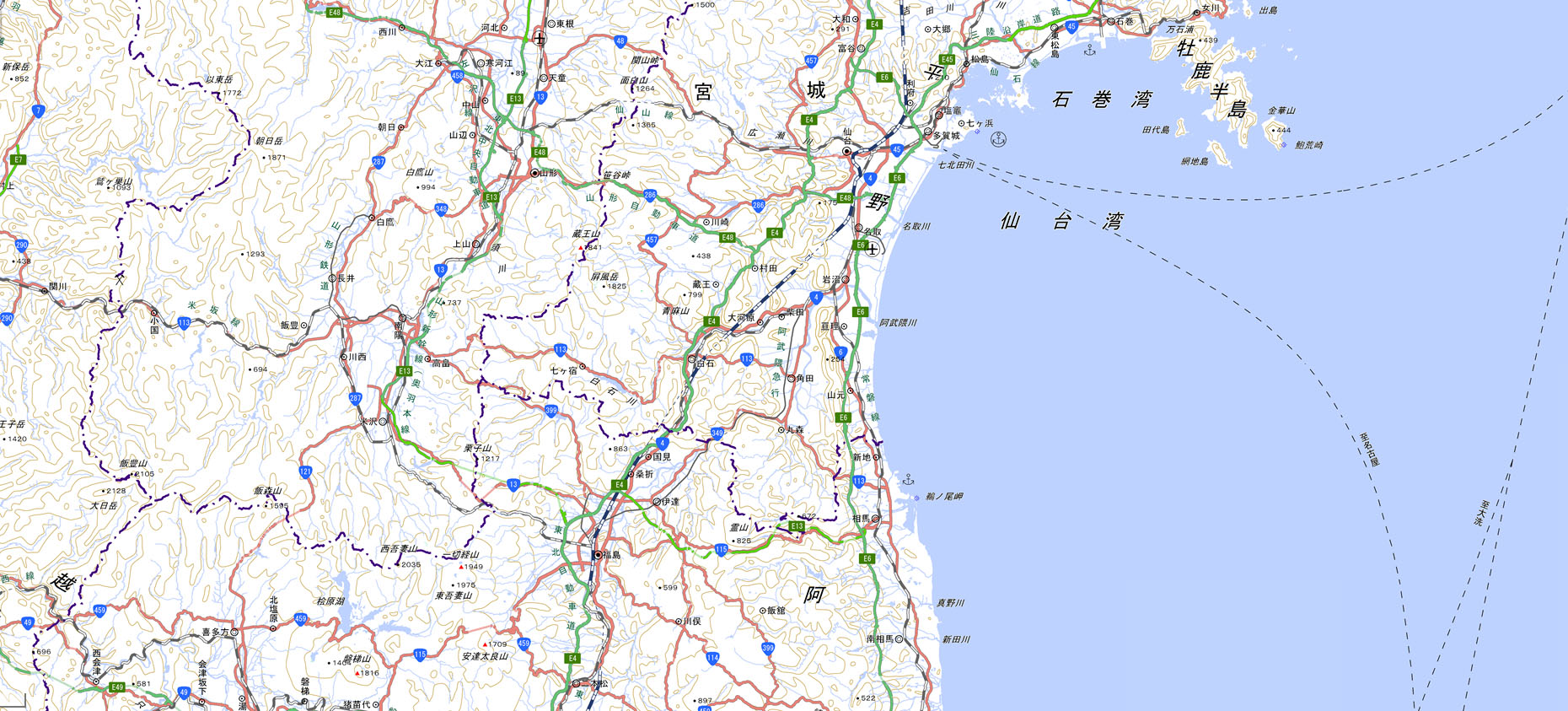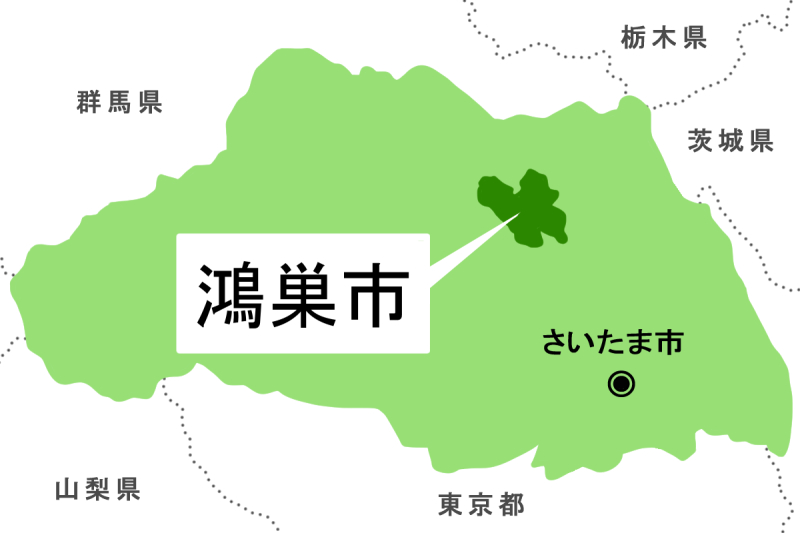【名作文学と音楽(32)】愛と幻想のチェンバロ音楽 小川洋子の『やさしい訴え』、須永朝彦の吸血鬼小説3作
ディドロの小説『ラモーの甥』では<哲学者>にさんざん悪口を言われたフランスの大作曲家ラモーだが、昭和の日本に彼を熱愛する文士がいた。その人の名は坂口安吾。1931年に発表したエッセイ『現代仏蘭西音楽の話』の冒頭で、「ハナハダ偉大なアインシュタイン氏によれば、古典音楽はバッハ、モツアルト以外の全てを抹殺して差し支へないと言ふのです」と振っておいて、自分の考えではそこにラモーを加えなくてはならないと力説した。
前者二人を「多少とも重い冥想を載せて、その憂鬱をワルツに紛らす都会人」と見立てた上で、ラモーを「エレガンなミニュエットに憂身を扮す可憐な淋しがりやです」といとおしがり、『シンデレラ』や『眠れる森の美女』のおとぎ話を持ち出しながら、「素敵に甘美な哀愁がラモオの音楽にはいつも流れてゐるのです」とうっとりする。<無頼派>のレッテルをはがしてみると、安吾は思いのほか乙女チックな趣味の持ち主だったようだ。また、戦後になってもラモーへの心酔は変わらなかったとみえ、飼い犬のコリーをラモーと名付けて可愛がった。
小川洋子(1962~)の『やさしい訴え』(1996年、文春文庫)は、そのラモーの音楽が重要な役割を果たす小説で、標題は彼の『クラヴサン曲集』の中の1曲から取られている。クラヴサンはチェンバロのフランス名。ちなみに英語ではこの楽器をハープシコードと呼ぶ。
主な登場人物は、カリグラファー(西洋書家)の瑠璃子、チェンバロ職人の新田、その女弟子の薫。愛人をつくり、酔って暴力を振るう夫に耐えられなくなった瑠璃子が親の持つ別荘へ家出し、近くに工房を構える新田と薫に出会ったことから筋が展開し始める。瑠璃子は新田に惹かれ、深い関係にもなるが、新田と薫が醸し出す<美しく調和した世界>が崩れることはない。瑠璃子の嫉妬は胸の中で静かにくすぶる。
瑠璃子は二つの三角関係が交わるところにいる。また、薫は薫で、過去に三角関係の深刻な悲劇を経験していた。彼女の婚約者には隠れて付き合う別の女がいて、結婚式の直前、彼はその女によって殺されたのである。しかし薫は事件の影をあらわに見せない。いつも愛らしく、素直で、なかなかの健啖家でもある。
瑠璃子が家を出る前に話を戻そう。本作で最初に出てくる音楽はチェンバロの曲ではなく、瑠璃子と夫の会話の場面で隣家から聞こえてくるヴァイオリンの音だった。10歳の男の子が毎日、コンクールの課題曲をさらっている。あまり上手ではないらしく、音は濁り、必ず同じ所で音をはずす。物思いに沈むような旋律で始まる短調の寂しげな曲だった。瑠璃子は前にも聴いたことのある曲だと思うが、題名を思い出すことができない。夫は関心を示さず、そのうち不機嫌そうに立ち上がり、愛人のところへ行った。瑠璃子の心情をなぞるようなこの曲(と少年の演奏ぶり)の名前は後に明らかになるが、今は書かないでおこう。
彼女が別荘に来たのは8年ぶり。着いた翌日、長年管理を頼んでいるペンション<グラスホッパー>の奥さんが、食べ物や日用品を持ってきてくれた。前に飼っていた猫と山羊は死に、今は孔雀がいると聞いて少々驚く瑠璃子。
何事もなく数日が過ぎた。5日目の夜、入浴中に雷雨がひどくなり、湯船から立ち上がろうとした瞬間、停電になった。そこへ蝋燭とマッチを持ってきてくれたのが薫だった。グラスホッパーの奥さんに頼まれて届けに来たのだという。翌日、瑠璃子は礼を言うために新田と薫のいる工房を訪ねた。
仕事場の光景が物語に色彩を与える。チェンバロは3台あった。扉の近くに黒っぽい2段鍵盤の楽器。薫の後ろには白地に金色の模様を巡らせ、蓋の内側に外国の田舎の風景(湖と茂みと石造りの建物)を描いた1段鍵盤。窓際に置かれた未完成品には、響板に小鳥と草花の絵が描かれていた。現代のピアノとは違い、チェンバロにはしばしば、華やかな装飾が施される。作者には笑われるかもしれないが、私はここで、グラスホッパーの孔雀を思い出した。孔雀が羽を大きく広げて美しい模様を見せるのと、蓋を開けたチェンバロが内に秘めた絵画を鑑賞に供するのと、どこか似ているような気がする。
新田は楽器に絵も描いたのだろうか。勝手にそうだと想像しておこう。瑠璃子がレンブラントの描く女性(妻のサスキア)に似ていると言ったのも、飼い犬ドナの本名がドナテロ(イタリア・ルネッサンスの彫刻家ドナテッロ?)であるのも、彼の美術に対する関心の深さを示しているではないか。
新田についてもう少し語ろう。元はウィーンに留学したピアニストで、コンクールにも入賞したことがあるが、ある時から人前で演奏することができなくなり、楽器職人に転向した。チェンバロ製作はベルギーで勉強し、3年前に離婚して現在は独身。
薫は長崎出身で牧師の娘。短大を出たあと、父親の教会で日曜学校の世話をしたりオルガンを弾いたりしていた。教会で古楽のコンサートがあったとき新田のチェンバロと出会い、制作者を目指して弟子入りした。
三角関係の重なり合いについては先に述べたが、作者はほかにも、つながりのある事物のセットを幾つも埋め込んでいる。たとえば<目>に関して。瑠璃子の夫は眼科医で彼の愛人は視能訓練士、老齢のドナは目を病み、瑠璃子が今取りかかっている仕事の一つは、盲目の元霊媒師(96歳)が書いた自叙伝の愛蔵版。新田は作業中の事故で怪我をしたとき、眼鏡を落として割った。
もちろん、一番大きな仕掛けは何度となく登場する『やさしい訴え』だ。弾くのはいつも薫である。瑠璃子は新田に弾いてほしいと思うが、いくら頼んでも断られる。人前で弾けないのはピアノもチェンバロも同じだから、当然と言えば当然。ところが瑠璃子はあるとき、新田がこの曲を弾き、彼の傍らに薫がたたずんでいるのを偶然見てしまった。瑠璃子は、二人が「わたしと新田氏が肉体を結びつけた場所とは遠く離れたところで、もっと深い至福に浸っていた」と思い知らされる。
瑠璃子をめぐるこのあとの展開は急だ。夫の愛人が妊娠したと知って離婚に踏み切る一方、新田からは薫を愛しているとはっきり聞かされる。母が別荘を売りに出し、自身は東京での新しい仕事を決める。冒頭に出てきたヴァイオリン曲の謎も解けた。瑠璃子のハミングを聞いて新田が教えてくれた曲名は、チャイコフスキーの『懐かしい土地の思い出』。瑠璃子はこの曲を心の中に響かせながら、子供時代からの思い出が詰まった別荘地へ旅立ったのだった。
最後の方に素敵な場面がある。新田が最近作ったチェンバロの完成を祝うパーティーだ。楽器に付ける制作者名の字体は瑠璃子がデザインした。薫が3曲チェンバロを弾くと休みを入れてワインと共に何か二つ食べる。バッハの『アリア ト長調』『シンフォニア第5番 変ホ長調』『イタリア協奏曲』が終わるとブルーチーズとキャビア、クープランの『葦』『優しい恋わずらい』『小さな風車』のあとは生ハムとメロン、デュフリの『メヌエット ハ短調』『デュ・ビュック』『アルマンド』で一息ついてローストビーフと海老のカクテル、パーセルの『二つのメヌエット イ短調』『ロンド ニ長調』『グラウンド ハ短調』ではワインもう一杯とチョコレート。こうして並べてみると、曲名もメニューの一部のように感じられる。おしまいは瑠璃子がリクエストした『やさしい訴え』だった。
その曲『やさしい訴え』。原題を<Les Tendres Plaintes>といい、『恋の嘆き』の名でも知られる。tendre(優しい、愛情深いetc.)にもplainte(告訴、嘆きetc.)にも広い意味があるので、いろいろな解釈が可能になる。書名に選ばれた題のほかに、もう一つ別の題があると知ってみると、新田にチェンバロを弾いてもらいたいという訴え(実際には、愛してほしいという無言の訴え)、新田の心を自分のものにできない嘆きの両方が同時に意識され、興もさらに深まるような気がする。
チェンバロの縁を引き継いで次に紹介するのは、須永朝彦(1946~2021)のごく短い小説『契』(1970、ちくま文庫『須永朝彦小説選』所収)。須永の作品世界は「耽美的、幻想的」などと評されるが、その傾向を示す掌篇の一つである。
「日はめぐり、また秋の月が満ちる。例年のごとく、私は次のやうな新聞広告を出した」と書き出され、以下の文が続く。「パート・タイマー募集 ★ピアノを弾ける17~22歳の男性でチェンバロに興味のある方 ★九月九日午後八時より委細面談・即決」。ここまで既に、妖しげな空気が漂ってこないだろうか。
9人の応募があった。容姿で5人に、首筋の華奢さで2人に絞り、最後は指の美しさで決めた。満月の夜に<私>が客をする時にに演奏するのが、選ばれた若者の役目だ。
正装した8人の来客(20歳前後の美男ばかり)が現れるのに合わせ、チェンバロに向かった若者は<私>の指示に従い、『最愛の弟の旅立ちに寄せる綺想曲(カプリチオ)』を弾きだした。
バロック音楽に詳しい読者なら、ここで首をかしげるだろう。<弟>は誤りで<兄>ではないのかと。ヨハン・セバスチャン・バッハに『最愛の兄の旅立ちに寄せる綺想曲』(1704)という、チェンバロのための曲があるからだ。兄とは3歳年上のヨハン・ヤーコプのことで、彼がスウェーデン王の楽団へオーボエ奏者として赴任するのに際して書かれたというのが従来の見方だが、近年になって、親しい友人との別れが作曲の動機だという説も出てきたという。いずれにせよ、満月の夜に弾かれたのは、この曲ではなかった。小説の続きを読もう。
演奏が終わると<私>は若者の肩に手を置いてねぎらいの言葉をかけ、彼の華奢な首筋に唇を寄せた。「私の荒れた唇はみるみる艶やかによみがへり、もちろん、八人の青年たちにも血は順次頒(わか)ちふるまはれた」。棺の中に横たえられた若者に<私>が言う。「おまへは、今宵から私の九番目の弟になるのだ」。チェンバロを弾きに来ただけのつもりだった若者は、あろうことか吸血鬼の餌食になり、図らずも<旅立つ弟>にされてしまったのだった。
須永の吸血鬼小説には、チェンバロがよく登場する。没後に筐底から発見された『彼の最期』(創元推理文庫『吸血鬼文学名作選』所収)もその一つだ。舞台はウィーン。広大な邸で吸血鬼の舞踏会が開かれている。<バロック調の精華を偲ばせる目も彩な衣裳>をまとった8人の男女(実は女と見えた4人も男)が恋人同士のように踊り、アルフレートと呼ばれる青年がチェンバロを弾く。館の主ヘルベルト・フォン・クロロックは、300年前にシレジアの壮大な城館からこの邸に引き移り、以来、8人の青年と暮らしているという設定で、そうすると舞踏会の音楽を担当する楽器はピアノではなく、チェンバロでなくてはならない。
演奏曲目が幾つも書いてある。『蝙蝠』『夜の幸ひならむため』『天使のごとき羊飼』『われら夜を頌(たた)へむ』『めざめよと呼ぶ聲あり』『夜は誰がために』『血の恵み』『美しき満天の星』。このうち『めざめよと呼ぶ聲あり』は、バッハ作曲のカンタータ140番に含まれる曲(後半が<呼ぶ声が聞こえ>になっている訳も多い)のことだと気づく人もいるだろう。さまざまな楽器のために編曲され、耳にすることの多い有名な曲である。
しかし、この夜演奏されたのは<古い舞曲>だと書かれている。バッハのカンタータはそこに当てはまらない。『夜の幸ひならむために』『われら夜を頌(たた)へむ』『夜は誰がために』『美しき満天の星』と同じように、<夜>に関係づけられた曲名であろう。承知のように、吸血鬼が活動するのは夜である。
では『蝙蝠』は? ドラキュラはコウモリや狼に変身する。『血の恵み』は説明の必要がないだろう。『天使のごとき羊飼』がよく分からなかったが、やはり吸血鬼にちなむ言葉なのだと思われる。
また、『就眠儀式』(1970年、『須永朝彦小説選』所収)で青年がチェンバロで弾くのは『誰が私たちに血の泉を与へるのか』。<血の泉>は<知の泉>との語呂合わせだろうか。<血の恵み>が<主の恵み>と響き合うように。
ところで、怪奇映画の音楽といえばパイプオルガン、という一般的なイメージがあるのではないだろうか。しかし、うなるような大迫力の音は須永の繊細な文学に向いていない。やはりチェンバロのかそけき響きが似合うと思う。(松本泰樹・共同通信記者)
まつもと・やすき1955年信州生まれ。30年以上も前のことになるが、須永氏の自宅でインタビューをさせてもらったことがある。彼が編者を務めた国書刊行会の『鏡花セレクション』が出た時だった。私の記憶に間違いがなければ、和机に掛けられたテーブルクロスは、黒字に真っ赤な唐辛子が散らされた模様の布だった。今思えばこれも、吸血鬼につながるイメージの意匠ではなかったか。