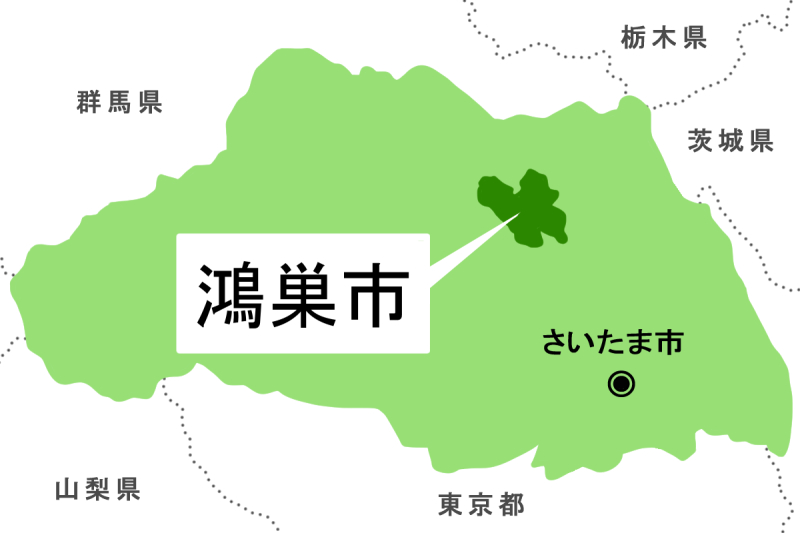【逍遥の記(29)】言葉の奥に横たわる沈黙を見る 13回目の震災展、自分の詩型や表現乗り越える試みも
2013年から始まり、今年が13回目となる日本近代文学館(東京都目黒区駒場)の震災展。今回は展覧会のタイトルを「海、山、人、黙(もだ)す―震災と言葉」と名付け、これまで以上に批評的な視点を取り入れて開催している(3月29日まで)。担当の編集委員は、館副理事長で詩人・作家でもある小池昌代だ。
この震災展は名誉館長の詩人、中村稔の呼びかけで始まった。実作者たちの揮毫、つまり肉筆による俳句や短歌、詩の作品を見せることに主眼を置く。戦後最悪の被害をもたらした東日本大震災と原発事故を中心に、詩歌の実作者が過去の災害にどのように向き合い、表現してきたかを示す試みだ。今年の展示について小池はこんなメッセージを会場に掲げた。
「あのとき、波は壁となり、陸を侵し、船は陸にあがり、看板の文字はばらばらになった。具体的な意味でも抽象的な意味でも、言葉は破壊され、直喩も暗喩も存在意義を失いました。(中略)現実を写し取ろうと挑みかかっても、現実は常に言葉よりも大きい。そこに生じる、ずれ、きしみ、相克。悲劇を前に、私たちは死者たちの沈黙に寄り添い同意する他はありません。表現は、そこを乗り越えて出てきます」
■燃料デブリ
まず新規の揮毫作品2作を紹介したい。
中村稔(1927年~)が今展のために書いた新作「早春の岸辺で」は、燃料デブリのつぶやきだ。燃料デブリとは、原発事故で溶け落ちた核燃料のこと。炉心溶融が起きた1~3号機では計880トンの燃料デブリが生じたとみられている。視点を原発に置き、人間の営為の愚かさを映し出した。
詩の中で、燃料デブリが嘆く。「ぼくもこんな有様で見苦しい限りだ」「何億分の一かを取りだして何が分るのか、知れたものだ。まるでお先真っ暗なのだな」
宮城県塩釜市出身の俳人、渡辺誠一郎(1950年~)の新規揮毫作品も原発を詠んでいる。
〈春の限り炉心の底の潦〉
「潦」は「にわたずみ」と読む。地上にたまり、流れる水のことだ。「春の限り」という季語が、原発事故の起きた春を想起させる。そして、潦は「処理水」とも「汚染水」とも呼ばれて、忌避され、いくたびもの春を迎えている。時間と空間を一挙に把握する季語を持つ詩型の底力を改めて感じる。
■詩型の違い
詩型の違いにも注目したい。特に俳句や短歌は物言わぬ動植物を詠み込むことで「沈黙に寄り添う」強さがある。
〈被曝の牛たち水田に立ちて死を待てり〉という金子兜太(1919~2018年)の作品は、人の言葉を発しない牛の側から震災をみる。
句集「龍宮」が衝撃を与えた照井翠(1962年~)は4句を記している。〈喪へばうしなふほどに降る雪よ〉〈双子なら同じ死顔桃の花〉〈春の星こんなに人が死んだのか〉
そして汚れてしまった雛人形にも、この災害の悲しみを語らせる。
〈潮染みの雛の頬を拭ひけり〉
短歌では、梶原さい子(1971年~)の作品を紹介したい。〈百度も波は来しとふそのたびに陸のかたちを大きく変へて〉〈半身を水に浸かりて斜めなるベッドの上のつつがなき祖母〉〈ぎざぎざの海岸線を咲き継いでゆく椿なり咲き継いで照らす〉。被災者にしか詠めない歌を、覚悟を持って詠んでいると感じる。1首目や3首目の鳥瞰的な視点が効いている。
自らの詩型にとどまらなかった人たちもいる。歌人の永田和宏(1947年~)は、三十一文字では言い終えることのできない気持ちを長歌で表現した。一部を引用する。
〈ただ数に数へられゆく/死者たちのそのそれぞれに/死をなげく家族はあるを/苦しさに寄り添ふと言ふ/悲しみを頒ちあふとふ/そらぞらしき言葉はあるも/寄り添ふも頒つももとより/できるはずなし〉
愛する家族や友を喪った悲しみを抱える人にとって、それが数で表現されるときに感じる理不尽さは想像に難くない。逆に死者数から、残された者たちの悲しみの総体を思うとき、その途方もなさに言葉を失う。
俳人の長谷川櫂(1954年~)は、震災時に最初に出てきたのは短歌だったという。「荒々しいリズムで短歌が次々に湧きあがってきた」とのことで、まずは「震災歌集」を出版し、翌年になって「震災句集」を出した。
■厳しい批判
詩人の和合亮一(1968年~)については揮毫ではなく、出版された詩集が展示されている。震災直後に出版された「詩の礫」「詩ノ黙礼」「詩の邂逅」の3部作から、2024年11月出版の最新詩集「LIFE」までが並ぶ。
和合は福島で生まれ育ち、被災した。震災直後、家族を避難させたあと、ツイッター(現X)で詩を発信した。「放射能が降っています。静かな夜です」。平明な言葉は世界中の人たちに届いたが、詩壇からは厳しい批判にさらされた。このことを振り返り、小池が言う。
「あのときの和合さんの詠み方は、現代詩の禁を犯したというか、ある意味で現代詩を破壊したと思う。でもそのことによって、現代詩のこれまでを乗り越えたともいえる」
あまりにも大きな災厄に直面し、自分の詩型や表現を壊して立ち向かった人たちの格闘を思うとき、戦争や原爆の悲惨さを直後に書いて非難された人たちのことが頭をよぎる。
小池は展示パネルで和合の最新詩集「LIFE」について書いている。「屈折を織り込んだ繊細な表現には、ユーモアと透明感があり、言葉の向こう側に、今なお、2011年3月が透視される」
今年は戦後80年だが、例えば東日本大震災から80年後、どんな言葉が残り、震災を伝え続けているだろう。「震災を書く」営みは今後も続く。(敬称略/文・写真は田村文・共同通信記者)