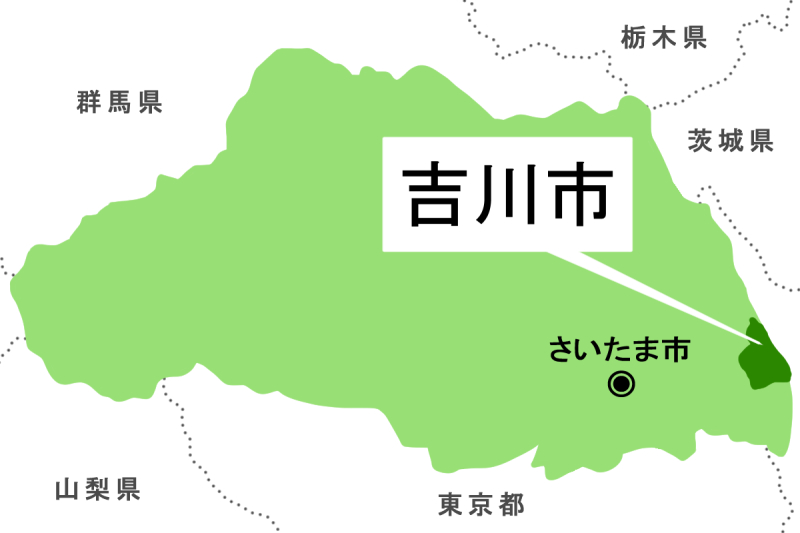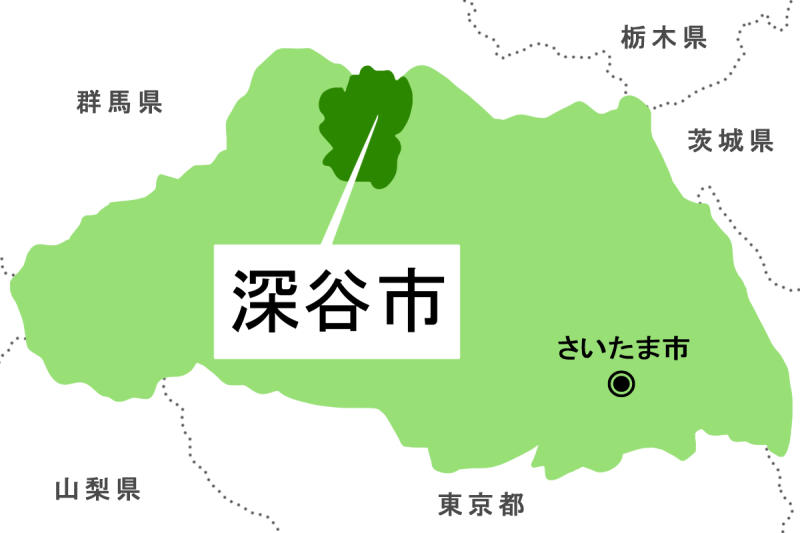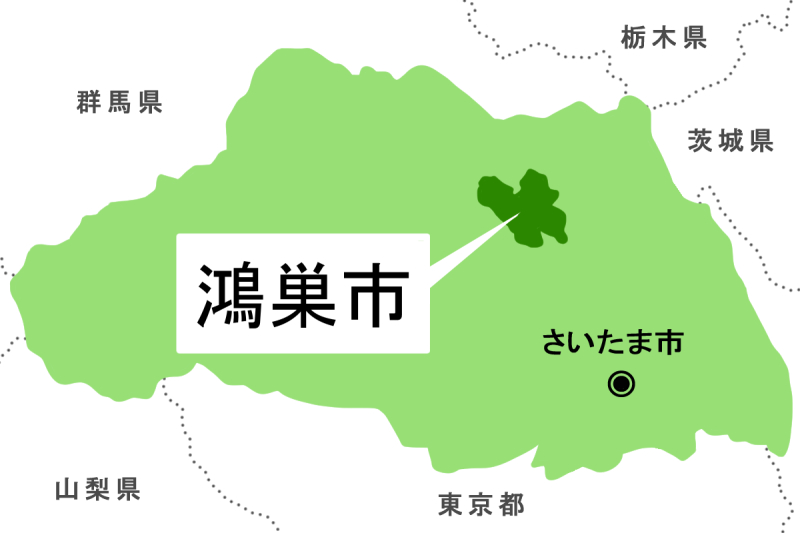【3分間の聴・読・観(32)】ラストから味わう読者の特権 1人から始まる心の揺れとは
今までに出合った本の中で、再読したいものは何冊あるだろう。未読の書は数え切れず、新刊も次々と現れる。読むのは大好きだがこの先は何ともおぼつかない。そう自問するわが身に斎藤美奈子の新刊「ラスト1行でわかる名作300選」は刺激になった。名著の最後の1行に着目して読みどころを示し、作品の真意を掘り下げている。
「サイエンスの香り高い小説を神話に押し込めるってどうなのよ」など、切れ味よく迫る筆致に運ばれて、私も再読か初めてかを問わず手に取りたくなる本のリストができた。優れたブックガイドでもあり、ツッコミに教えられる仮想読書会のようでもある。
「吾輩は猫である。名前はまだ無い」「メロスは激怒した」。書き出しが有名なこれらの名作も、最後の1行はそれほど知られていない。言われてみれば確かにそうだ。結末が先に分かってしまうと楽しみや意欲がそがれる気もするが、当代の読み巧者である斎藤はこう喝破する。
「だいたい、ラストが割れたくらいで興味が失われる本など、最初からたいした価値はないのである」。再読にも通じる卓見と言っていい。何度でも感動したり、新たな意味を発見したりできる作品は強度と柔軟さを兼ね備え、時代を超えると私も思う。
そんな名作をそろえた「ラスト1行で…」には、ひざを打つ批評がいくつもある。ぜひ本書で実感してほしい。例えば夏目漱石の「坊っちゃん」は無鉄砲な熱血漢の物語をイメージするかもしれないが、題名はひ弱そうな「坊っちゃん」。なぜか。斎藤はラストから折り返して答えを導く。
最後の一文は「だから清(きよ)の墓は小日向の養源寺にある」。主人公を心から「坊っちゃん」と呼んだのは、ばあやの清だけだった。清は亡くなる直前、坊っちゃんの寺へ埋めてほしいと懇願する。そしてこのラスト。「大好きなばあやの前で懸命に虚勢を張る男の子」が主人公の真情として浮かび上がる。「だから」の重い意味に感じ入った。
「ノンフィクション篇」も面白い。中でも「共産党宣言」「学問のすゝめ」の章が秀逸だ。これをラストで斬る意外性はもちろん、斎藤の評言もいい。「共産党宣言」の最後の一文「万国のプロレタリア団結せよ!」(大内兵衛、向坂逸郎訳)に立ち上がった人も、たたきつぶそうとした人もいたと指摘し、「世界を変えたという意味で、最強のキャッチコピーだったことはまちがいない。人を動かすのは、やはり言葉の力なのである」と明快だ。
「学問のすゝめ」の最後は世界の広さ、人間の多様さをさとす一説で閉じられる。その一文を引いていわく「人間関係で悩む若者にはぜひ一言。諸君、『人にして人を毛嫌いするなかれ』だよ。福沢諭吉もそういってるよ」。
作者が擱筆(かくひつ)した地点から振り返り、全体の風景を見渡すことで意図に近づく。これが読書のだいご味であり、読者の特権でもあると再認識した。
たいていの場合、人は本を1人で開き、心に兆すなにがしかの揺らぎを通して著者と対話をしている。むろん本に限らない。新譜「天上の音楽」の聴き心地は、読書する心の揺らぎに似ている。佐藤友紀のトランペット、大木麻理のポジティフ・オルガンのデュオが「アヴェ・マリア」や「来たれ、異教徒の救い主よ」といった曲を静かに深く奏でる。
ポジティフ・オルガンはパイプオルガンの一種だが、ホールに設置するのではなく、持ち運べる大きさで、宗教曲の通奏低音によく用いられる。冒頭のトレッリ「ソナタ ニ長調」から、人の手の動きを感じる繊細さに引きつけられた。端正で艶やかなトランペットも聴き手を包み込む。アルバムを聴き入るほどに、曲がもたらす心の微細な動きが意識できる。1人で名作をひもとくときの感覚と言えばいいだろうか。
読むも聴くも、始まりは1人である。(杉本新・共同通信文化部記者)
【今回の作品リスト】
▽斎藤美奈子「ラスト1行でわかる名作300選」
▽佐藤友紀・大木麻理「天上の音楽」
すぎもと・あらた 「ラストの一文は新たな確執の予兆だね」「あんたが目立つなっちゅうの」「チェッ」。こういった決めぜりふも楽しめる「ラスト1行で…」。本文で引用した「サイエンスの香り高い小説」とは、映画化されたあのSFです。