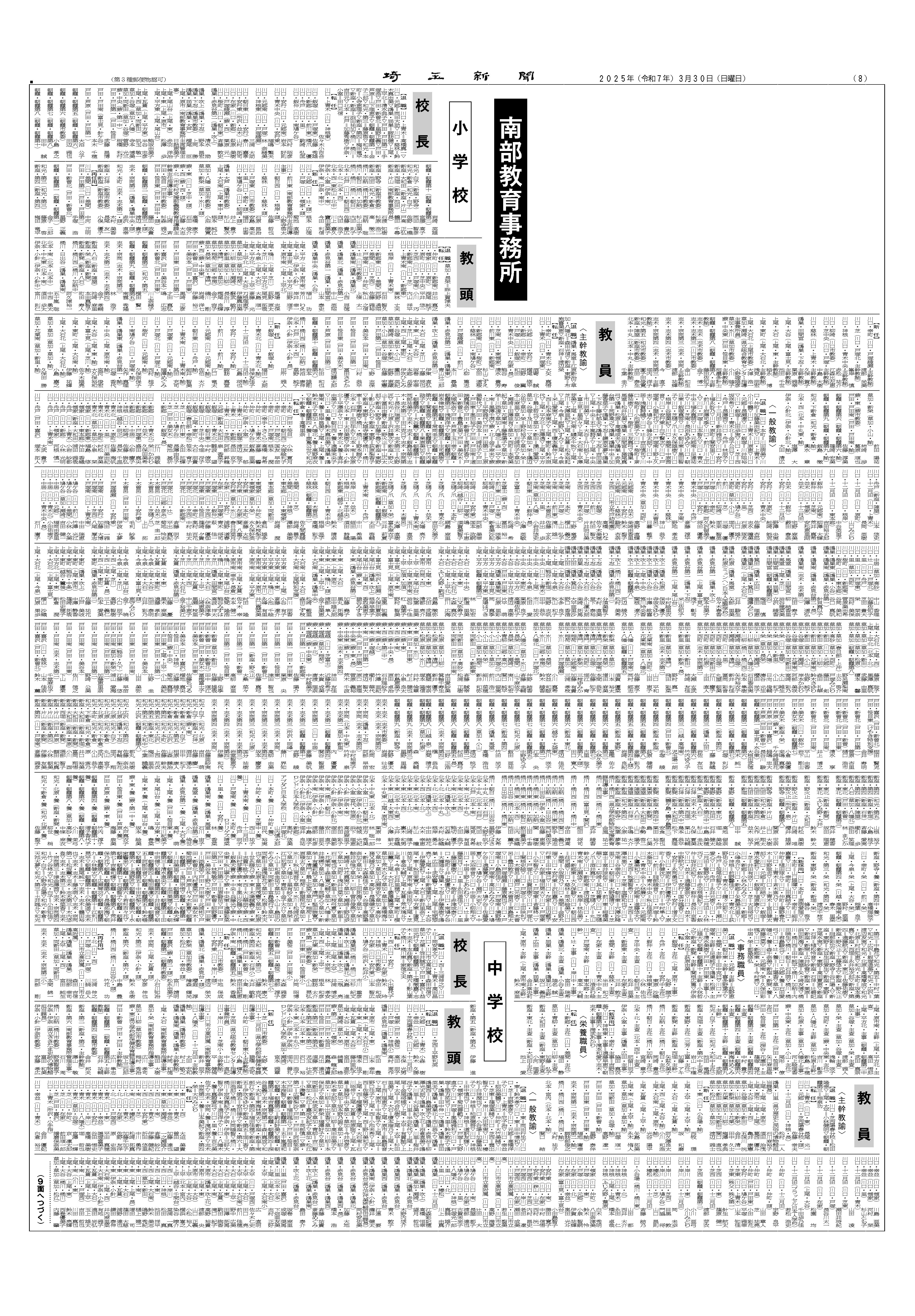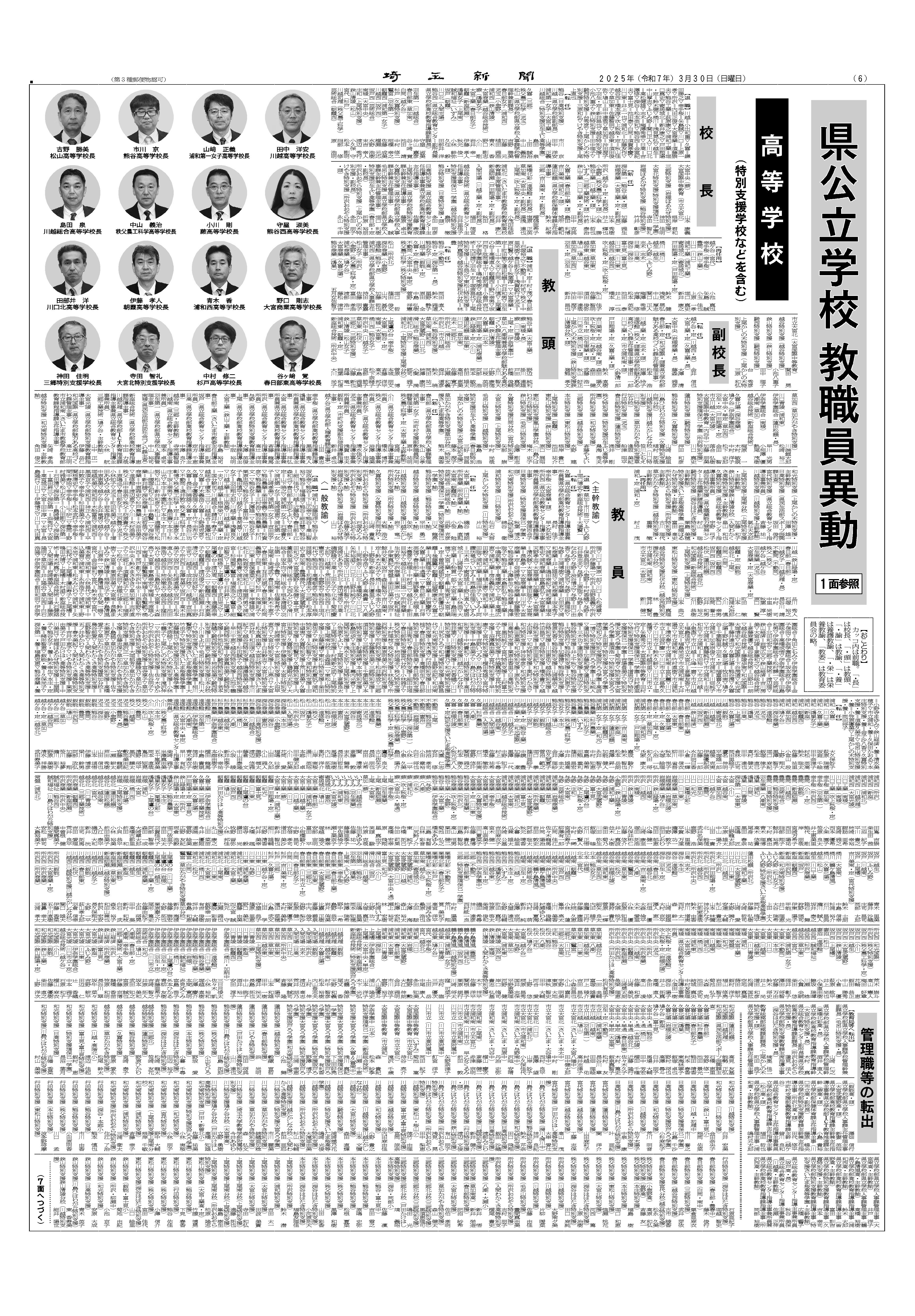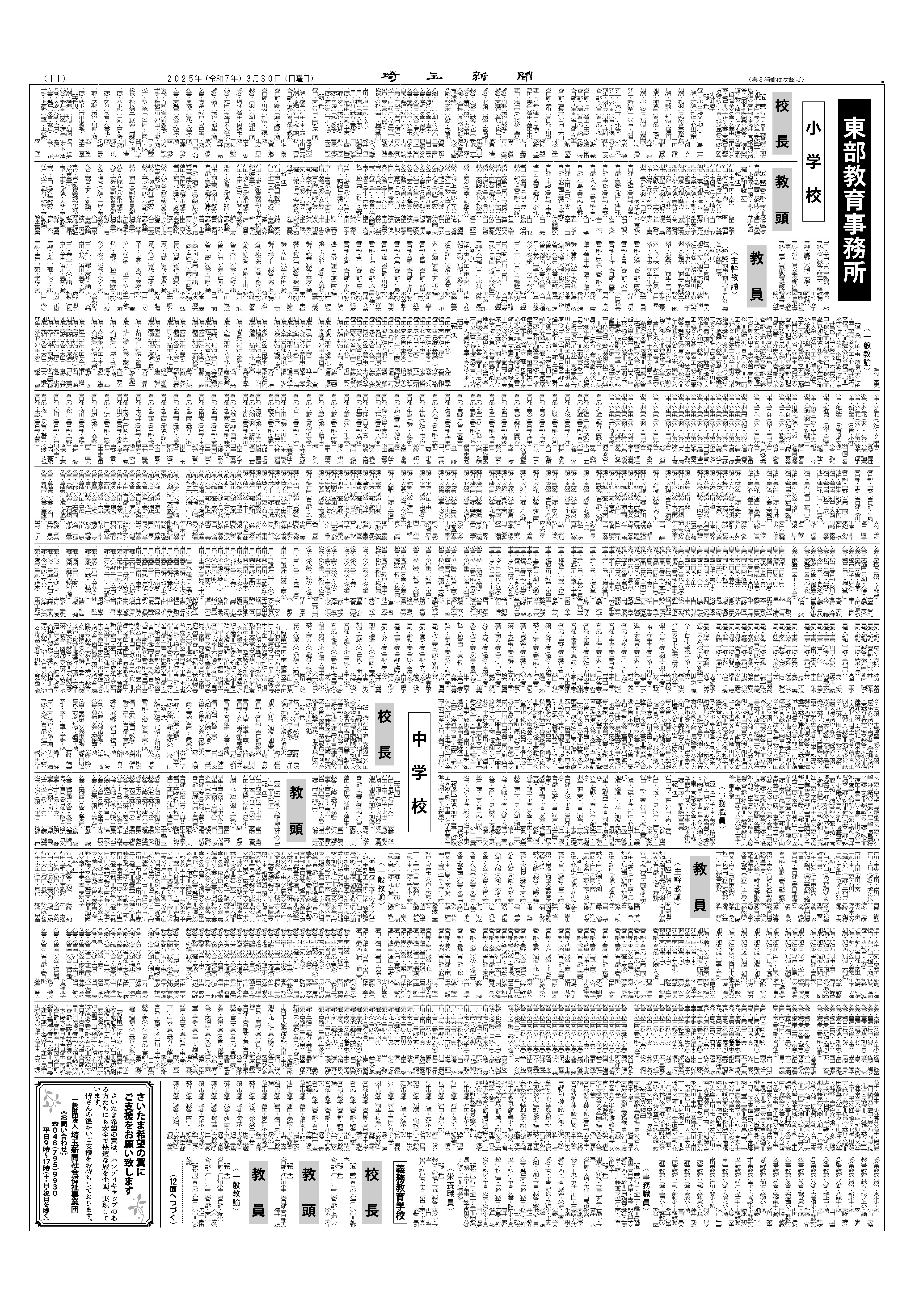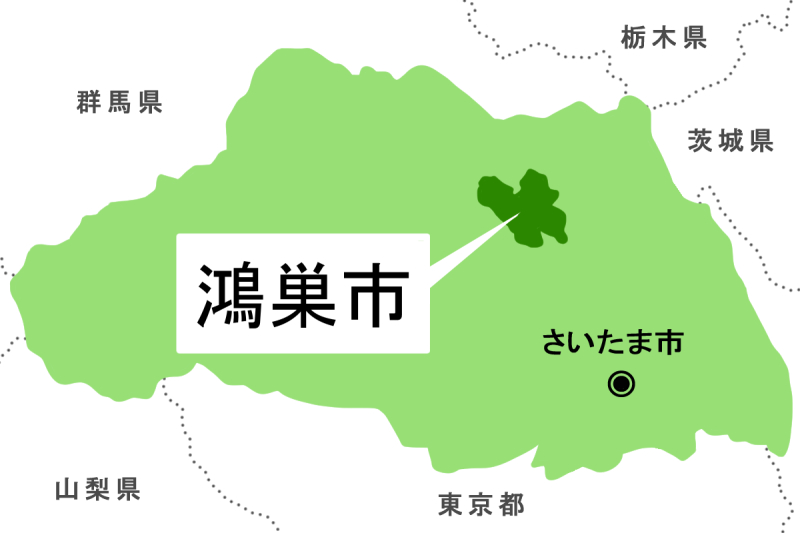【逍遙の記(30)】被害者と加害者の間の深い溝 闇から光明を見いだした人の言葉
被害者と加害者は時に入れ替わる。誰も傷つけず、誰にも傷つけられないで人生を終える人はおそらくほとんどいないだろう。しかし、両者は時間の流れ方がまったく違う。被害者と加害者の間には深い溝がある。
■押し寄せる惨めさ
作家の朝比奈あすかの小説「普通の子」(KADOKAWA)は小学校でのいじめ問題を扱い、加害者と被害者の認識の違いの大きさを浮き彫りにする。
夫と同じ会社で働く佐久間美保はある日、小学5年生の息子が学校の2階ベランダから飛び降りたという連絡を受ける。息子は踵を骨折し、入院した。一体、何があったのか。理由を尋ねても、息子はなかなか話をしてくれない。教師や親たちから事情を聴くうちに、背景にいじめがあると分かってくる。息子は被害者なのか、それとも加害者なのか。真相を探るうちに、美保自身が小学生だった日々がよみがえる。
美保は3年生の頃はいじめられていた。首謀者はアケミだ。その経験があまりにつらかったから、5年生のときに男子の野々村や女子のエリがターゲットになると、いじめる側に回った。かばえば、やられる。教師も止められない。小学校時代は楽しくなかったが、美保は「生き延びた」と思っていた。
そんな昔の話を聞かせると、夫が「野々村くんはどうなったの」と聞くので、こう言った。「どうだったかな。ちゃんとは覚えてないけど、新しい先生がしっかりしていたから、六年生ではもういじめられていなかったと思う」。同じように、エリも乗り越えたはずだと信じていた。
いじめられた側はどんな日々を送り、いまはどう思っているのか。後日談の一端が小説の後半で明かされる。いじめる側、いじめられる側の溝の深さと暗さ、そのリアリティーに戦慄する。でも想像力を少し働かせれば分かる。被害者を生きる時間は過酷で、密度が濃い。苦しみ一色になり、夢の中にまで惨めさが押し寄せる。誰も助けてくれなければ、その現実に打ちのめされる。学校が近づけば憂鬱になり、教室に入ろうとすれば足がすくむ。孤立し、世界が敵になったような気分になるだろう。
■男でも女でもない
盛岡市に住む作家の木村紅美は、小説「熊はどこにいるの」(河出書房新社)で生き惑う4人の女と1人の男児の物語を紡いだ。4人はみな傷ついているが、だからといって誰かを傷つけないわけではない。被害者の中にも暴力性や支配欲があり、だからこそ罪の意識も持っている。
暴力から逃れてきた女たちをかくまう「丘のうえの家」に暮らすリツは幼少時、叔父から性暴力を受けたことで、徹底した男嫌いになった。本人の意志とは関係のない幼い頃の経験が影響を与え続けているのだ。だからこそ、同居するアイが拾ってきた男の赤ん坊を「男でも女でもない、透きとおった性の子にしたい」という欲求を持つ。ジェンダーを巡るある種の実験といえるかもしれないが、同時にそこにはやはり加害性が潜んでいるように思えてならない。
だが、そんなリツに、自分の罪を告白する女性もいる。物語の後半、サキという女性がリツに言う。「わたし、殺しました、生みたての赤ちゃんを」。リツは「殺したのは、わたしも、同じかもよ」と応じて、言い添える。「むかしは、貧しい村じゃ、子どもは生まれるなり水死させたりもしたの。(略)だって、生かしておいても餓死が待っているんだからね」
リツもサキも、被害者であると同時に加害者だ。そう自覚するような人たちを、この作家はこれまでも描いてきた。
■目に見えない恐怖
元フジテレビアナウンサー、渡邊渚のフォトエッセイ「透明を満たす」(講談社)を発売直後に読み、そこに記されている被害体験の壮絶さに衝撃を受けた。生命を脅かすような出来事(トラウマ体験)の中身は記されていないが、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を患った1年半の苦しみを平明な言葉でつづる。
「2023年6月のある雨の日、私の心は殺された」。それは大げさでもなんでもない記述だと、読んでいくと分かる。眠れない、食べられないが重なり、どんどんやせていく。体力、気力、仕事…。手にしていたものを次々と失い、未来が見えなくなる。入院しているとき、「ギャー」という幻聴が、実は幻聴ではなく自分の叫び声だと気づく。自分で自分を殺したくなる衝動に駆られる。まだ20代、未来がきらきら輝いていたはずなのに。
「同世代の友人たちは結婚や出産、昇進、転職などでライフステージが変わっていくなか、私はベッドに寝て天井を見上げることしかできず、社会から隔絶される孤独感は筆舌に尽くし難い苦しみでした。少し気分が晴れて元気になったのに、偶然トラウマに関することに触れてしまって症状が悪化したこともありました。目に見えない恐怖がずっと心と頭を支配して、この真っ暗闇が一生続いていくのではないかと思ったら、生きている意味を見失い、自分で自分を傷つけてしまった日もあります」(「まえがき」より)
そこからどうやって、再び生きる気力と体力を取り戻していったのか。絶望の中にあったとき、知人の女性が涙を流しながら「幸せな未来は絶対に来る」と言ってくれたこと。精神科の主治医が「こちらから手を離すことは絶対ない」と約束してくれたこと。彼女を支えてきた言葉が幾つも紹介されている。
彼女が苦しんでいる間、彼女に加害行為をした側の人たちはどんな日々を過ごしていたのだろう。彼女の交流サイト(SNS)には心ない言葉が書き込まれることもあったというが、それでもそれを閉じなかったのは「私をPTSDにした人たちに『私の言論は止められない』と訴えたかったからだ」という。 そして、読者にこんなメッセージを送る。
「あなたの人生はあなたのもの。誰にも奪えない。真っ暗な日々は永遠には続かないし、絶対に夜は明ける。だから生きたい人生を諦めないで」
どん底の闇にいた人が、周囲の助けを得ながら見つけた光明と言葉たち。その力強さが、多くの被害者たちをきっと励ます。(敬称略/文・写真は田村文・共同通信記者)