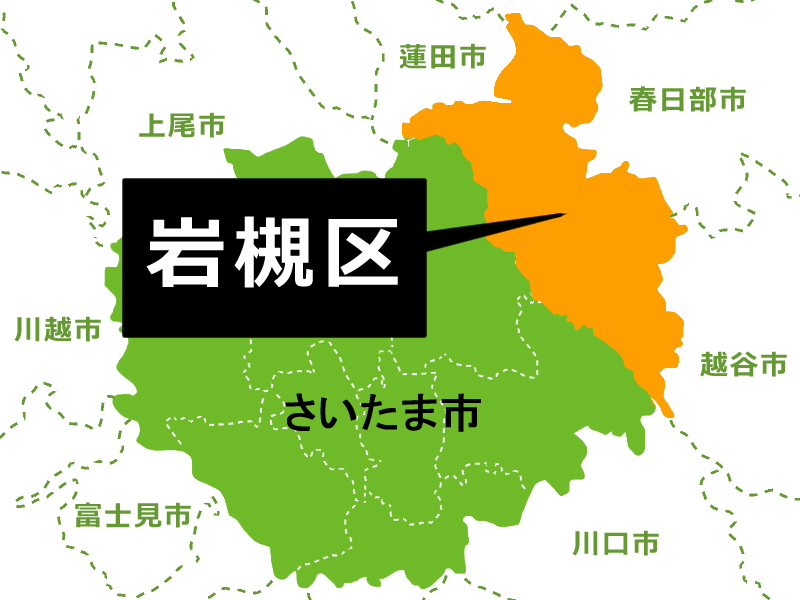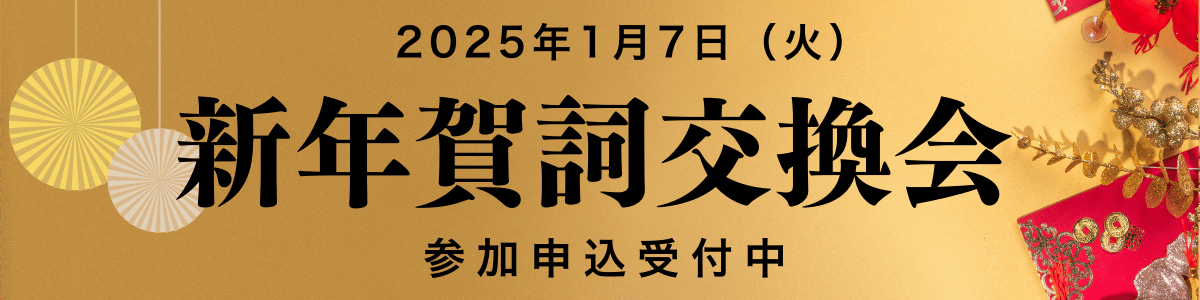夫倒れ入院…妻は面会禁止、探る最期の言葉 見つめ合うことも叶わず夫天国へ 妻つづった最初で最後の恋文
埼玉詩人会(川中子義勝会長)が主催する「第29回埼玉詩人賞」に、熊谷市の里見静江さん(70)の詩集「足もとの冬」(土曜美術社出版販売刊)が選ばれた。コロナ禍で面会もままならない中で逝った夫へ、最期に言えなかった感謝の言葉、失ってもなお愛しい思いを詩につづっている。
里見さんは九つ年上の夫・南海夫(なみお)さんと職場で出会い、約45年間連れ添った。ともに本が好き。「隣にいて一緒の方向を向いている同志のような存在だった」という。しかし、自閉症の娘の世話をしながら介護職の仕事と詩作、南海夫さんの病も重なり、「ある時から夫の背中を見ているようになった」。
2019年10月、南海夫さんは急性すい炎で入院。一時退院したが、翌年2月29日にこの病気が再発して再入院。3月23日に亡くなった。葬儀や埋葬など自分ひとりで行い、ペンを取る気になれなかった。四十九日を過ぎた頃、「日がたつと風化してしまう。今じゃなければ書けないものがある」と思った。介護職の習慣でふだんから取っているメモを基に「言い残してしまった、言葉までいかないもやもや」を詩に紡ぎ始めた。
新型コロナウイルスの感染拡大が始まった時期に倒れた南海夫さん。車に娘を乗せ、夫を運ぶ救急車の後を不安な思いでついていく。「その日/全国よりも早く/小さな家族の緊急事態は始まっていた」(「緊急事態宣言/二〇二〇年閏日」)。入院した病院ではまもなく面会禁止に。「患者とキーパーソンは/みつめ合うことも話すこともできず/言い遺したい言葉を別々に探っている」(「三月のドア」)。
桜が咲く頃、夫は天国に旅立つ。部屋に残された2人の本を片付けながら、若い頃に丹羽文雄について語り合ったことを思い出す。「不在となった男に一度だけ送ろう/書いたことのない恋文を/まためぐりあって/本の話をしましょう」(「恋文」)。
最後の詩「もしわたしであったならば」でこう締めくくる。「群青に変わりはじめた空に/両手をかざして 深呼吸しよう/たまわった さびしいばかりの自由に ありがとう と言おう」。
存命中に南海夫さんのことを詩にすることはなかった。晩年は「空気のような存在」だった夫。男と女の関係だった頃を思い返し、最後の言葉を贈った。「(夫は)あまり表に出るタイプじゃない。まさか詩に書かれるとは思っていなかったでしょう。天国で照れ笑いしていると思いますよ」。