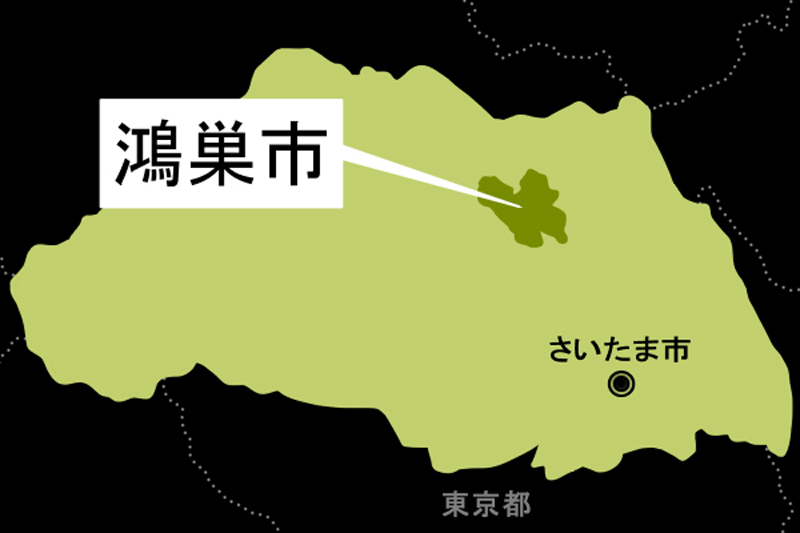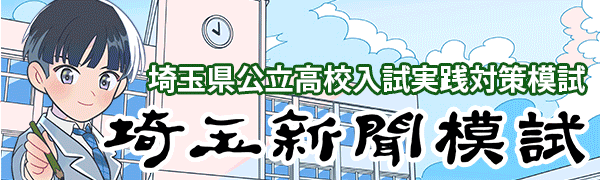若者は即戦力、勉強より戦争が大事…戦闘機の部品製造にささげた青春 宮代の女性、断片的な当時の記憶語る
戦後75年がたち、「周りはもう、戦争を知らない人たちばかり。当時の話はすることはないと思っていた」と宮代町の山野井八重子さん(91)は語る。女子学生が軍需工場などで労働に従事する「女子挺身(ていしん)隊」の一員として、群馬県で戦闘機の部品製造に従事。貴重な青春をささげ、複雑な気持ちで終戦を迎えた。
「当時の記憶も断片的にしか覚えていない」という山野井さんは、群馬県館林市の館林高等女学校(現館林女子高校)に通っていた。太平洋戦争が始まっても、1、2年の時は学校で授業を受けられたが、3年になると、同級生全員が市内の小さな工場に派遣された。
1944年5月。当時16歳の山野井さんは、高校の先輩や都内から疎開してきた学生ら約200人と共に、戦闘機の尾翼製作に従事した。「いつ学校に戻れるのか」と不安に駆られながらも、ペンを電気ドリルに持ち替えて、零戦の鋲(びょう)打ちに日々、汗を流した。
「若者は男女問わず日本の即戦力として扱われた。勉強よりも戦争が大事。勉強をしたいなんて、あの頃は考えることもなかった」
作業中に空襲警報が鳴ると、荷物を抱え、みんなで近くの山に避難した。山野井さんが働く工場は直接の被害は受けなかったが、45年2月ごろ、同県太田市内の工場が甚大な空襲被害を受けて、「次はここに来るのではないか」と、不安に押しつぶされそうになった。
ただ、そんな厳しい生活の中にも、安らげる瞬間はあった。半日作業の時は学校に行き、先生たちと雑談したり、映画鑑賞を楽しんだ。4年の卒業式には、「君が代」と「海ゆかば」を泣きながら歌った。
工場からは1カ月につき、7円50銭の給料が支給された。学校の月謝を払うと、いくらも残らなかったが、それなりの買い物はできた。自宅通勤の山野井さんは「食事も家で取れたので、疎開の人たちと比べたら、まだ恵まれていた」という。戦時下の物資不足で白いご飯は食べられず、モロコシやサツマイモが主食だった。
8月15日の玉音放送は工場内で聴いた。敗戦を知り、「これだけ一生懸命やってきたのに」という悔しさ、「これで戦争が終わる」という喜び、「明日から、学校にも行けなくなってしまうのではないか」という不安が入り交じり、自分がどんな表情で耳を傾けていたのか覚えていない。
「戦争の真っただ中、若さと情熱でとにかく精いっぱい生きてきた」と語る山野井さん。若者と接する機会は減り、戦争の無残さ、平和の尊さを伝えることは少ないが、戦争を知らない人たちにこうメッセージを送る。
「今では、お金を出せば解決できることが増えているが、もっと辛抱をする気持ちを持って生きてほしい」