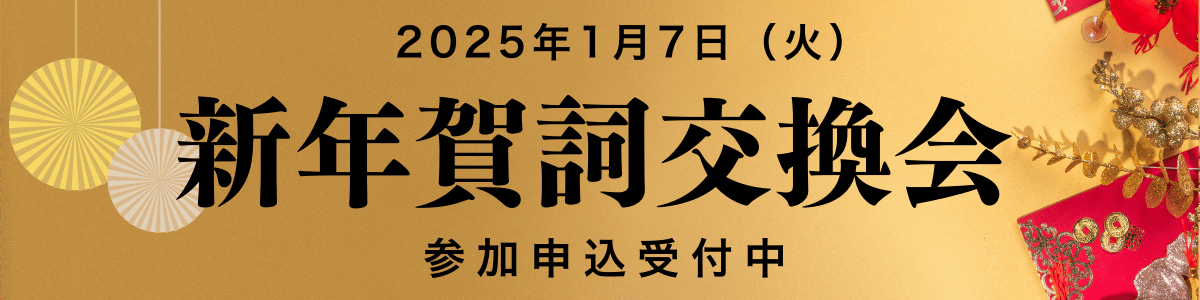「埼玉の思い出あり過ぎる」 芥川賞の九段理江さん AI、幻の国立…現実と接続の世界描く「東京都同情塔」
第170回芥川賞に17日、埼玉県さいたま市出身の九段理江さん(33)の「東京都同情塔」(2023年新潮12月号)が選ばれた。候補入り2度目で栄冠を射止めた。受賞作は、パラレルワールドの東京に現代版「バベルの塔」が建設される物語。九段さんは「現実と小説の世界が接続しているのが、今の私にとって大事なこと」と語る。
九段さんは1990年、旧浦和市生まれで、現在は千葉県在住。子どもの頃は県内を20カ所ほど転居しつつ、高校~大学時代をさいたま市内で過ごした。2021年、「悪い音楽」で第126回文学界新人賞を受賞し、デビュー。太宰治の「女生徒」を下敷きに母娘の関係を描いた「Schoolgirl」(21年文学界12月号)で芥川賞候補に。「しをかくうま」(23年文学界6月号)で野間文芸新人賞を受賞した気鋭の作家だ。
芥川賞受賞作の舞台は、「アンビルドの女王」の異名を持つ世界的建築家ザハ・ハディドさんがデザインした幻の国立競技場がそびえ立つ近未来の東京。この世界では、犯罪者を「ホモ・ミゼラビリス(同情されるべき人々)」と呼び、罰ではなく「幸福」を与えるため都心の豪華なタワマンに居住させる、という思想が浸透。核となる新時代の刑務所「シンパシータワートーキョー」の建設プロジェクトが進行中だ。
主人公の建築家・牧名沙羅は美しいザハのスタジアムと調和するタワーを設計しようとする。日常の一部となった生成人工知能(AI)やオリンピック後の東京、コミュニケーションの分断など現実と地続きの近未来を描く。
昨年、自分で決めたテーマの力作が芥川賞候補に入らず「引退」も頭をよぎった。そんな時、編集者から「アンビルド(建てられることのなかった建造物)のモチーフに興味がある」と言われ、翌日にはもう「東京都~」の構想を完成させていた。受賞会見では「書き続けることを支えてくれた人々に感謝を伝えたい」と顔をほころばせた。
インパクト大のタイトルはシンパシータワートーキョーの訳語。主人公・牧名は「日本人が日本語を捨てたがっている」と嘆くなど「言葉の乱用」についても考えさせられる作品だ。「『言葉を使って何ができるか』を追求するのがライフワーク。小学6年生の時も、デビュー前も『言語』を題材にした文章を書いている。私にとって逃れられないテーマ」と創作を語る。
県南部の県立高校に通っていた際は、通学定期を使える範囲にある全ての図書館を巡ったほどの本好き。未発表だが、故郷を舞台にした小説も手がけている。「埼玉の思い出はあり過ぎる」と笑った。