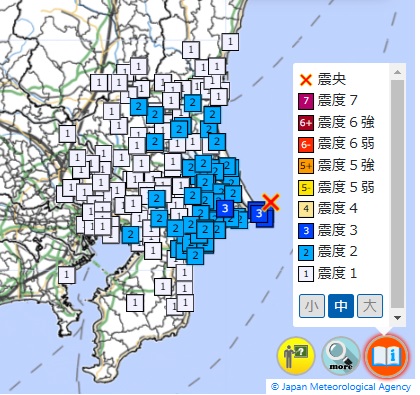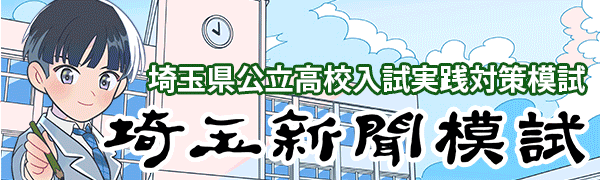【逍遥の記(25)】「緑の野原をうたいたかった」 時空超えて生きる言葉 新川和江を悼む
詩人の新川和江が8月10日、心筋梗塞のため死去した。95歳。年齢からいえば、生をまっとうしたということになるのだろうが、悲しみがひたひたと押し寄せてくる。
女性詩人の中で、石垣りん、茨木のり子、そして新川和江の3人の作品を、私は繰り返し読んできた。彼女たちの言葉に支えられてきたと言ってもいい。だから今、とても寂しい。
でも、ひとたび新川の詩句を思い起こせば、気持ちは前向きになる。彼女の詩は自由で、のびやかで、向日性を帯びている。誰もが分かる平明さ、やわらかな言葉、その核にある強さとしなやかさ。それらが私を励ます。亡くなっても、言葉は時空を超えて生き続ける。
■戦争が出会わせた恩師
長いインタビューをしたのは2005年9月だった。当時、私は「おんな詩(うた)の鼓動」という連載を書いていて、女性詩人や女性歌人の取材を重ねていた。そうして、新川に会った。
取材を申し込むと、自宅近くの蕎麦屋に来るように言われ、カメラマンと2人で出かけた。行きつけの店らしく、注文しないでインタビューをしていても文句を言われることもない。4時間以上も話を聞いた。取材後は「もっと食べなさいな」と促されながら食事をともにした。
76歳だった彼女はとても元気で、実に楽しそうに話した。ゆったりとした語りだった。でもその中から、「詩」への思いの切実さが強く伝わってきた。常に詩を求めてきた人なのだなと思った。
あいさつと軽い雑談が済むと、すぐに戦争の話になった。10代の新川は戦時中もひそかに詩を書いていた。恩師の西條八十に出会えたのも、皮肉にも「戦争のおかげ」だった。
童謡詩人として有名だった50代の西條が、新川の住む茨城県絹川村(現在の結城市)に近い下館町(現在の筑西市)に疎開してきたのを新聞記事で知り、詩作ノートを持って訪ねた。以来、自転車で通った。自作の詩を読んでもらうだけでなく、西條が書いたアルチュール・ランボーの論文を写す作業も、頼まれて懸命に取り組んだ。
「詩を書くなんて軟弱で、非国民のすることだと思われていた」時代だが、新川には詩が必要だった。しかし、いつの間にか西條のもとに通っていることがばれて、教師に「自由主義にかぶれている。反省しろ」と、しかられた。空襲警報が鳴っても防空壕に入れてもらえないことさえあった。
「それでも詩が書きたかった。詩を書くことが、今日生きたのだと感じられる唯一のことでした」
敗戦後すぐの1946年春、女学校を卒業すると同時に結婚した。その後、夫婦で上京し、新川は少女雑誌や学習雑誌に小説や詩を書き、同人誌や文学グループに参加した。旺盛な文学活動だったが「夫から見たら、張り合いのない女だったと思う」。
1955年に長男を出産。「子どもが生まれても、書くことが生活の中心でした」
■拒否を上書きする「稲穂」や「海」
代表作「わたしを束ねないで」を発表したのは1966年、37歳の時だ。
「わたしを束ねないで/あらせいとうの花のように/白い葱のように/束ねないでください わたしは稲穂/秋 大地が胸を焦がす/見渡すかぎりの金色の稲穂」
「束ねられる」ことの拒絶から始まり「止めないで」「注(つ)がないで」「名付けないで」「区切らないで」と続いてゆく。
「こういう気持ちは少女の頃からあった」と明かした。「女は、子どもの頃には親の、結婚したら夫の、年を取ったら子どもの言うことに従わなければならない。でも、そんな生き方ってなんだか悲しい。大人になったら一人の人間として広々と生きてみたかった」
束縛への抵抗の意思を示す言葉が繰り返されるのに、詩全体から頑なな印象は伝わってこない。否定し、拒否するだけでなく、明るく肯定的な自己イメージを提示して、上書きしているからだろう。第1連なら「わたしは稲穂」。その後は「羽撃(はばた)き」「海」「風」「終りのない文章」。
温かくて広く、豊かな気持ちになる。やさしい言葉を使い、リズムもいい。音感が抜群だ。だから覚えやすい。そんな作風は「男たちが書く詩へのアンチテーゼ」なのだと新川は言った。
「現代詩は『この世は荒地』という考えに基づいて出発していて、痛みや傷をモチーフにした詩が主流だった。でも私は、荒地はうたいたくなかった。緑の野原をうたいたかった」
■目指したのは精神の自立
詩人の吉原幸子と、女性を主体とする季刊詩誌「現代詩ラ・メール」を創刊したのは1983年のことだ。「詩を書くことによる精神の自立を目指しました」と振り返った。
「ラ・メール」の出現は、男性主導の文壇・詩壇に一石を投じた。多くの女性たちに書く場を提供し、新人を発掘して育てながら10年間、40号まで続いた。
編集の実務に携わった棚沢永子が2023年8月、書肆侃侃房から出版した「現代詩ラ・メールがあった頃」は、この詩誌の誕生から終焉までの日々をつづる。懐かしさや哀惜にとどまらず、当時の葛藤や混乱、時には怒りまで隠さず書いていて、読ませる。
その疾風怒濤の中でも、新川は包容力を見せている。彼女の立ち居振る舞いこそ、ラ・メールが目指した「精神の自立」の実践だとみるのは、穿ちすぎだろうか。
インタビューの時に聞いた、新川の詩についての考え方を幾つか紹介したい。
「最初に詩人がやることは、故郷を捨てること。そして心を遠くに飛ばすんです」
「詩は生活に入り込まないと駄目。トイレットペーパーに印刷されるのが理想です」
「詩は人間にとって最も大切な生活に密接につながることによって、意味を持つ」
女性の詩というと、初めに新川さんの詩を思い浮かべる。そして「わたしを束ねないで」の詩句が、いつの間にか口をついて出ている。きっとこれからも、彼女の残した詩の言葉に支えられ続けるのだろう。(敬称略/共同通信記者・田村文)