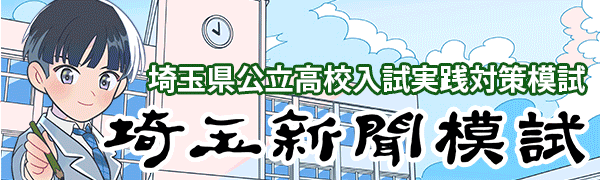【3分間の聴・読・観!(26)】割れてしまいそうな心が生んだ魔力 高揚感が癖になる「ボレロ」と苦い熱量
日ごろ耳にする機会が多いクラシック音楽の一つがモーリス・ラヴェルの「ボレロ」だろう。スネアドラムのリズムが曲をリードし、二つの旋律は木管から金管、弦と楽器を代えながら、打楽器とともに厚みを増していく。高揚感が癖になり、何度でも聞きたくなる。
この曲が生まれるまでの苦闘、喝采の後に訪れた苦悩を描く映画「ボレロ 永遠の旋律」(アンヌ・フォンテーヌ監督)を見てまた聴き直すと、さらに妖しく、味わい深い。
若き日の賞での落選、第1次世界大戦従軍、母親への追慕、プラトニックな愛など、作曲家の人生に影響を与えたエピソードを織り込みながら、「ボレロ」で名声を手にした後、晩年に向かって内面に変調を来すさまを、映画は丹念に描いていく。
今にも割れてしまいそうな作曲家の心は、薄く透き通ったガラスのようだ。主演のラファエル・ペルソナは緊張感あるたたずまいで不安と自信がないまぜになった人物を表現している。
人生に関わる女性たちも魅力的だ。終始寄り添うミシア(ドリヤ・ティリエ)は知的で寂しげな女性だが、ぬくもりのある視線が忘れ難い。ラヴェルに作曲を依頼し、「ボレロ」の初演(1928年)で踊るダンサーのイダ・ルビンシュタイン(ジャンヌ・バリバール)の強い個性は、この曲の魔力を引き出している。
ラヴェルの作品では「亡き王女のためのパヴァーヌ」や「ピアノ協奏曲ト長調」第2楽章などの繊細さ、美しさに私は陶然とするのだが、一方で、世間が注目する「ボレロ」は、自身の他の作品を飲み込むような存在になる。一人の作曲家としてどう受け止めればいいのか。
映画の冒頭、ジャズやアフリカ音楽など思いもよらぬアレンジの「ボレロ」が流れる。しかもそれぞれが違和感なく溶け込んでいる。ほぼ100年の間、人々を魅了する曲にはさまざまな解釈に耐える強さがあることは間違いない。
強さを生んだ人物の揺れる晩年に、誰にとっても分かりやすい答えはないかもしれない。その人生を思い、曲を聴き続けたい。
次々と異なる音色で同じ旋律を重ねていく「ボレロ」の曲想と通じるのではないかと直感したのが、新刊の漫画「哺乳瓶ビールの夏」(ベン・グッドマン作)。こちらは日本の現代、ある大学の学生寮で起こった夏の出来事を描く群像劇である。
飲酒、ゲーム、マージャンに打ち込む、というか時間を費やす学生たちは、年に1度の「祭り」を盛大に催す。いつにも増したらんちき騒ぎに紛れ、寮生の一人で4年生の福本が姿を消した。同じ学年の大塚洋平は福本の行方を寮生たちに尋ねるが、誰も知らない。それどころか気に留める様子もない。洋平自身、祭り当夜は飲み過ぎて記憶をなくしている。
ミステリアスな展開に繰り返し登場する寮生たちはいずれも個性的だ。きっちり寮を管理する4年生の寮長、2浪3留3休学でいったい何歳か分からない大学院生や、嫌みで相手をおとしめてばかりだったり、部屋に閉じこもってアートに打ち込んでいたり、極めてまじめで親切だったりと、さまざまな顔を持つキャラクターたちを見ながら、実際にこういう人はいるなあと納得した。
そんな彼ら、彼女らだが、祭りの高揚を経て、社会に出る一歩手前の焦りが言葉の端々に紛れ込んでいると思った。表向きの顔とは違う繊細な心の内も感じられる。奔放に生きられるような錯覚と期間限定の自由が詰まった学生寮には高い熱量があり、キャラクターがそれぞれの個性でエネルギーを発している。社会に出て何十年もたった大人が忘れてしまった熱さでもある。
高揚が通り過ぎても人生は続く。ラヴェルとこの漫画をつなぐのは、そんな苦さではないだろうか。(杉本新・共同通信記者)
すぎもと・あらた 文化部を経て編集委員室所属。
【今回の作品リスト】
▽アンヌ・フォンテーヌ監督「ボレロ 永遠の旋律」
▽ベン・グッドマン「哺乳瓶ビールの夏」